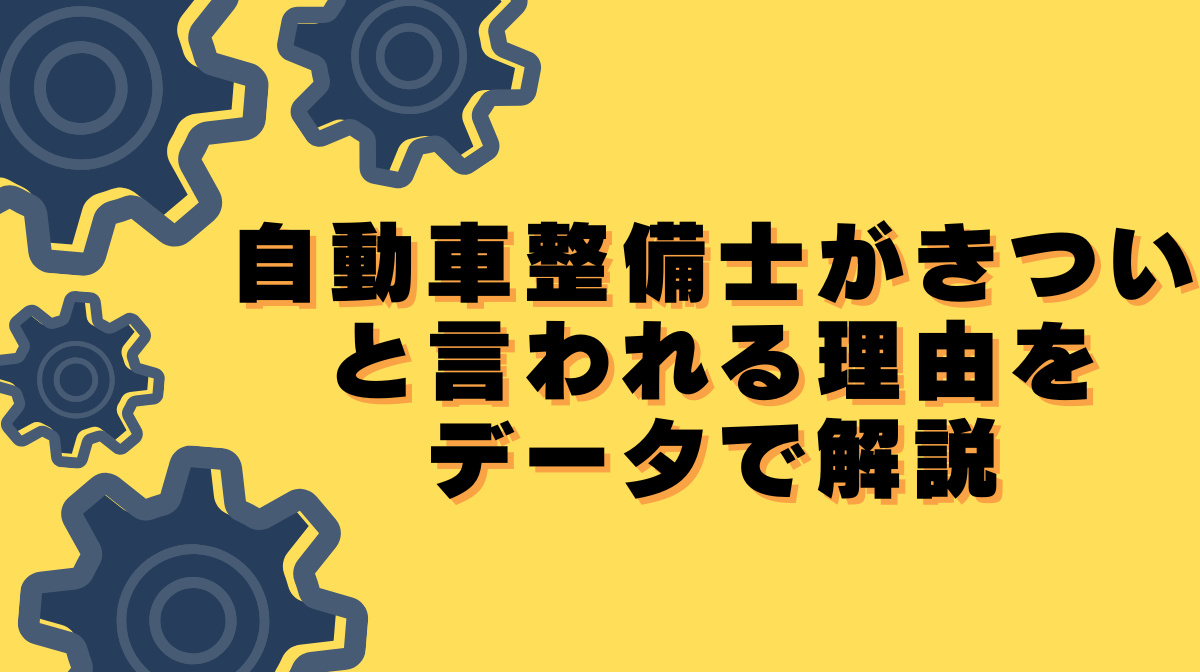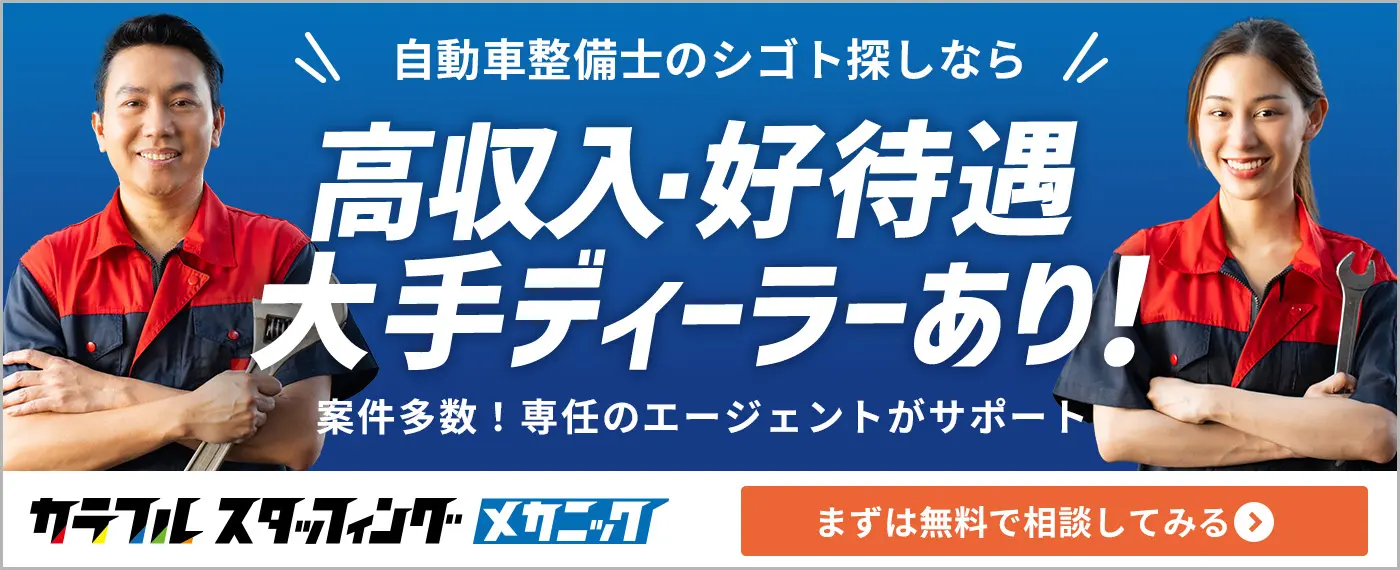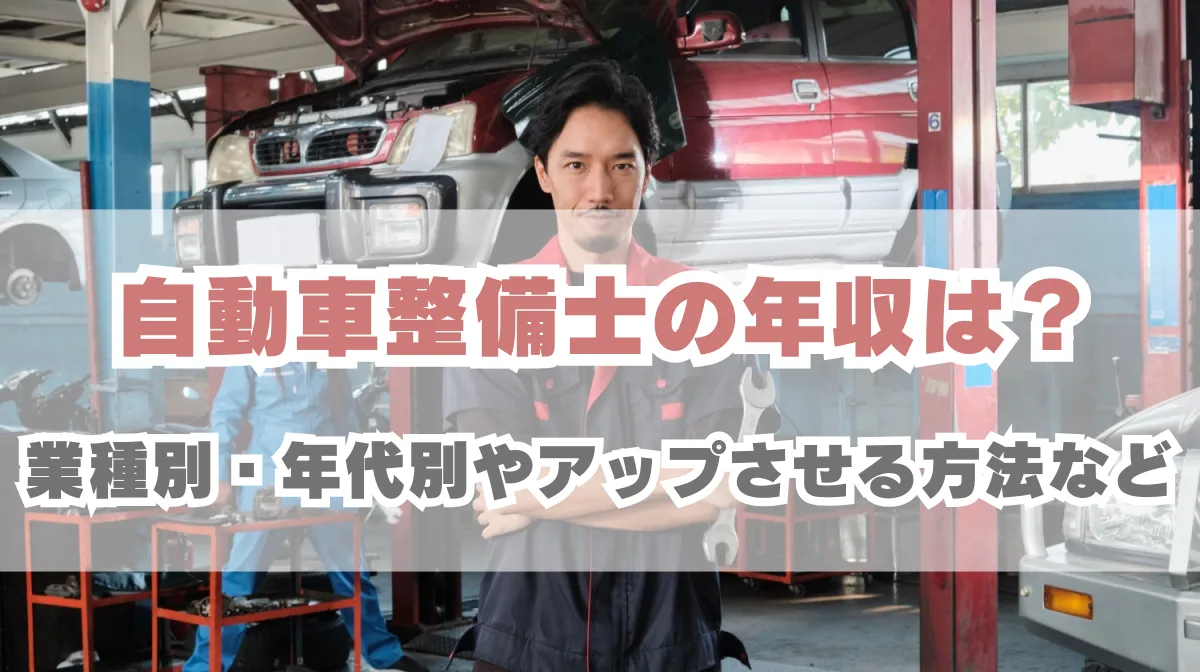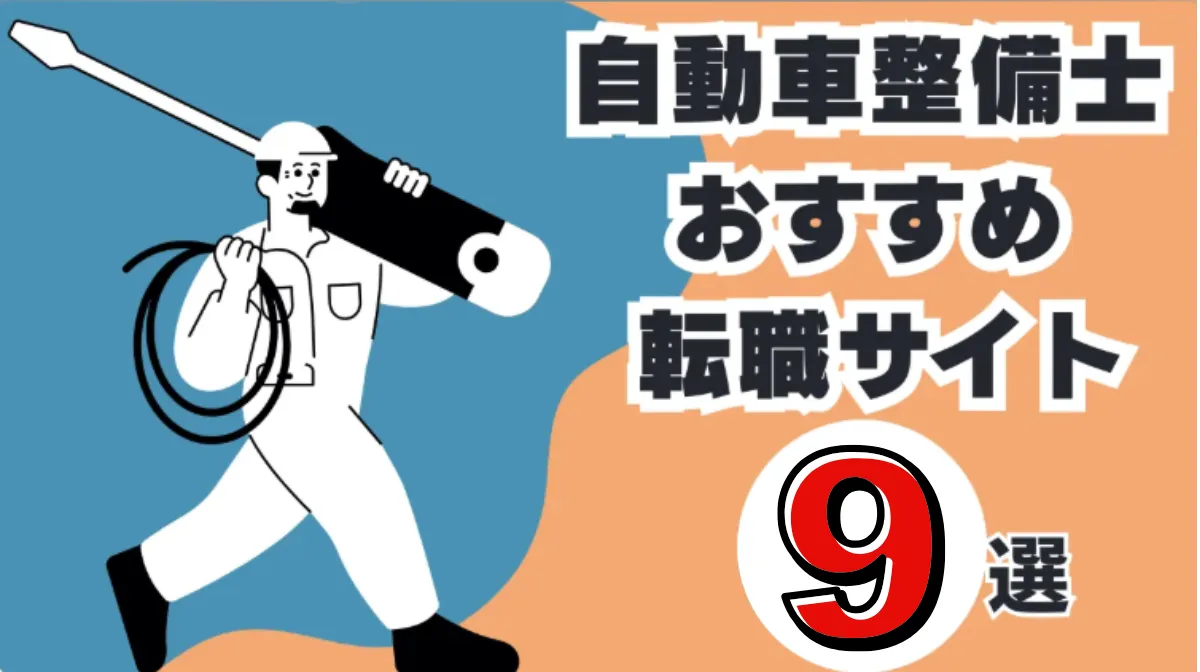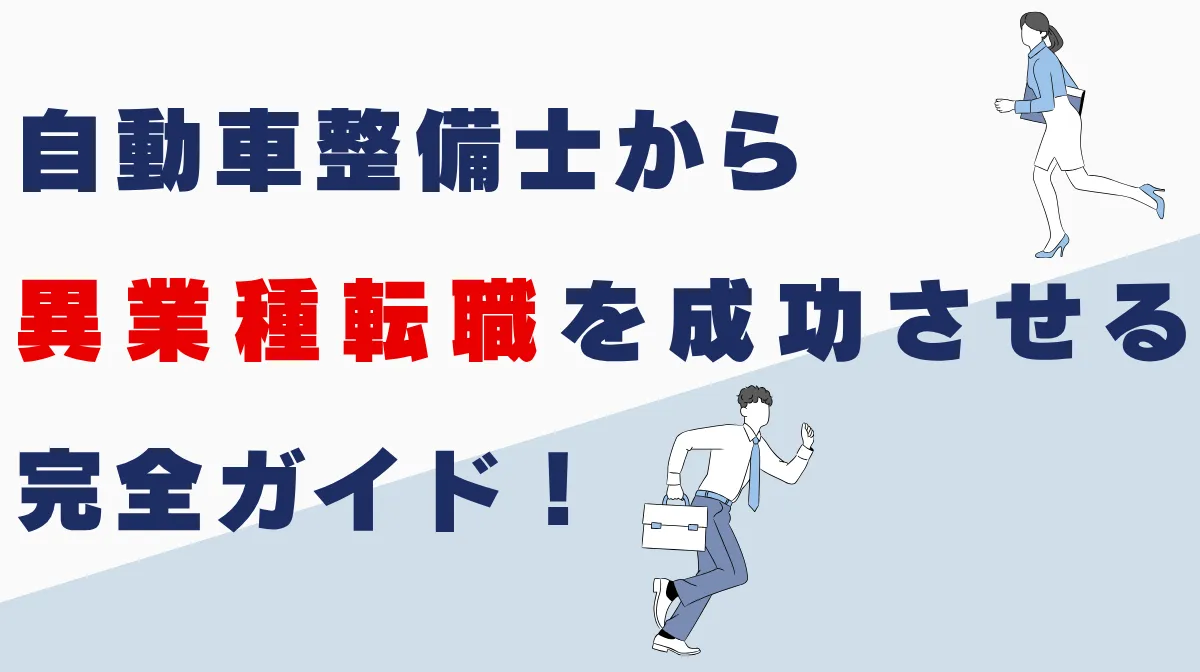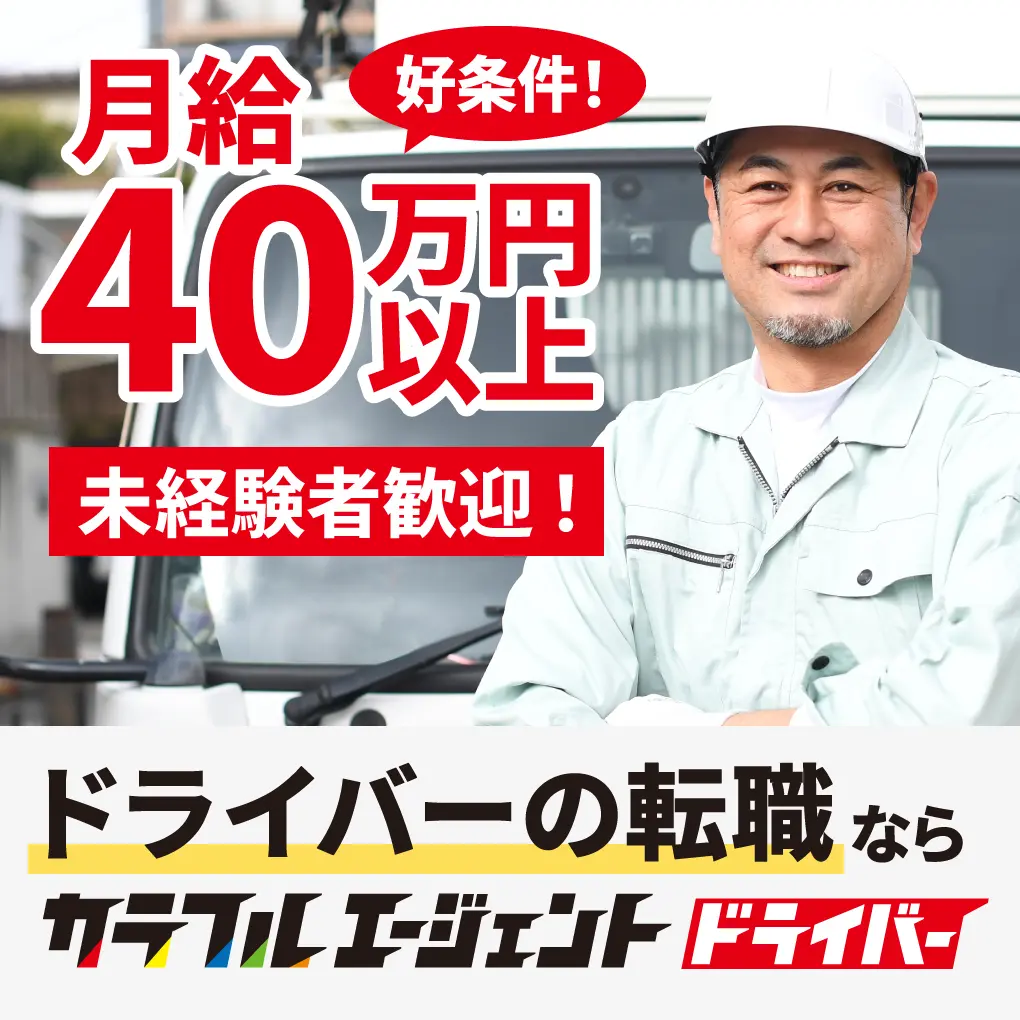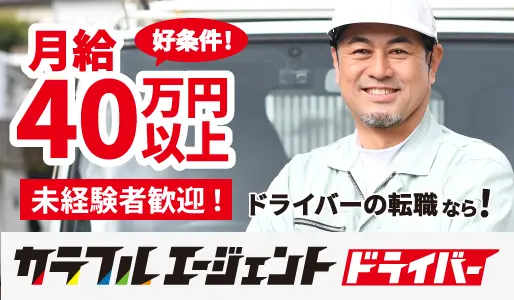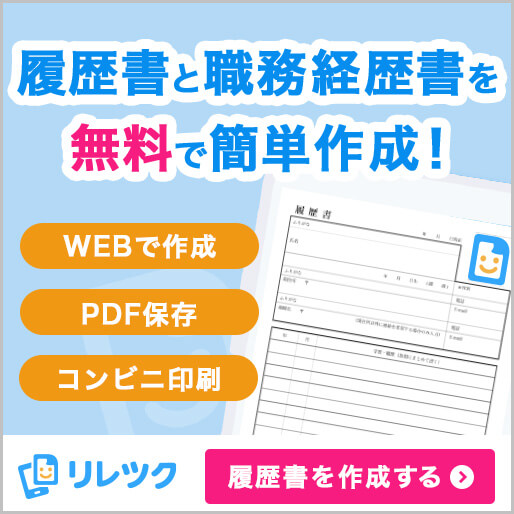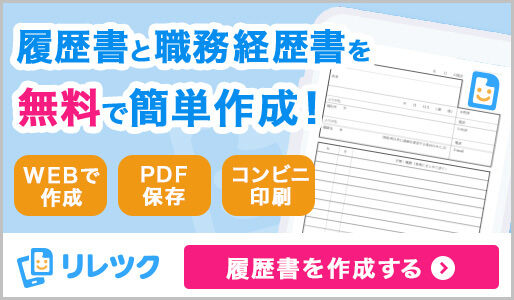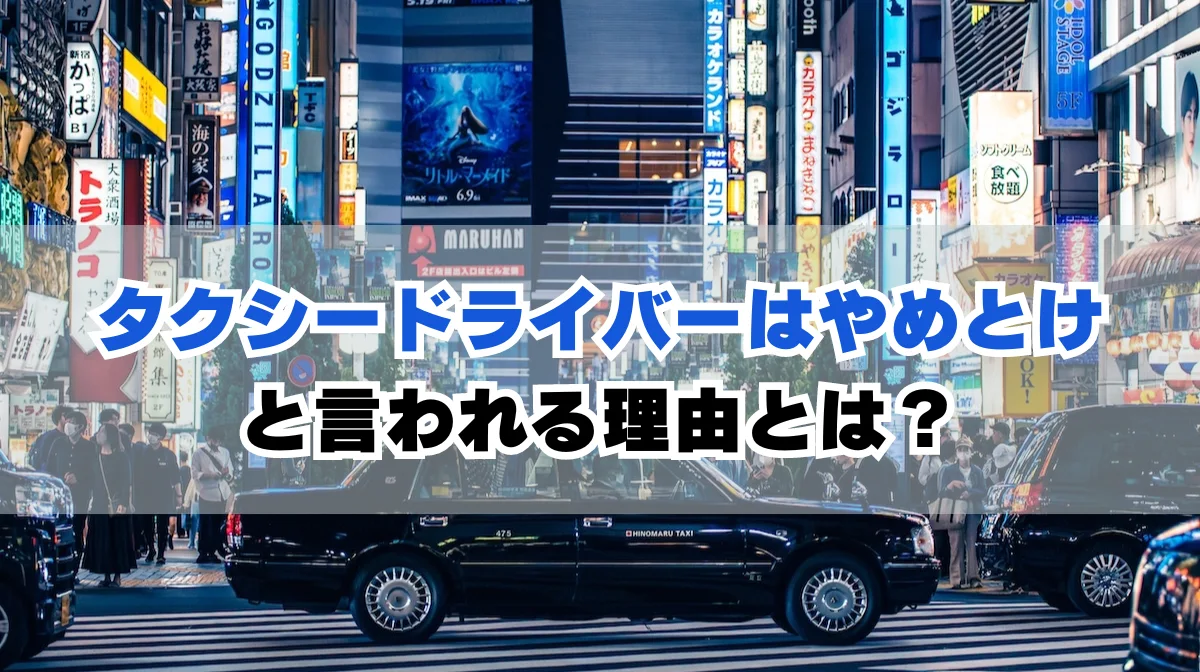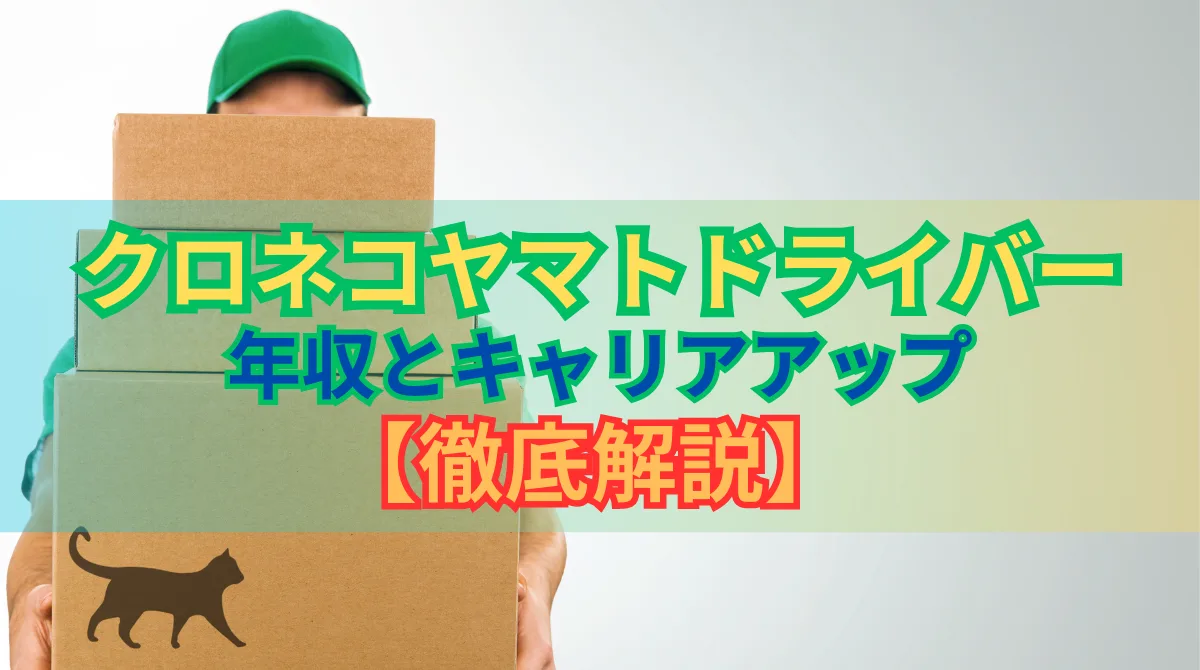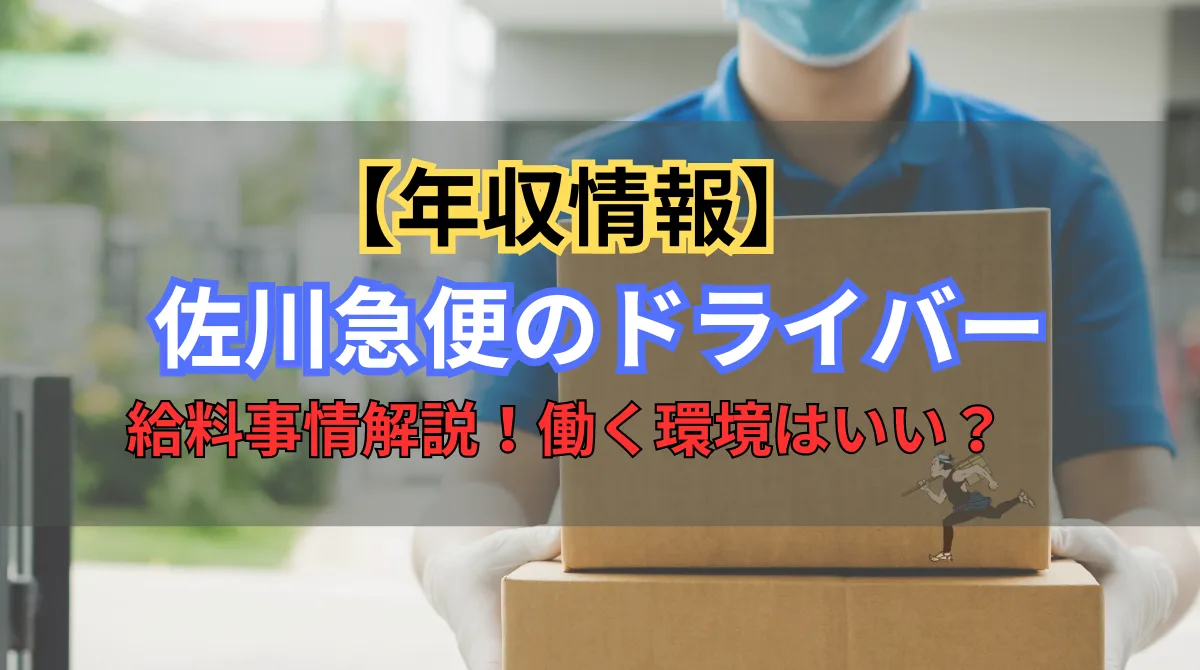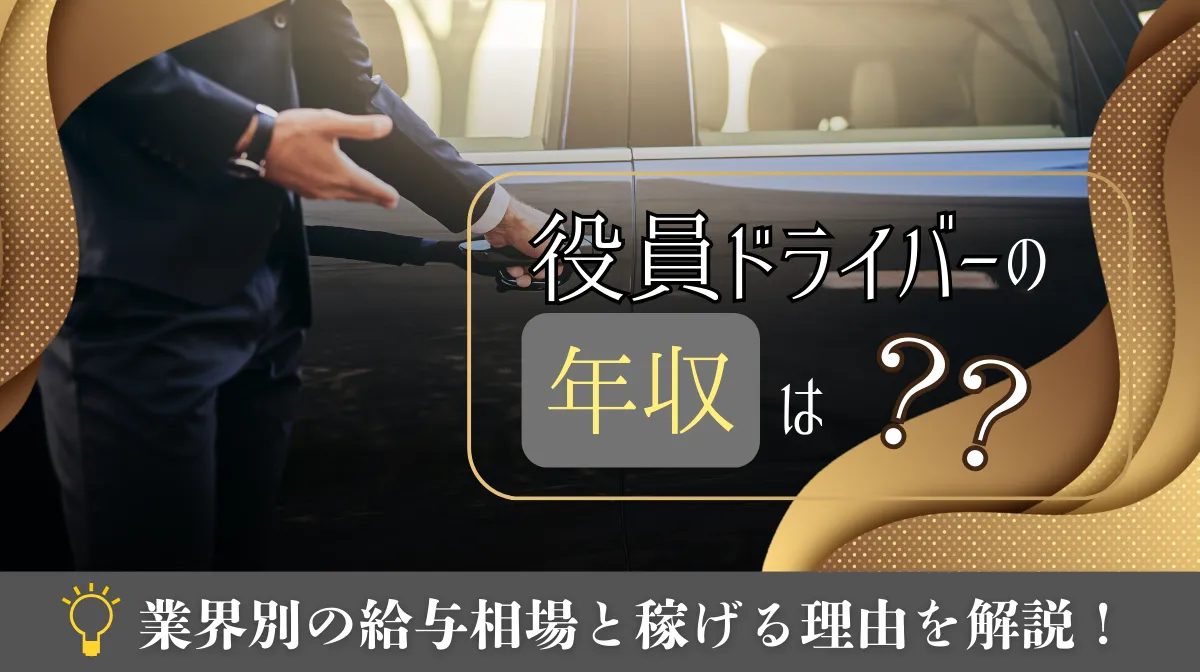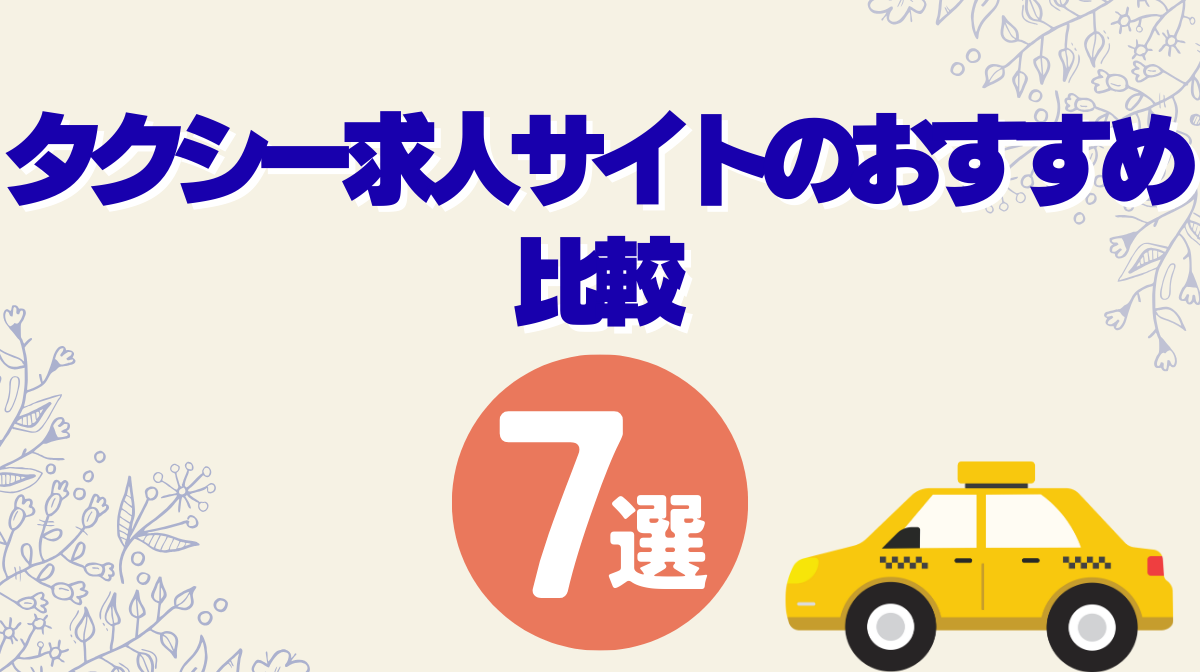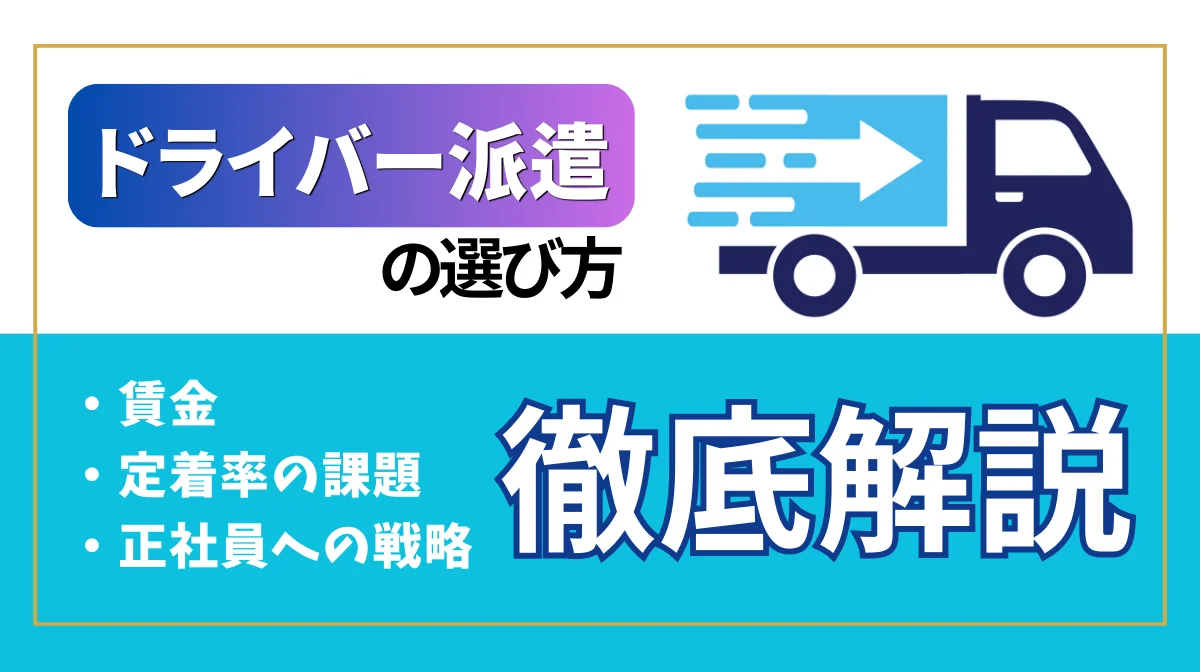自動車整備士の仕事に対し、「きつい」「やめとけ」といった厳しい意見を目にすることがあります。
専門的な技術職でありながら、なぜこのように言われるのでしょうか。一方で、自動車業界はEV化や自動運転など、100年に一度の変革期を迎えています。
この記事では、自動車整備士が「きつい」と言われる理由を、給与や労働環境の公的データから客観的に分析し、深刻な人手不足を背景に、待遇改善の転職や経験が活きる異業種へのキャリア戦略を具体的に解説します。
- 自動車整備士が「きつい」と言われる待遇・肉体・精神面の具体的な理由
- 公的データに基づいた整備士の平均年収や労働環境の実態
- 現状を改善するための「同業種への転職」や「異業種へのキャリアチェンジ」といった具体的な選択肢
1.自動車整備士が「きつい」と感じる5大分類の構造的要因
自動車整備士の仕事が「きつい」と感じられる背景には、主に「肉体」「環境」「精神」「待遇」「スキル」という5つの側面が存在します。
まずは、自身の感じている辛さがどのタイプに当てはまるか、客観的に分類してみましょう。
【肉体・環境面】「3K」と呼ばれる作業環境と体力負担
自動車整備は、基本的に立ち仕事であり、重いタイヤや部品の持ち運び、エンジンルームなどの狭い場所での不自然な体勢での作業が求められるため、体力的な負担が非常に大きい仕事です。
汚れと危険
エンジンオイルやグリスなどで作業着が汚れることは日常茶飯事であり、工具の使用やジャッキアップ作業は常に怪我のリスクを伴います。
高温多湿・低温環境
夏は工場内の熱気、冬は寒風が吹き込む環境での作業は、肉体的な「きつさ」に拍車をかけます。
【精神・心理面】ミスが許されないプレッシャーと納期ストレス
自動車整備士の仕事は、人の命を預かる仕事です。ブレーキやエンジンなど、重要保安部品の整備ミスは、重大な事故に直結します。
- 「絶対ミス不可」の緊張感
この「絶対にミスが許されない」というプレッシャーは、常に精神的な緊張を強いることになります。 - 納期に追われるストレス
特に車検や点検の繁忙期には、限られた時間で多くの車両を処理する必要があり、納期に追われるプレッシャーが精神的な負担となります。
【待遇・経済面】仕事量に見合わない給与水準と長時間労働
仕事の負担感や専門技術に対する責任の重さに対して、給与水準が見合わないという声は最も多く聞かれます。
- 労働時間の長さ
繁忙期には残業や休日出勤が続くこともあり、労働時間の長さが待遇への不満につながりやすい側面があります。 - 昇給の停滞
専門技術職であるにもかかわらず、経験年数を重ねても給与が上がりにくい給与テーブルの問題を抱える企業が少なくありません。
【スキル・成長面】最新技術への対応とキャリアパスの曖昧さ
自動車技術が急速に進化する中で、スキルアップや将来のキャリアに関する不安も「きつさ」の一因となっています。
- 技術変化への対応
EV(電気自動車)やADAS(先進安全技術)など、従来の機械整備知識だけでは対応できない新しい知識の習得が常に求められます。 - キャリアパスの閉塞感
現場での作業が中心となり、管理職や本部職への具体的なキャリアパスが見えにくいことから、将来に漠然とした不安を感じることがあります。
【人間関係面】古い体質の職場文化とコミュニケーションストレス
場や整備士という職種特有の、古い体質や人間関係がストレスとなるケースも多く見られます。
- 体育会系の文化
職人気質や年功序列の文化が根強く残り、上下関係が厳しい職場環境にストレスを感じることがあります。 - 顧客対応の難しさ
技術的な説明を分かりやすく顧客に伝えたり、クレームに対応したりする際のコミュニケーションのストレスも、精神的な負担となる場合があります。
▼あわせて読みたい
自動車整備士が「やめとけ」と言われる理由と、それでも成功できる戦略について、より詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
2.客観的データで見る自動車整備士のリアル

では、こうした「きつい」という感覚は、客観的なデータではどのように示されているのでしょうか。
平均年収は全産業平均と比べてどうなのか?
公的な統計データを見ると、自動車整備・修理従事者の年間給与(488万円)は、全産業平均を下回る傾向にあります 。
国家資格を持ち、高い専門技術と責任を要求される仕事でありながら、その価値が給与に十分に反映されていない現状が、データからも浮き彫りになっています。
▼あわせて読みたい
自動車整備士の年収について、業種別・年代別の詳細データと具体的な年収アップ方法を知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。
有効求人倍率5倍超が示す「深刻な人手不足」の現実
一方で、自動車整備士の有効求人倍率は非常に高い水準で推移しており、職種によっては5倍を超えることもあります。
これは、求職者1人に対して5件以上の求人があるという「深刻な人手不足」を示しています。この事実は、企業側が「きつい」労働環境の改善や待遇向上に本腰を入れなければ、人材を確保できない状況にあることを意味します。
働く側にとっては、職場を選び、より良い条件を交渉できる「強い材料」を持っているとも言えます。
■自動車整備士の派遣という選択肢もあります
カラフルスタッフィング メカニックは、車両整備士・メカニックに特化した人材派遣サービスです。専門のコーディネーターが希望に合ったお仕事をご提案し、有名ディーラーでスキルや経験を積めるチャンスもあります。派遣なら、複数の職場を経験しながら自分に合った環境を見つけることも可能です。
▼カラフルスタッフィング メカニックへのお問い合わせはこちら
3.「きつい」現状から抜け出すための3つの具体的な選択肢
(ディーラー等)へ転職する
異業種へキャリアチェンジする
年収向上を目指す
もし現状の職場で「きつい」と感じ、将来に不安を覚えるのであれば、その状況を客観的に分析し、次の一歩を踏み出すことが重要です。
具体的な選択肢は3つあります。
選択肢1:待遇の良い職場(ディーラー等)へ転職する
同じ自動車整備士であっても、職場によって待遇や労働環境は大きく異なります。
例えば、大手自動車メーカーの正規ディーラーは、給与水準が比較的高く、福利厚生や研修制度も充実している傾向があります。
また、特定の車種や技術に特化した専門工場なども、高い専門性を評価する給与体系を持っている場合があります。
人手不足の今だからこそ、自身の経験とスキルを適正に評価してくれる企業へ移ることは、現実的で有効な選択肢だと思われます。
▼あわせて読みたい
自動車整備士の転職を成功させるためのおすすめ転職サイトと、効果的な活用方法について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
■派遣で大手ディーラーの環境を体験してみませんか
いきなり正社員として転職するのが不安な方には、派遣という選択肢もあります。カラフルスタッフィング メカニックでは、有名ディーラーや優良企業での派遣求人を多数取り扱っています。まずは派遣で職場環境や待遇を確認してから、正社員登用を目指すことも可能です。
▼カラフルスタッフィング メカニックへのお問い合わせはこちら
選択肢2:整備士経験が活きる異業種へキャリアチェンジする
整備士として培った「車両の構造に関する知識」や「故障の原因を特定する論理的思考」は、他の業種でも高く評価されるポータブルスキルです。
例えば、以下のようなキャリアチェンジが考えられます。
- トラック・バスのドライバー
車両の日常点検や簡単なトラブルシューティングができる整備知識は、安全運行のプロとして大きな強みとなります。特に大型車両や特殊車両のドライバーは、整備知識が給与面で優遇されるケースもあります。 - 工場の設備保全(メンテナンス)
自動車以外の「機械」を扱う仕事です。機械の故障診断や定期メンテナンスは、整備士の業務と親和性が非常に高い分野です。 - テクニカルサポート・技術営業
整備の現場で培った知識を活かし、顧客や営業担当者に技術的なアドバイスを行う仕事です。体力的な負担は大幅に軽減されます。
▼あわせて読みたい
自動車整備士から異業種への転職を本格的に検討している方には、具体的な転職先と成功のポイントを詳しく解説した記事がおすすめです。
選択肢3:公的制度でスキルアップし、年収向上を目指す
「きつい」と感じる理由が、現在のスキルや資格では評価されにくいことにある場合、公的な制度を活用して市場価値を高める道もあります。
例えば、厚生労働省が実施する「教育訓練給付制度」は、働く人のスキルアップやキャリア形成を支援する制度で、指定の講座を受講すると費用の一部が給付されます。
こうした制度を利用して、電気自動車(EV)や先進安全技術(ADAS)に関する最新の整備技術、あるいはマネジメント職に必要な「運行管理者」 などの資格を取得し、キャリアアップと年収向上を目指すことも可能です。
4.自動車整備士の「やりがい」と「将来性」

ここまで「きつい」側面に焦点を当ててきましたが、自動車整備士の仕事には、それを上回るやりがいも確かに存在します。
きつさだけではない仕事のやりがい
故障の原因を突き止め、自分の技術で完全に修理できた時の達成感や、お客様から「ありがとう、助かったよ」と直接感謝される瞬間は、何物にも代えがたいやりがいです。
自分の仕事が、人々の安全な移動という社会インフラを支えているという誇りも、この仕事の大きな魅力です。
EV・先進技術の普及と整備士の将来性
EV化や自動運転技術の進展により、「整備士の仕事はなくなる」と不安視する声もありますが、実際はその逆だと思います。
ガソリン車とは全く異なる構造を持つEVや、複雑な電子制御システムを診断・整備するためには、従来の機械知識に加え、電気・電子・ITに関する高度な知識が不可欠となります。
これからの整備士は、古い技術者が淘汰される一方で、新しい技術に対応できる専門家としての価値が飛躍的に高まっていきます。
▼あわせて読みたい
自動車整備士不足の深刻な現状と、それが業界にもたらす影響について、最新データとともに詳しく解説している記事もぜひご覧ください。
5.厳しさの中にチャンスがある 整備士が主導権を握るキャリア戦略
自動車整備士の仕事が「きつい」と言われる背景には、給与水準や労働環境といった客観的な事実が存在します。
しかし同時に、深刻な人手不足は、働く側が主体的にキャリアを選択できるチャンスでもあります。
現状の「きつさ」に甘んじるのではなく、自身のスキルと経験を棚卸しし、待遇の良い同業他社へ移るのか、知識を活かして異業種へ挑戦するのか、あるいは新技術を学んで専門性を高めるかが決め手となります。
自らの市場価値を客観的に分析し、主体的に行動を起こすことで、自らが望む環境を見つけることができると思います。
■整備士専門の派遣サービスで新しいキャリアを始めよう
カラフルスタッフィング メカニックは、車両整備士・メカニック専門の人材派遣サービスです。業界を熟知した専門コーディネーターが、あなたのスキルや希望に合った最適な職場をご紹介します。派遣なら、柔軟な働き方で待遇改善を実現しながら、キャリアアップも目指せます。まずはお気軽にご相談ください。
▼カラフルスタッフィング メカニックへのお問い合わせはこちら