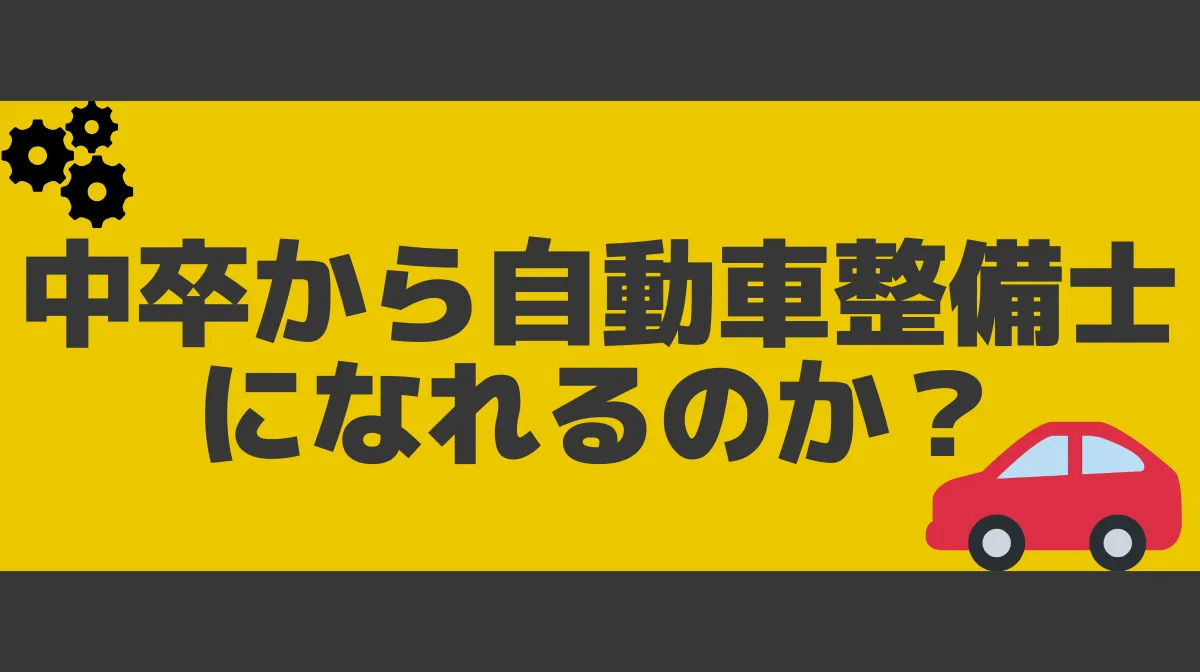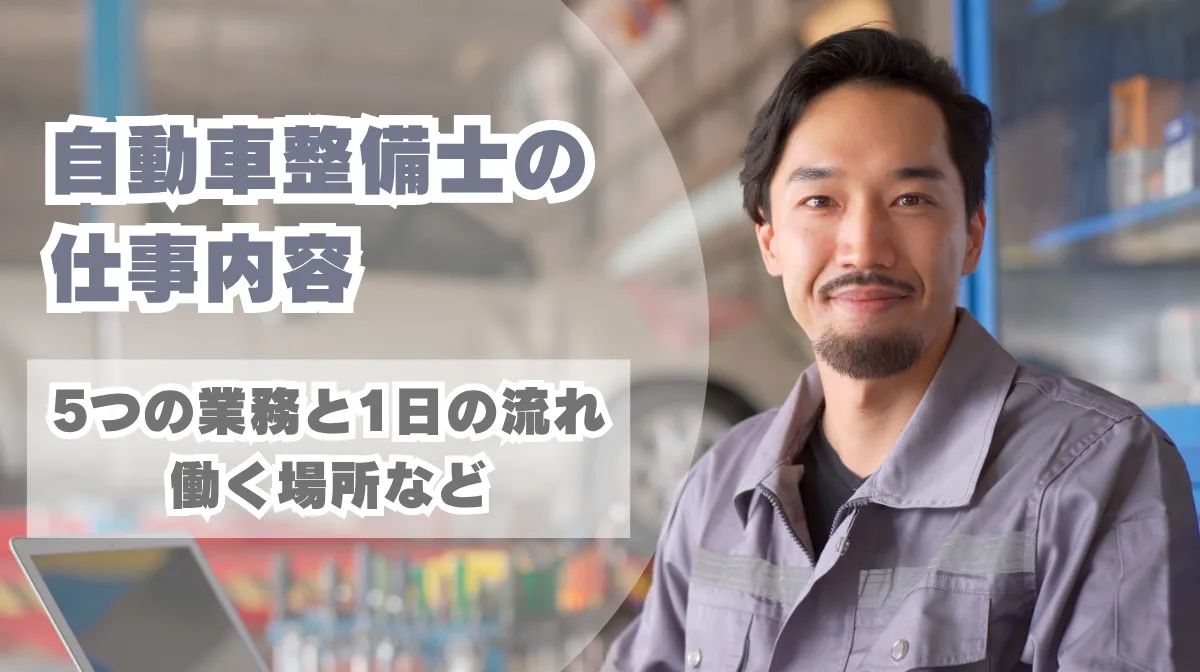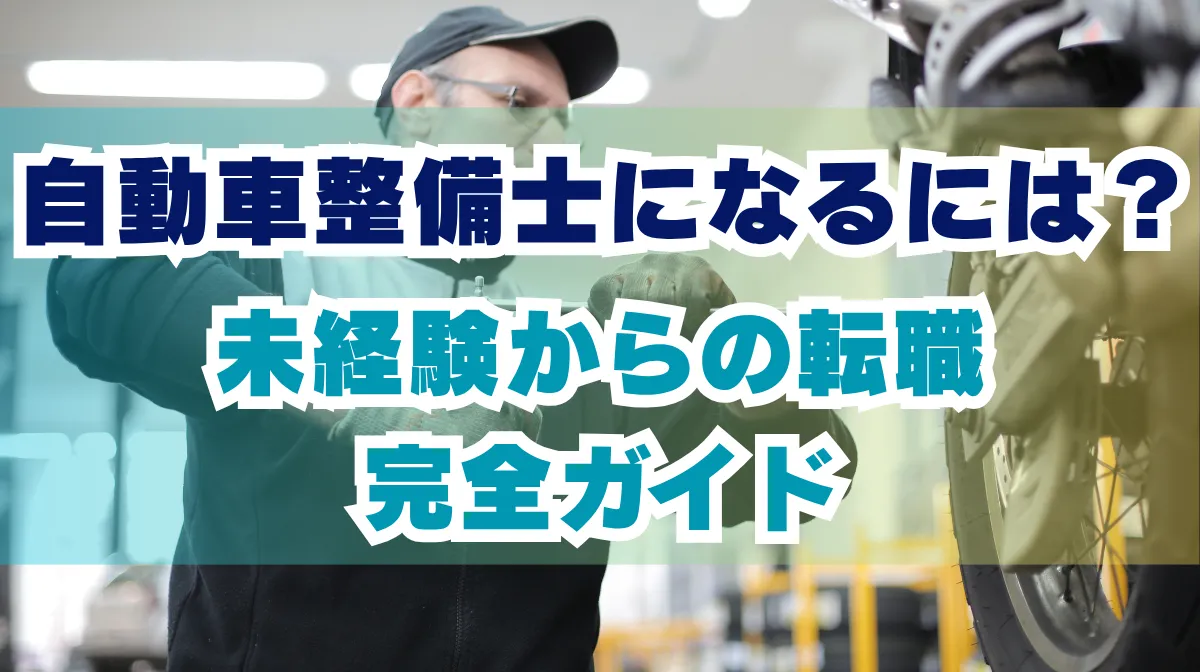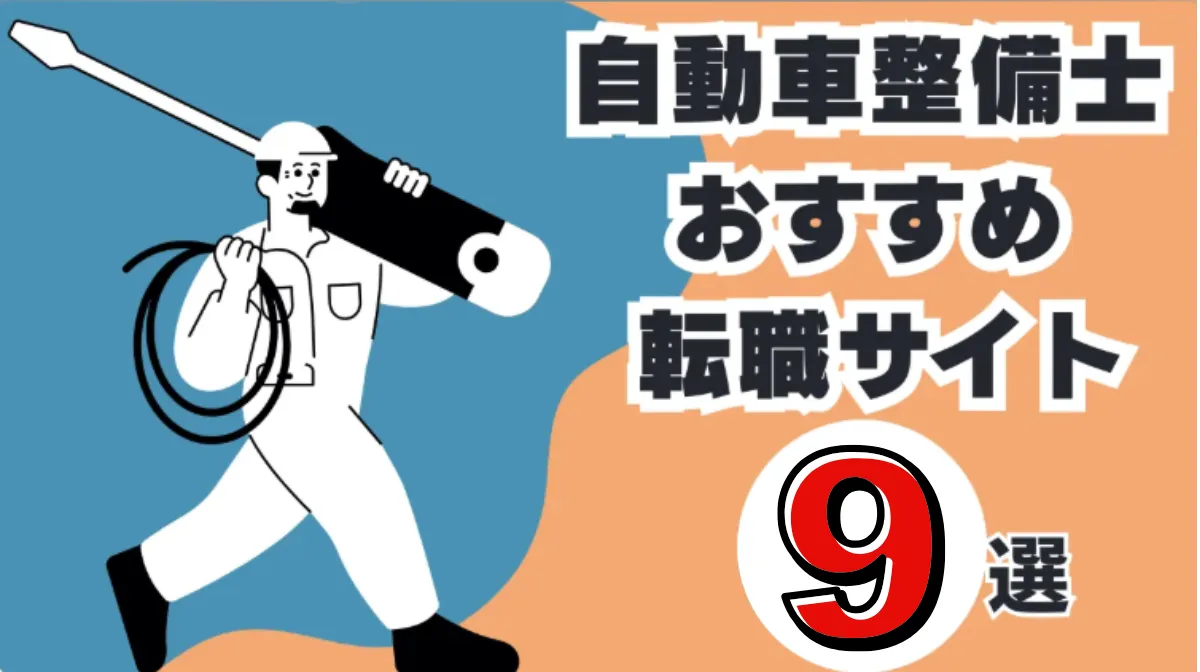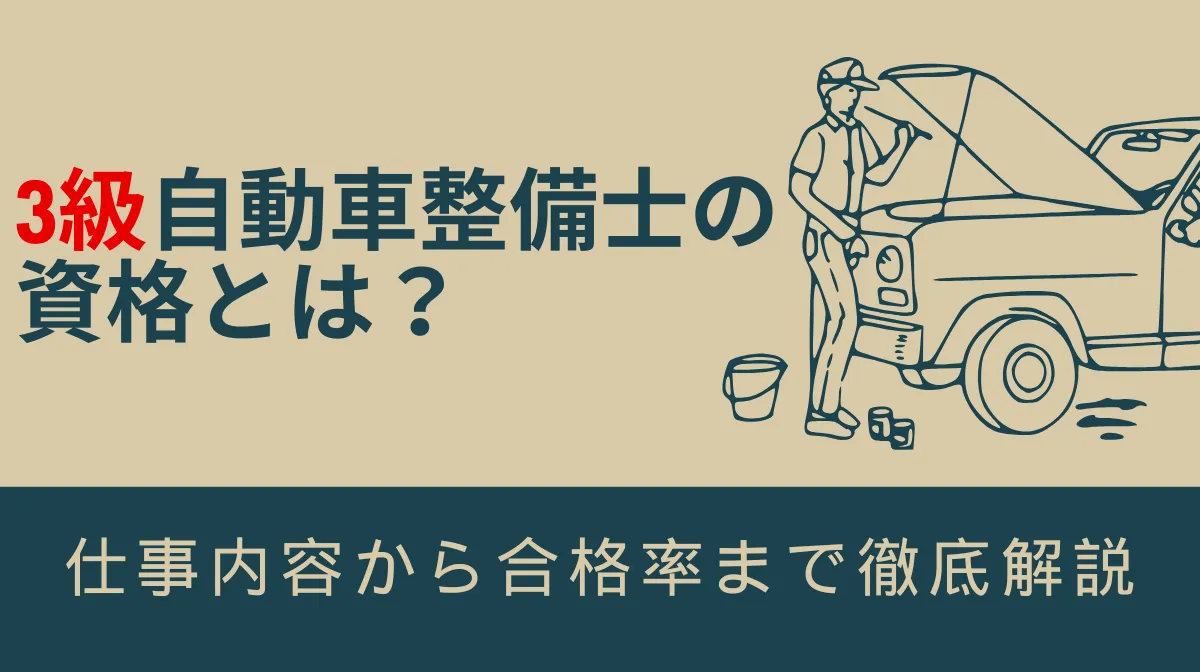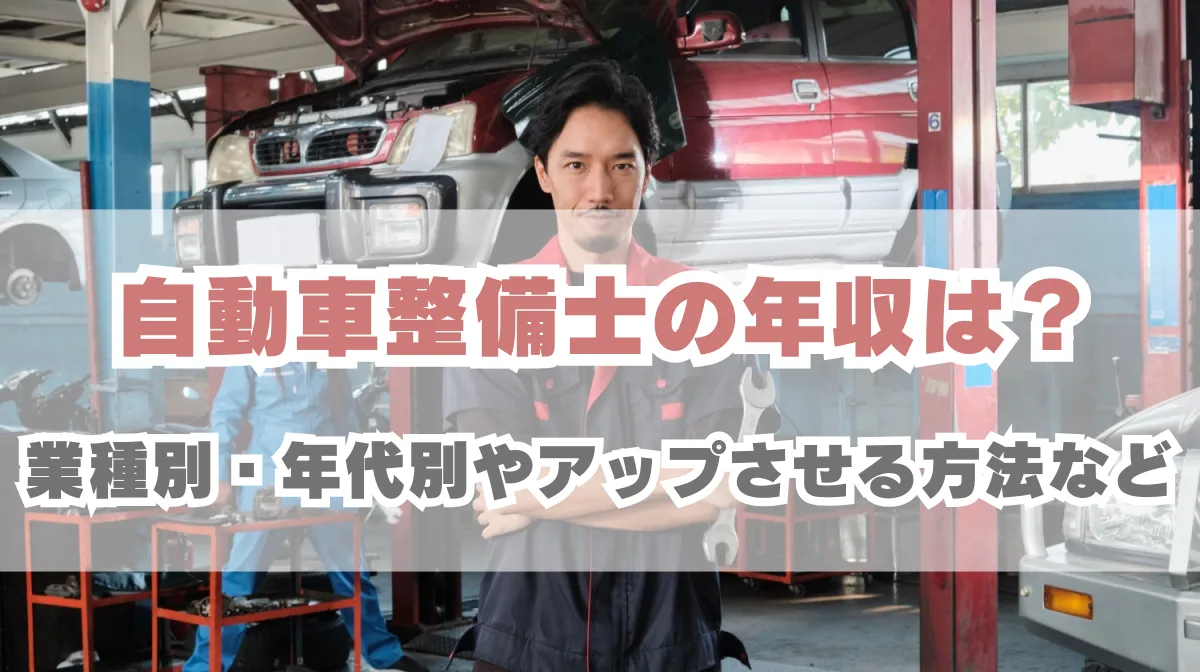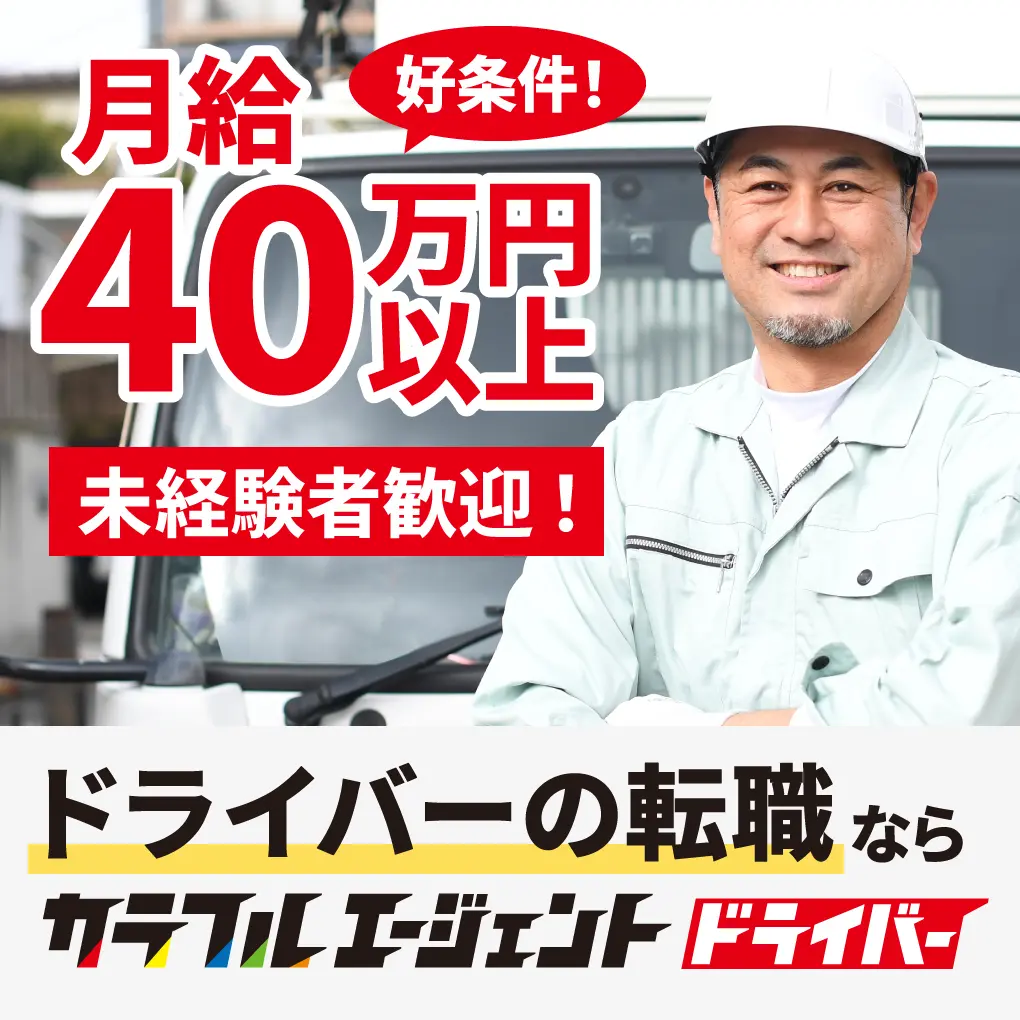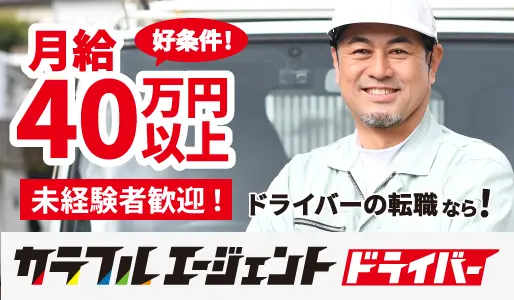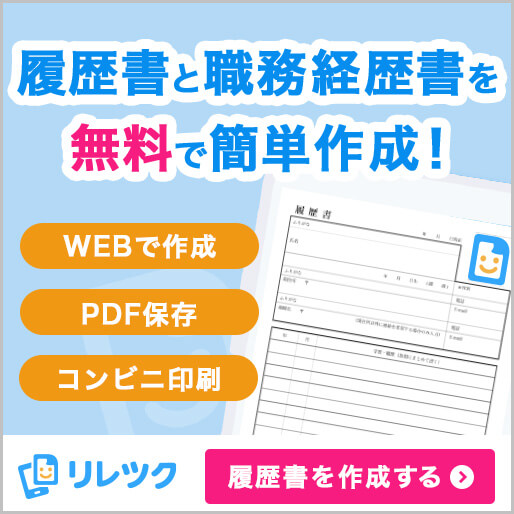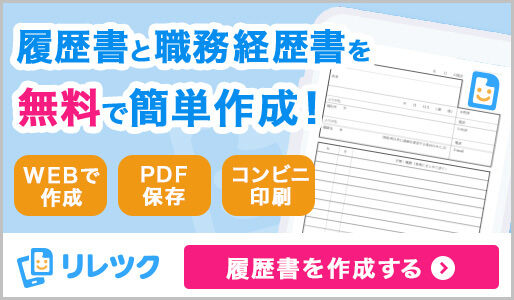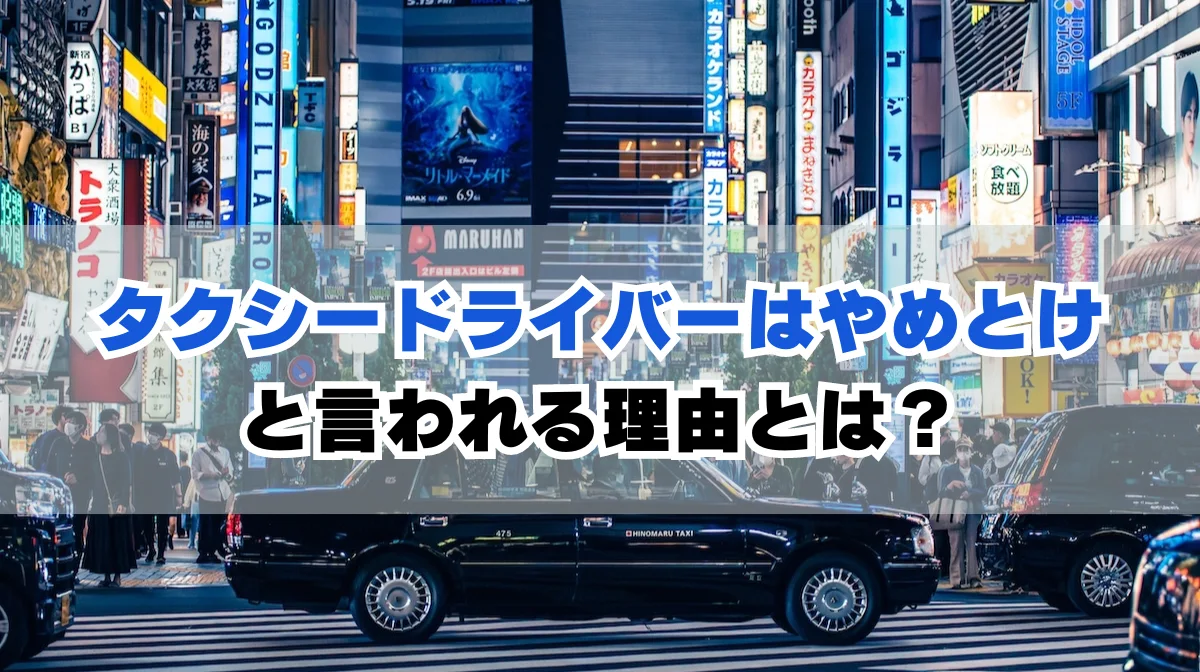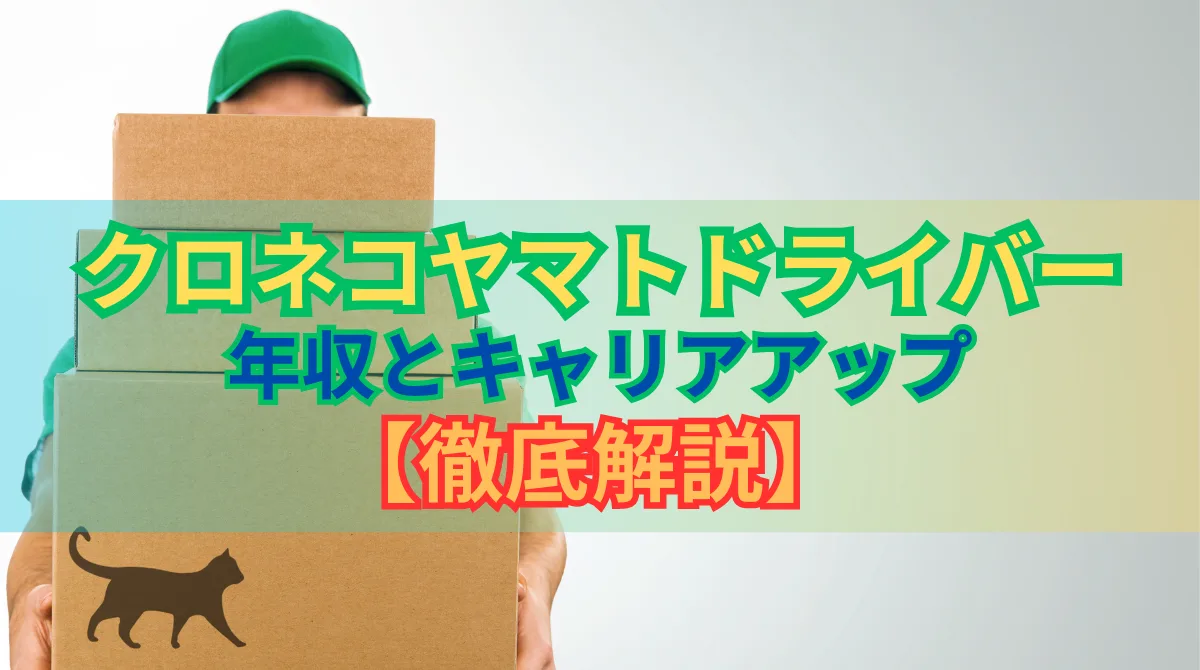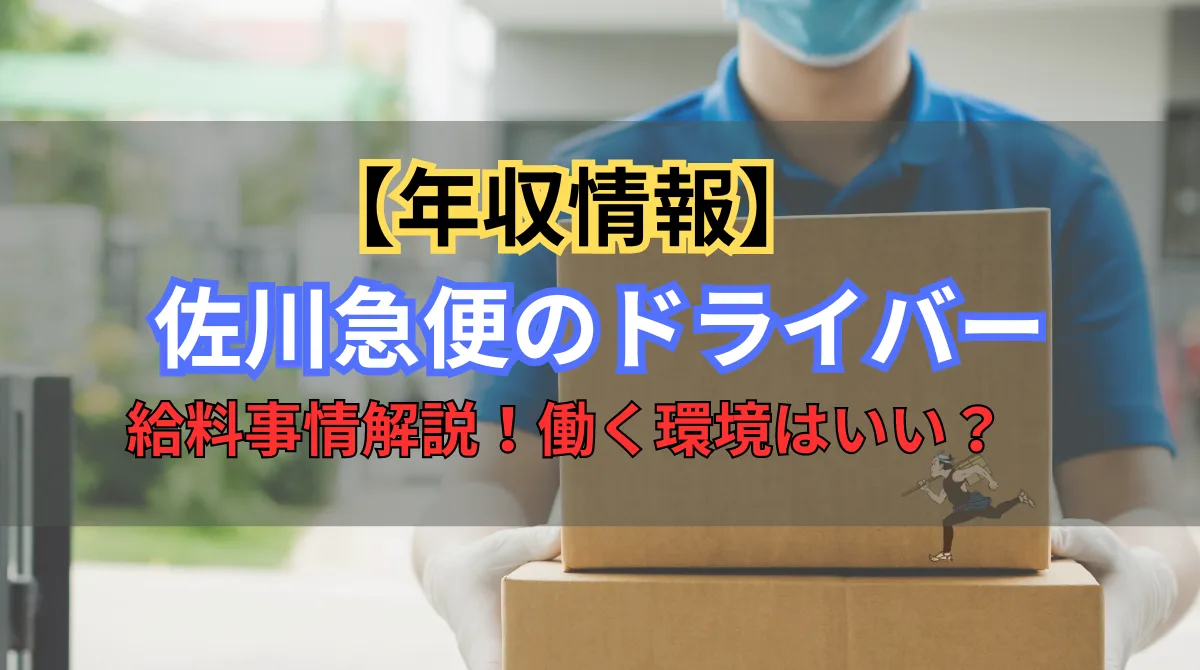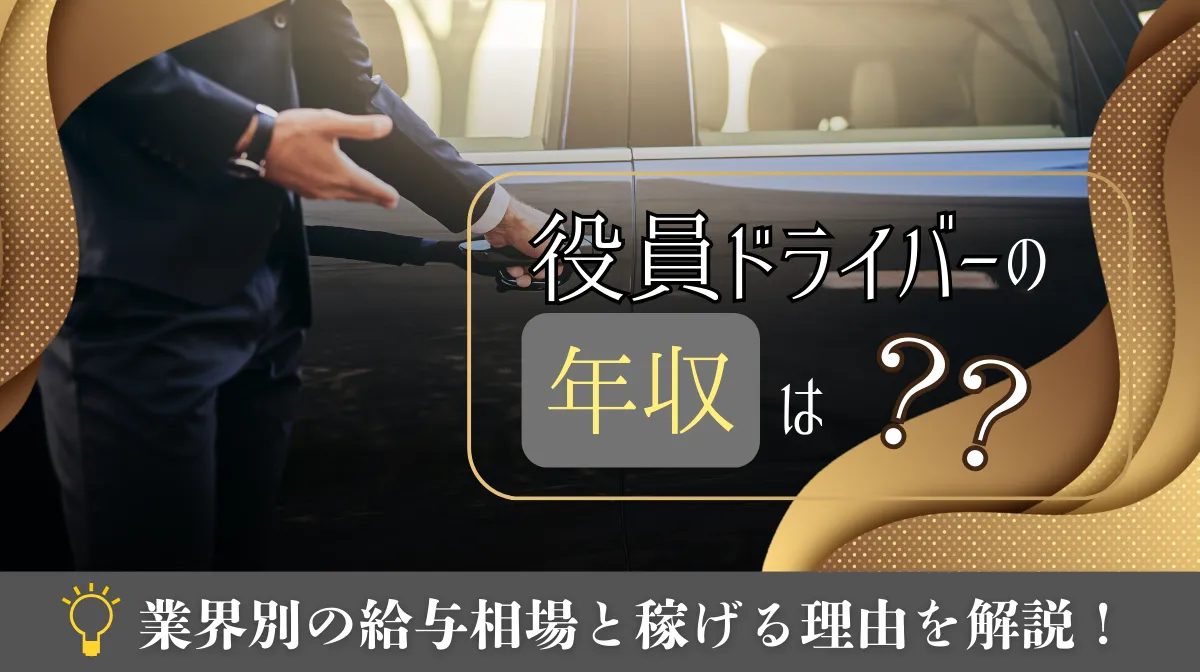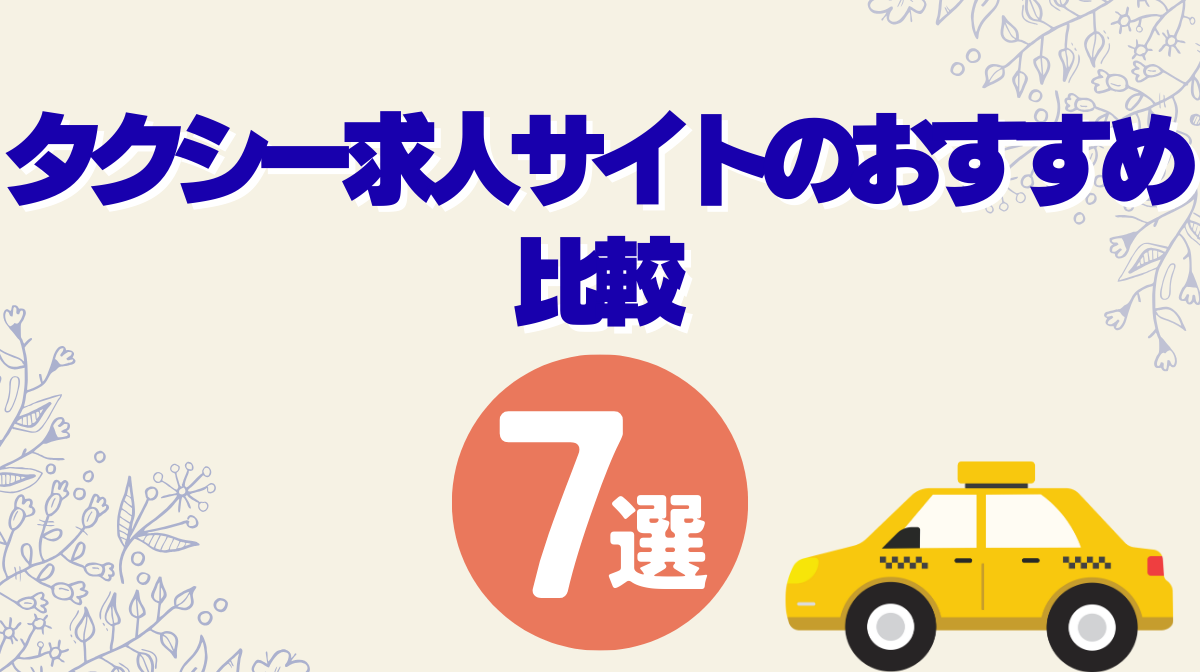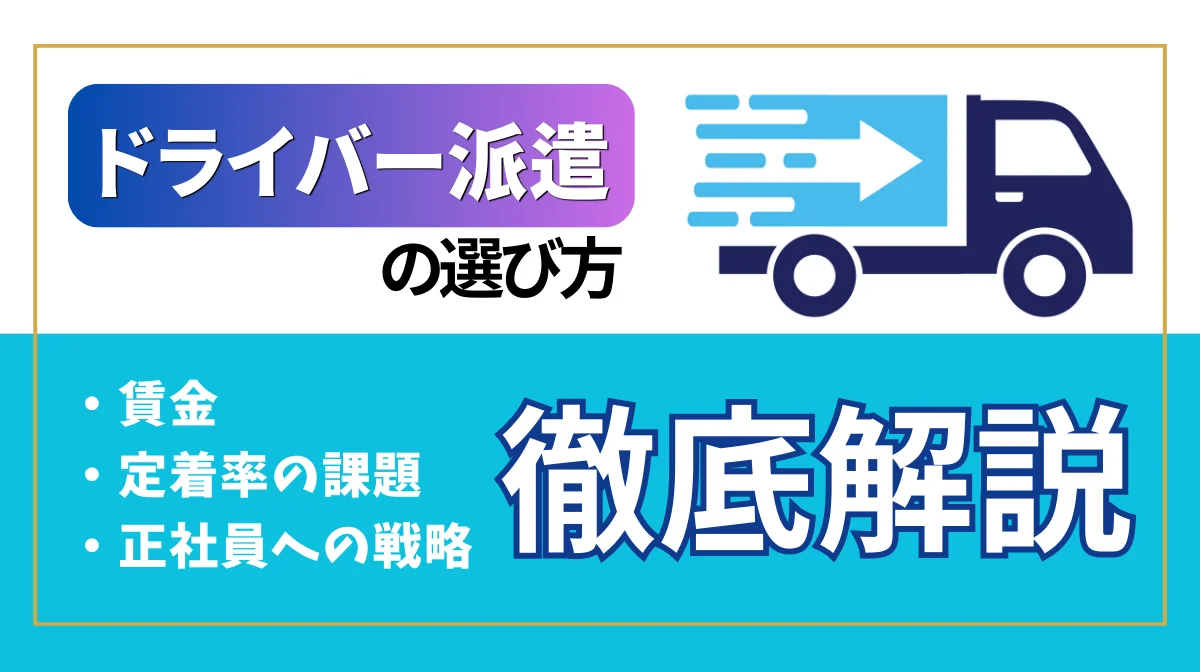中卒という学歴がキャリアの壁になるのではないかと不安を感じるかもしれません。
自動車整備士は、学歴よりも国家資格と実務経験が重視されます。
この記事では、中卒から自動車整備士になるための具体的な2つのルートと、学歴不問で活躍できる理由を解説します。
- 自動車整備士が中卒でも「なれる」明確な理由と、学歴不問求人の背景
- 国家資格(3級)取得のための2つの正規ルート(実務経験 vs 進学)
- 無資格・未経験で就職した場合の仕事内容と、資格取得までの流れ
- 整備士になった後のキャリアパスと将来性
1.【結論】中卒からでも自動車整備士になれます!学歴不問の理由とは

中卒でも自動車整備士を目指せるかという疑問に対し、結論から言えば、それは十分可能です。整備士のキャリアは最終学歴ではなく、国家資格の有無で決まります。
人材不足の業界では、学歴を問わず、意欲ある未経験者を積極的に採用・育成する動きが強まっています 。
自動車整備士と学歴:重視されるのは「国家資格」
自動車整備士として働くために最も重要なのは、最終学歴ではなく「自動車整備士技能登録試験」という国家資格です。
この資格は、国土交通省が管轄しており、受験資格に学歴は含まれていません。
もちろん、高校や専門学校の自動車整備科を卒業すると、実務経験が免除されたり、試験の一部が免除されたりするメリットはあります。
しかし、それはあくまで「資格取得までのルートが異なる」だけであり、中卒だからといって資格が取れない、整備士になれないということは一切ありません。
▼あわせて読みたい
自動車整備士の具体的な業務内容や1日の流れについて詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。
なぜ「学歴不問」の求人が多い?業界の深刻な人材不足が背景に
自動車整備士は、現代の車社会を支える不可欠な専門職ですが、慢性的な人材不足という課題を抱えています。
特に若い世代の担い手が不足しており、多くの整備工場やディーラーが、学歴や経験を問わず、意欲のある人材を積極的に採用・育成しようとしています。
このため、求人情報を見ると「学歴不問」「未経験者歓迎」といった募集が非常に多く見つかります。
企業側には、入社後に実務を経験させながら資格取得をサポートし、一人前の整備士に育て上げたいという明確なニーズがあるのです。
2.中卒から整備士資格(3級)を取得する2つの正規ルート
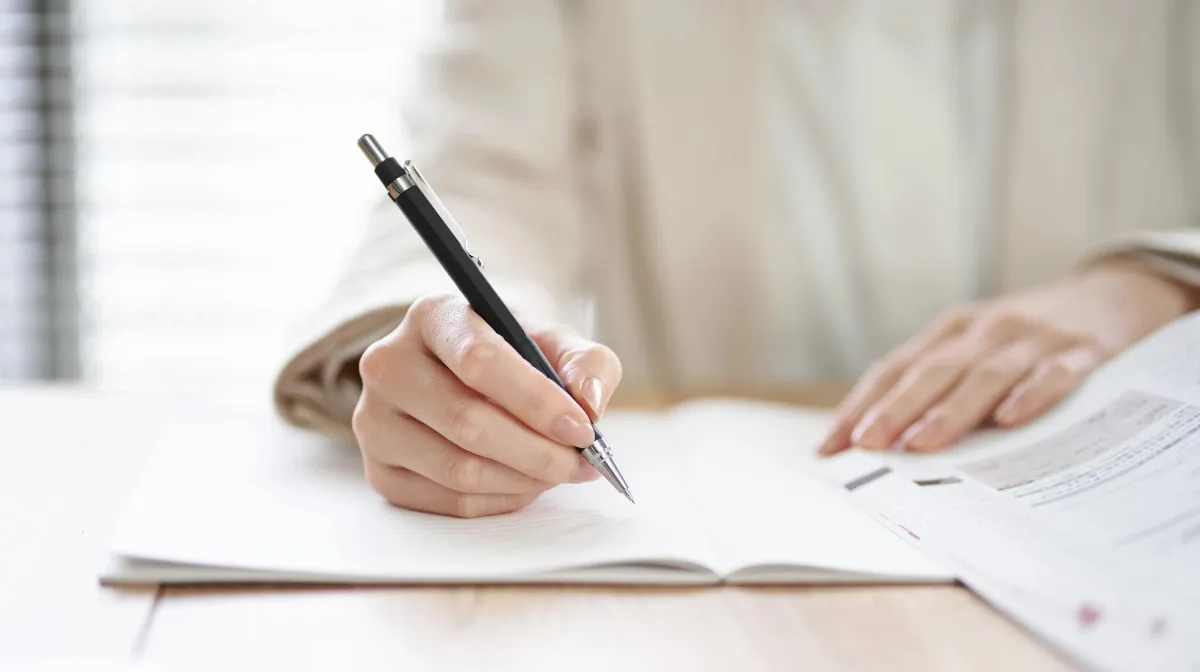
自動車整備士の国家資格には1級から3級までありますが、まず目指すべきは「3級自動車整備士」です。
この3級資格の受験資格を得るには、大きく分けて2つのルートが存在します。
ルート1:就職先行型(働きながら実務経験を積む)
まず「認証工場」と呼ばれる整備工場やディーラーに整備補助(見習い)として就職し、現場で働きながら資格取得を目指す方法です。
中卒の場合、国が定める1年以上の実務経験を積むことで、三級自動車整備士の受験資格が得られます。最大のメリットは、働きながら給与を得られる点と、OJTで生きた技術を学べる点です。
企業が資格取得費用や研修をサポートしてくれるケースも多く、経済的な負担を抑えたい方にとって現実的なルートです。
▼あわせて読みたい
未経験から自動車整備士への転職を考えている方向けに、具体的なステップや必要な準備について以下の記事で詳しく解説しています。
■派遣という働き方で整備士のキャリアをスタート
カラフルスタッフィング メカニックは、車両整備士・メカニックに特化した人材派遣サービスです。専門のコーディネーターが希望に合ったお仕事をご提案。有名ディーラーでスキルや経験を積めるチャンスもあります。資格取得支援制度がある派遣先も多数ご紹介可能です。
▼カラフルスタッフィング メカニックへのお問い合わせはこちら
ルート2:進学先行型(学校で学んでから就職する)
国土交通大臣が定める自動車整備士養成施設(専門学校や職業訓練校など)に入学し、必要な知識と技術を体系的に学ぶルートです。
中卒者でも入学が可能です。このルートの最大の強みは、2年間の課程を修了することで、三級だけでなく二級整備士の受験資格を最短で得られる点、さらに実技試験が免除される点です。
短期集中で高度な知識を習得し、将来的に高待遇なディーラーへの就職を目指すなら、このルートが有利になります。
3.【ルート1】未経験・中卒で就職し「実務経験1年」で3級を目指す方法

最も現実的で、経済的な負担も少なく始められるのが、この「就職先行型」ルートです。
最重要:実務経験は国が認めた「認証工場」か「指定工場」で
3級の受験資格として認められる実務経験は、どの工場で働いてもよいわけではありません。国土交通省から認可を受けた「認証工場」または「指定工場(民間車検場)」での経験が必須です。
就職先を探す際は、その工場が「認証工場」または「指定工場」であるかを必ず確認してください。
どんな仕事から始める?無資格でできる業務内容
無資格・未経験の場合、入社後すぐに分解整備(ブレーキなど重要部品の整備)に携わることは法律で禁じられています。
まずは、整備士のアシスタント(補助作業)として、以下のような業務からスタートするのが一般的です。
- 洗車や車内の清掃
- 工具の準備や片付け、工場の清掃
- タイヤ交換やオイル交換の補助
- 点検整備の補助
こうした補助業務を通じて、車の構造や工具の使い方、作業の流れを現場で学んでいきます。
賢い職場の選び方:「資格取得支援制度」の有無を確認
働きながら資格を目指す上で、職場のサポート体制は非常に重要です。求人を探す際は、「資格取得支援制度あり」の企業を積極的に選びましょう。
- 受験費用や講習費用の会社負担
- 勤務時間内での勉強時間の確保
- 先輩整備士による技術指導
こうした支援がある職場は、中卒・未経験者の育成に積極的であり、キャリア形成に役立ちます。
▼あわせて読みたい
効率的に求人を探したい方は、自動車整備士に特化した転職サイトの活用がおすすめです。以下の記事で最新のおすすめサイトを紹介しています。
4.【ルート2】中卒で入学できる学校(高等課程・通信制)で学ぶ方法

「まずはしっかり学んでから働きたい」という場合は、進学も有効な選択肢です。
専門学校の「高等課程」とは?
専門学校の「高等課程」とは、中学校卒業者(または高校中退者)を対象として、専門知識・技術の習得と同時に、高校卒業資格の取得を目指せる課程です。
整備士の養成コースを設けている高等課程では、座学で整備の基礎理論を学びながら、実習で工具の扱いや車の構造を実践的に習得できます。
これにより、18歳で現場に出る頃には、高卒資格と三級整備士の受験資格(または二級受験資格)を得ており、同年代より一歩リードした状態でキャリアをスタートできます。
通信制高校+専門学校(Wスクール)という選択肢
より柔軟な学び方を希望する場合、「通信制高校に在籍し、高校卒業資格を取得しつつ、提携する専門学校の自動車整備コースに通う」Wスクール(ダブルスクール)という方法もあります。
この選択肢は、自分のペースで高校の勉強を進められるため、集中して整備技術の習得に時間を割きたい方や、自宅から通いやすい学校を選びたい方に適しています。
どちらの学校も卒業できれば、整備士の受験資格と高卒資格の両方を無理なく手に入れることが可能です。
メリットとデメリットの比較(学費・期間)
進学ルートのメリットは、整備の基礎を体系的に学べること、そして卒業時に受験資格(または資格そのもの)を得られる点です。
一方、デメリットとしては、当然ながら学費がかかること、そして最低でも2〜3年の期間が必要になる点が挙げられます。
ご自身の経済状況や、どれだけ早く現場に出たいかを考慮して選択することが大切です。
■学校卒業後は派遣で多様な職場を経験
カラフルスタッフィング メカニックなら、専門学校や高等課程を卒業した後、派遣という働き方で複数のディーラーや整備工場を経験できます。専門のコーディネーターがあなたの希望やスキルレベルに合った職場をご提案。派遣だからこそ、自分に合った職場環境を見つけやすくなります。
▼カラフルスタッフィング メカニックへのお問い合わせはこちら
5.自動車整備士のキャリアパスと将来性

3級整備士の資格は、技術者としてのスタートラインです。ここからさらにステップアップすることで、収入や責任の大きな仕事に就くことが可能になります。
最終学歴に関係なく、スキルと資格が将来性を左右する道筋を見ていきましょう。
3級取得後のステップアップ(2級・1級・検査員)
3級は整備士としてのスタートラインです。多くの整備士は、さらに上位の資格を目指します。
- 2級整備士
整備全般(分解整備を含む)を行える、整備士の「中核」となる資格です。3級取得後に実務経験を積むことで受験資格が得られます。 - 1級整備士
最高難易度の資格で、高度な電子制御システムや環境技術に対応できる指導者レベルの資格です。 - 自動車検査員
指定工場(民間車検場)で、車検の最終的な合否判定(検査)を行うための重要な資格です。
このように、資格を取得していくことで、仕事の幅と責任が明確に広がっていきます。
▼あわせて読みたい
3級自動車整備士の資格について、仕事内容から合格率まで詳しく知りたい方は以下の記事で徹底解説しています。
給与は上がる?学歴より技術と資格が収入に影響
自動車整備士の給与は、学歴よりも「保有資格」と「技術力(経験)」によって決まる傾向が強いです。
中卒で入社しても、実務経験を積み、2級、1級、検査員と着実にステップアップすることで、高卒や大卒の整備士と同様、あるいはそれ以上に収入を増やしていくことが可能です。
▼あわせて読みたい
自動車整備士の年収について業種別・年代別に詳しく知りたい方、また年収をアップさせる具体的な方法については以下の記事で解説しています。
AI・自動運転が普及しても整備士の仕事はなくならない理由
「将来、自動運転が普及したら仕事がなくなるのでは?」と心配されるかもしれませんが、その可能性は低いと考えられています。
車がどれほど電子制御化されても、タイヤの摩耗、ブレーキパッドの消耗、オイル漏れなど、物理的な点検・整備が必要なくなることはありません。
むしろ、今後は「高度な電子システムを診断できる整備士」の需要がさらに高まると予想されており、学び続ける意欲があれば将来性が見込まれる職種です。
6.中卒から自動車整備士を目指す際のよくある疑問(FAQ)
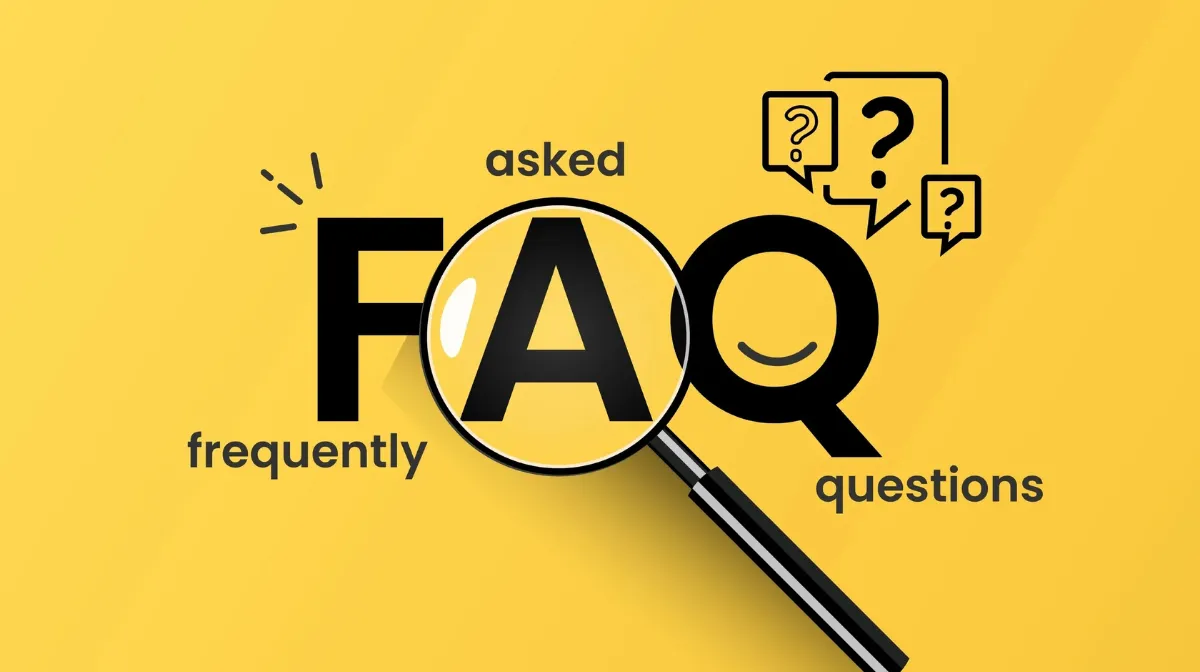

数学や物理が苦手でも大丈夫ですか?

整備には、簡単な計算(四則演算)や、電気の基礎(オームの法則など)といった知識が必要になる場面があります。しかし、入社時点ですべてを理解している必要はありません。
多くは、実務や資格勉強を通じて「現場で必要なこと」から学んでいけます。苦手意識があっても、学ぶ意欲があれば問題ありません。

大手ディーラーへの就職は難しいですか?

新卒採用の場合、大手ディーラーは専門学校卒以上を応募条件にしていることが多いのは事実です。
しかし、中途採用や、人材不足の状況下では、中卒であっても「3級以上の有資格者」であれば応募できるケースは増えています。
まずは「就職先行型」で地域の認証工場や指定工場で実務経験と3級資格を取得し、その後にディーラーへ転職するというキャリアプランも有効です。

働きながらの勉強は実際どのくらい大変ですか?

正直にお答えすると、日中働き、帰宅後に勉強する生活は決して楽ではありません。しかし、整備士の資格試験は、実務で経験していることがそのまま出題される部分も多いのが特徴です。
「現場でわからなかったことを、教科書で確認する」というサイクルを作れれば、効率的に学習を進めることができます。職場の先輩のサポートも得ながら、乗り越えていけば良いと思います。
■派遣で始める整備士キャリア|柔軟な働き方を実現
カラフルスタッフィング メカニックは、車両整備士・メカニックに特化した人材派遣サービスです。「まずは短期で働いてみたい」「いろいろな職場を経験したい」という方にも最適。専門のコーディネーターが、あなたの希望に合った有名ディーラーや整備工場をご提案します。
▼カラフルスタッフィング メカニックへのお問い合わせはこちら
7.学歴は関係ない!最初の一歩を踏み出すための行動プラン
自動車整備士への道は、中卒という学歴によって閉ざされるものではありません。
大切なのは「国家資格」と「実務経験」であり、それらを得るための正規ルート(就職先行型・進学先行型)が国によってしっかり定められています。
もし本気で自動車整備士を目指すなら、まずは最初の一歩として、「学歴不問」「未経験者歓迎」「資格取得支援制度あり」——この3つのキーワードで求人情報を検索することを推奨します。
意欲ある人材を待っている企業が、きっと見つかるはずです。