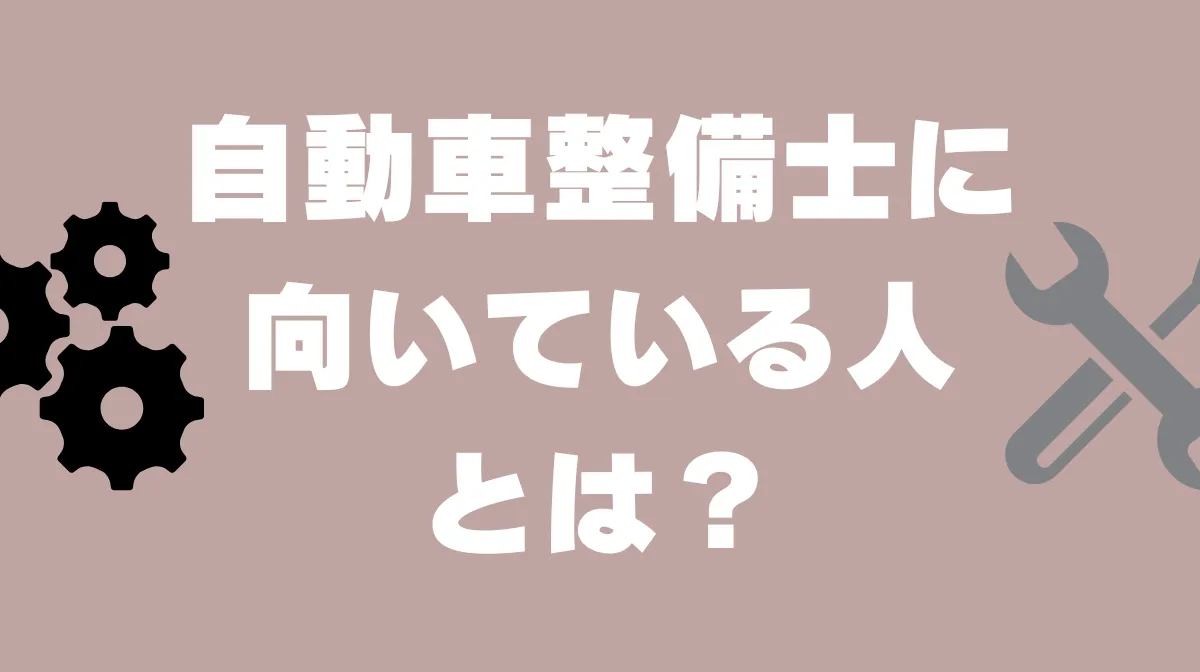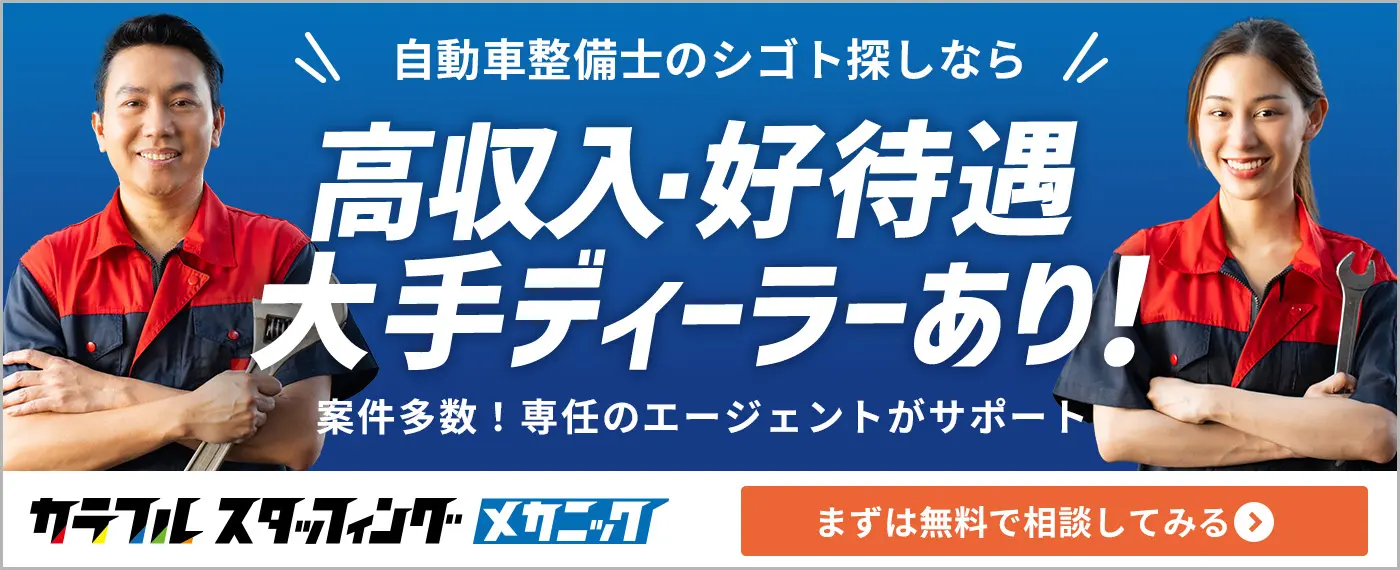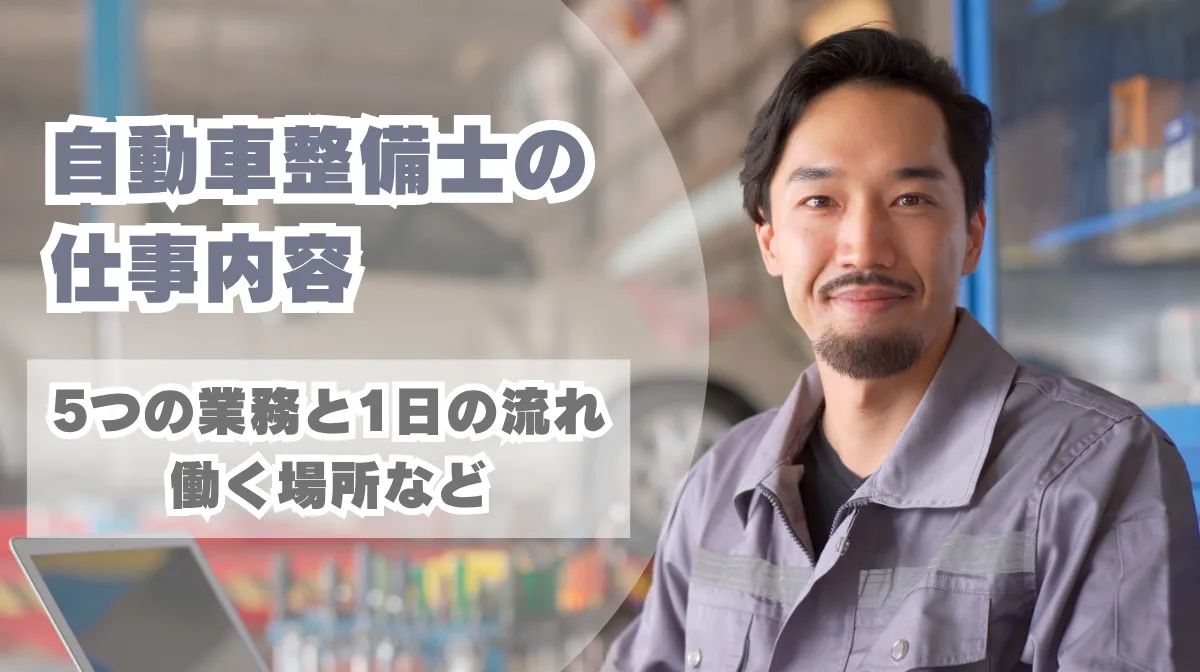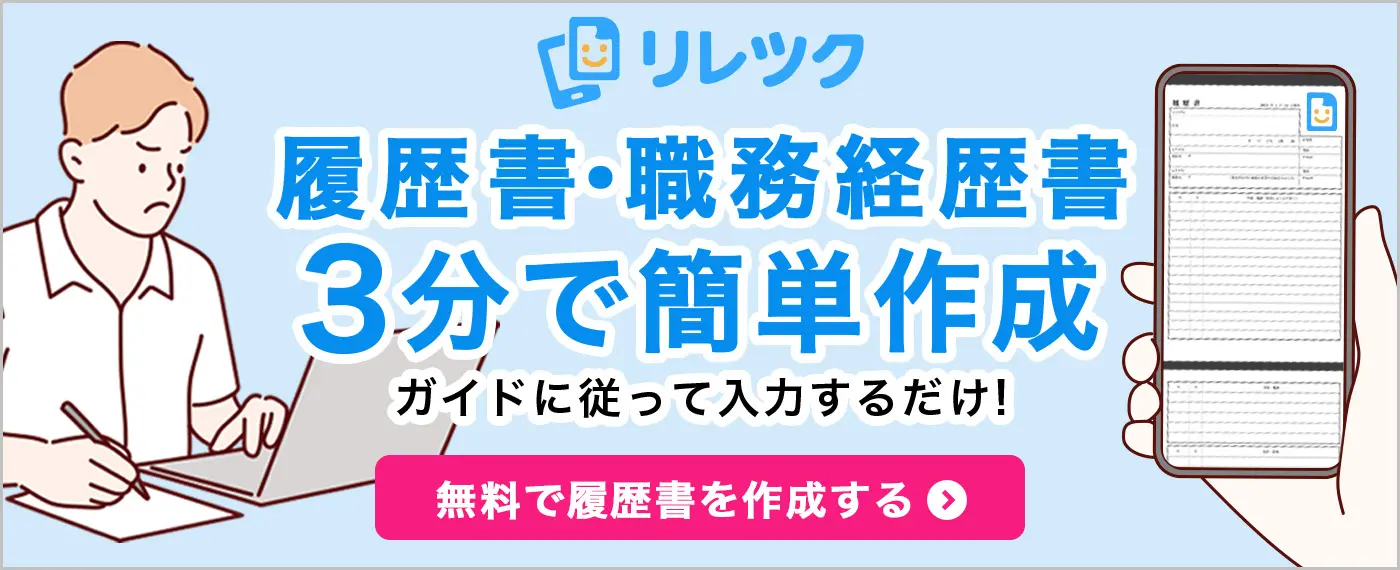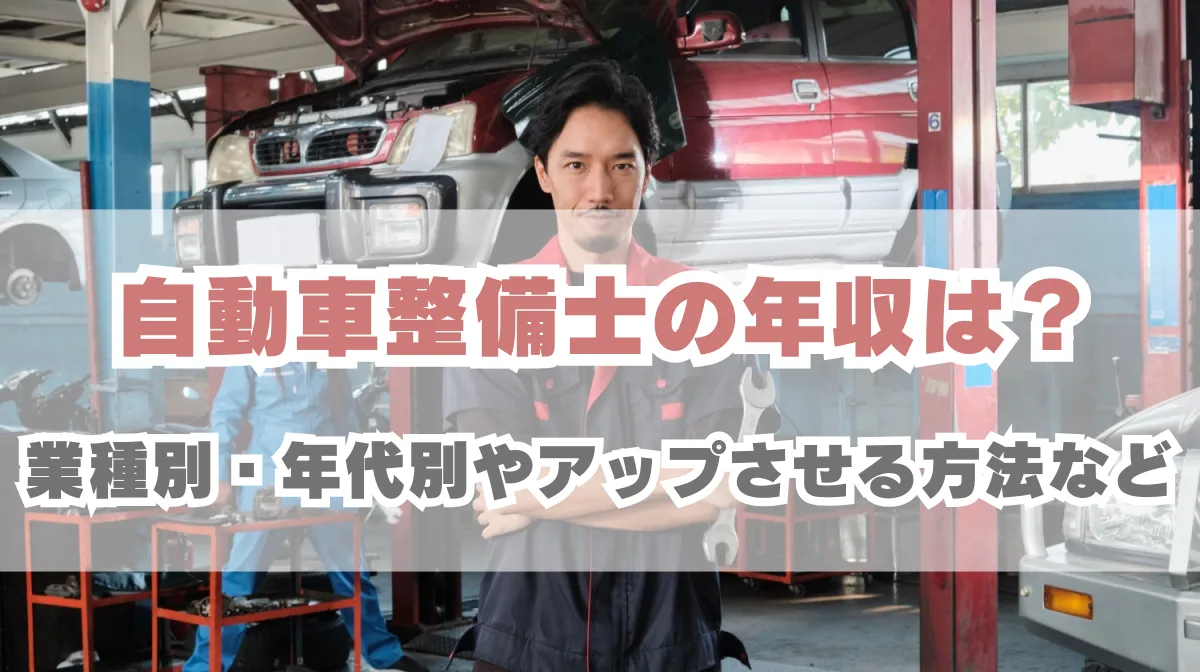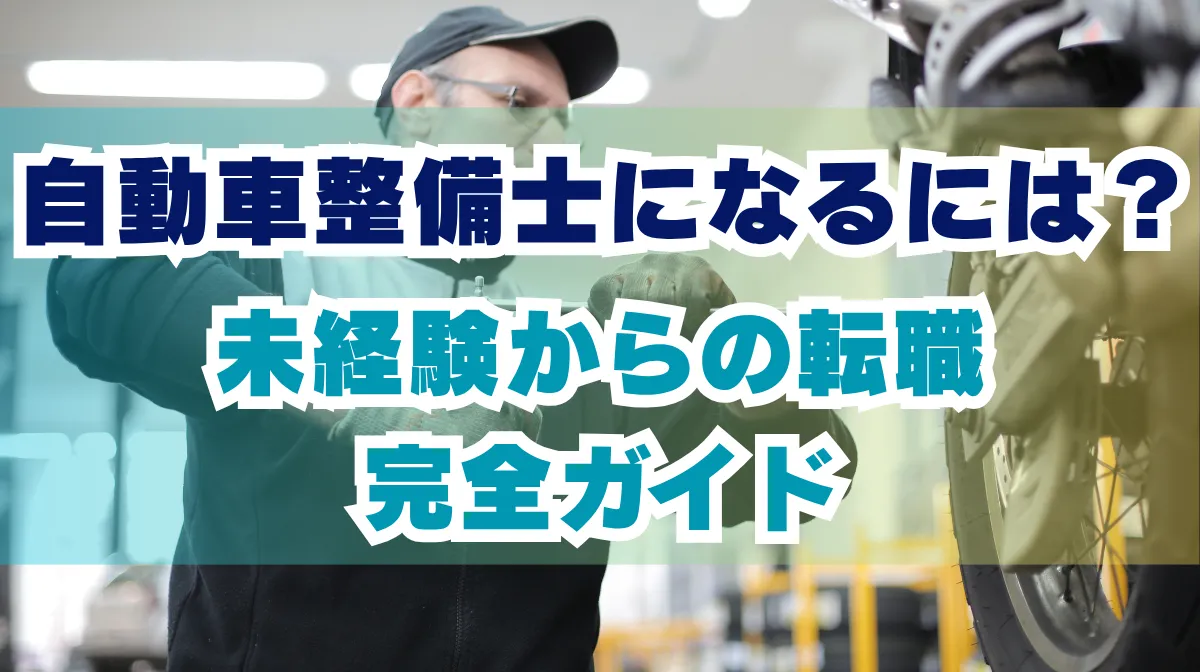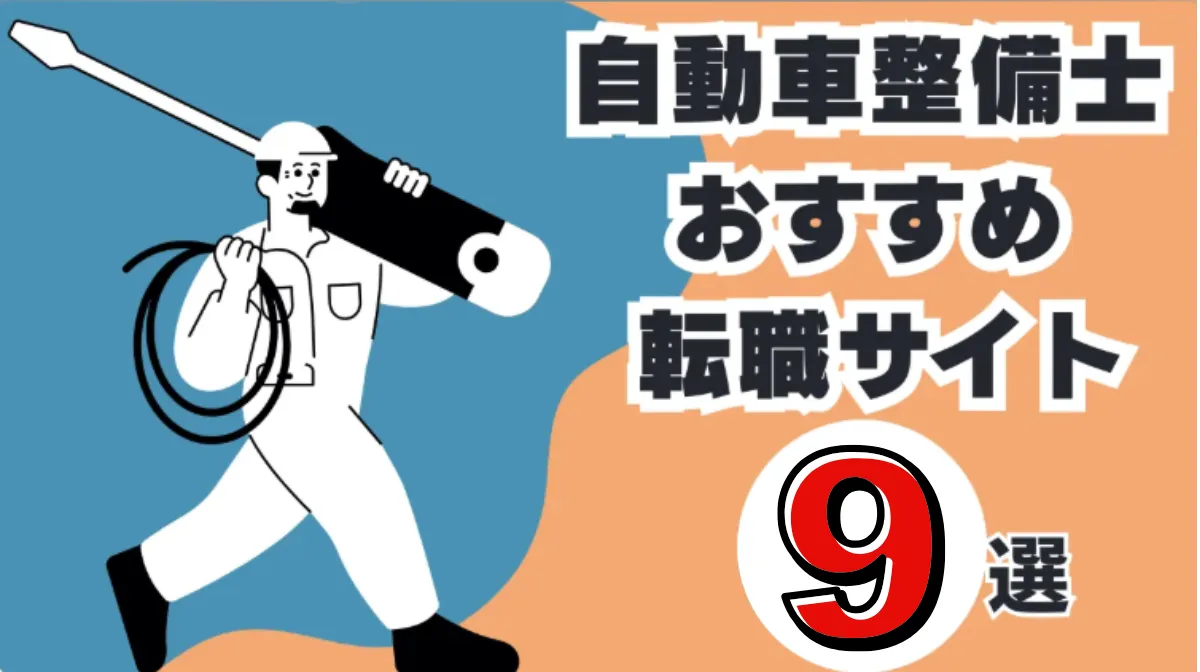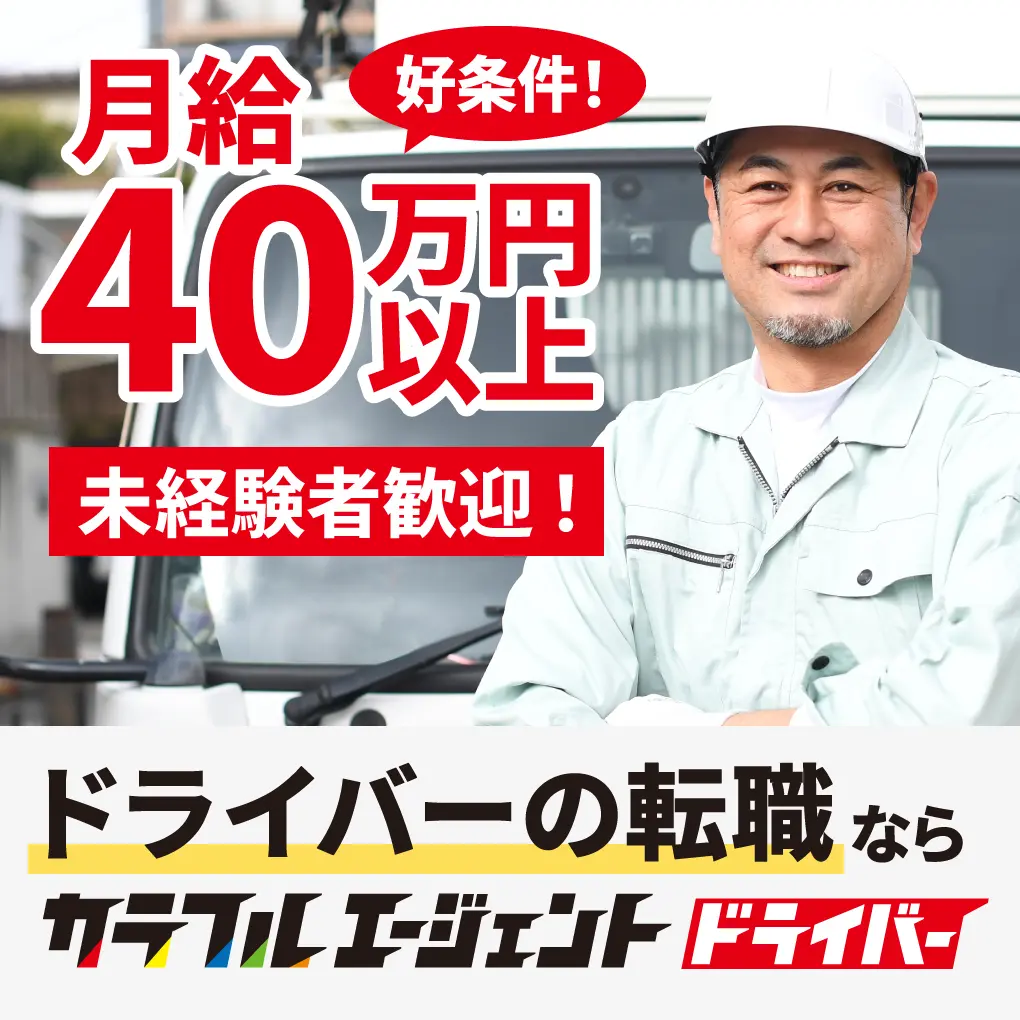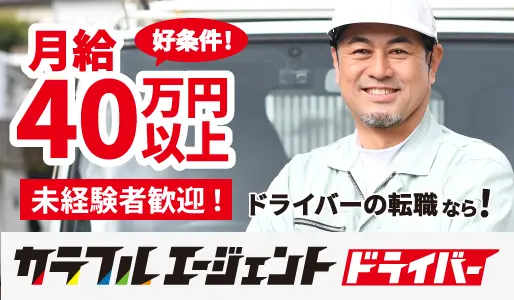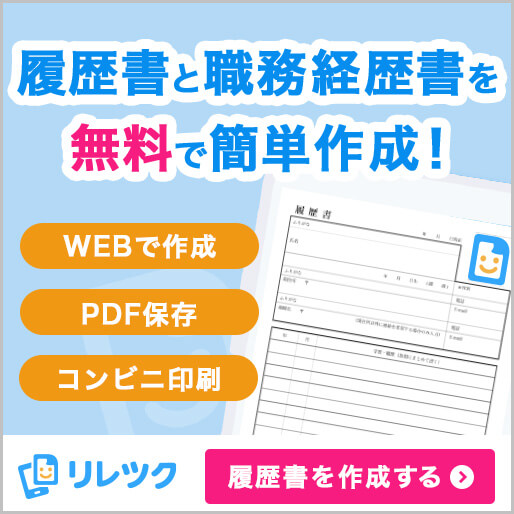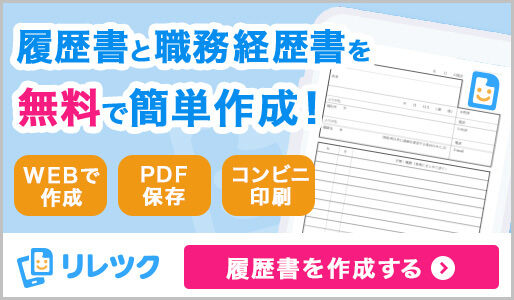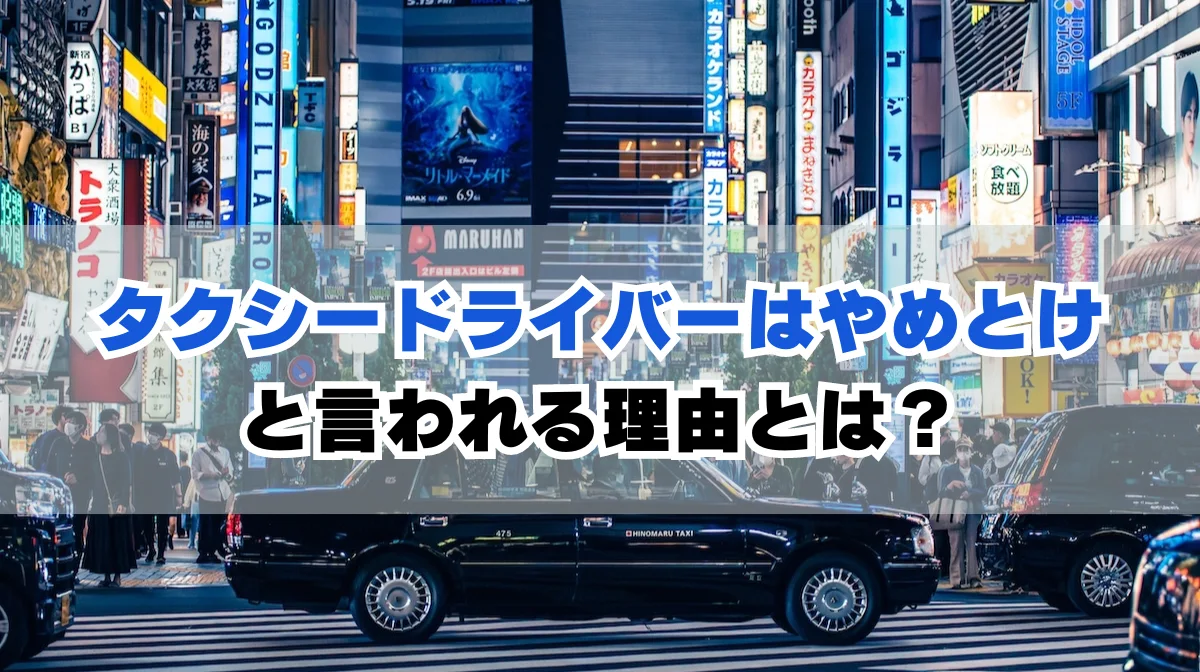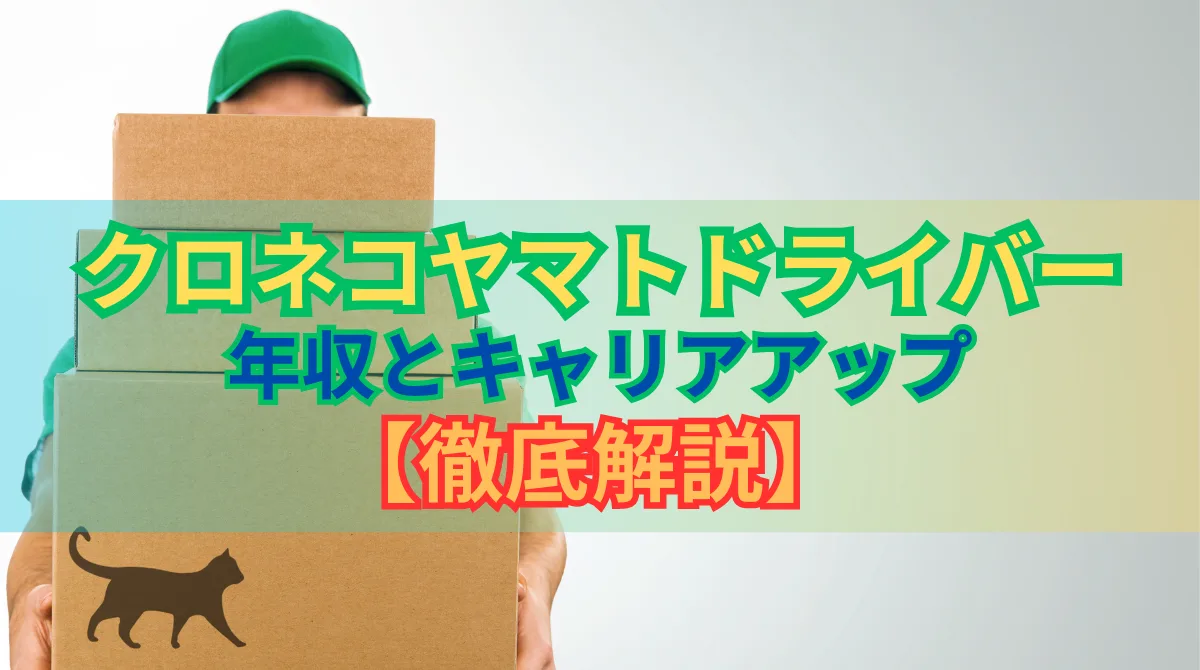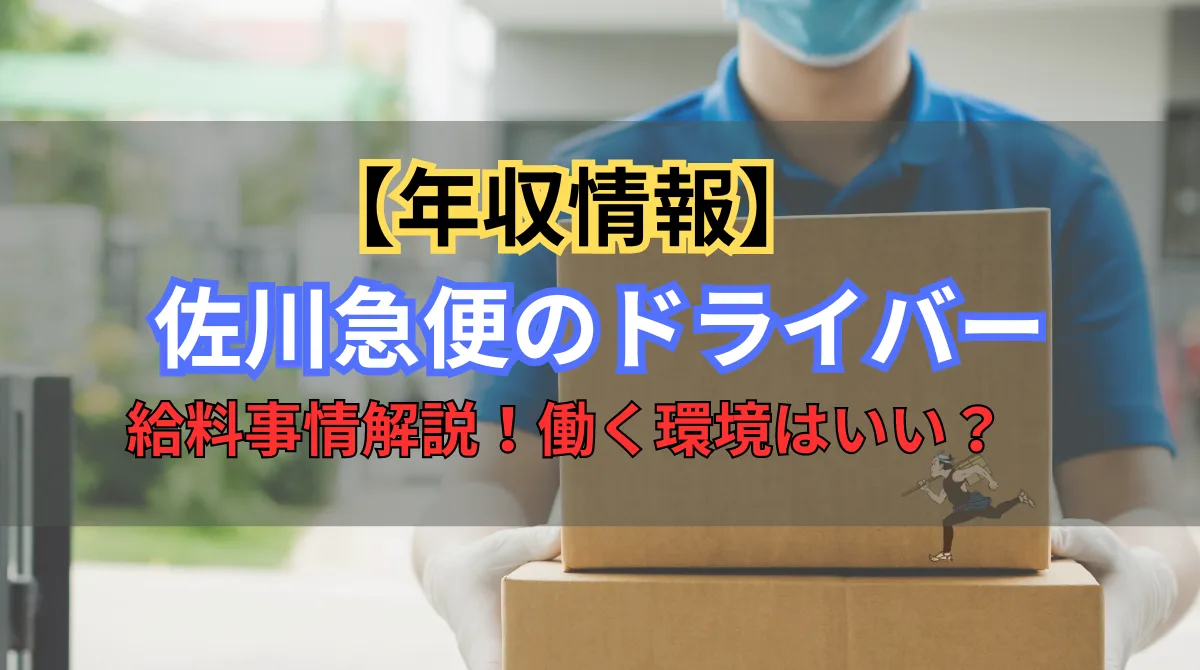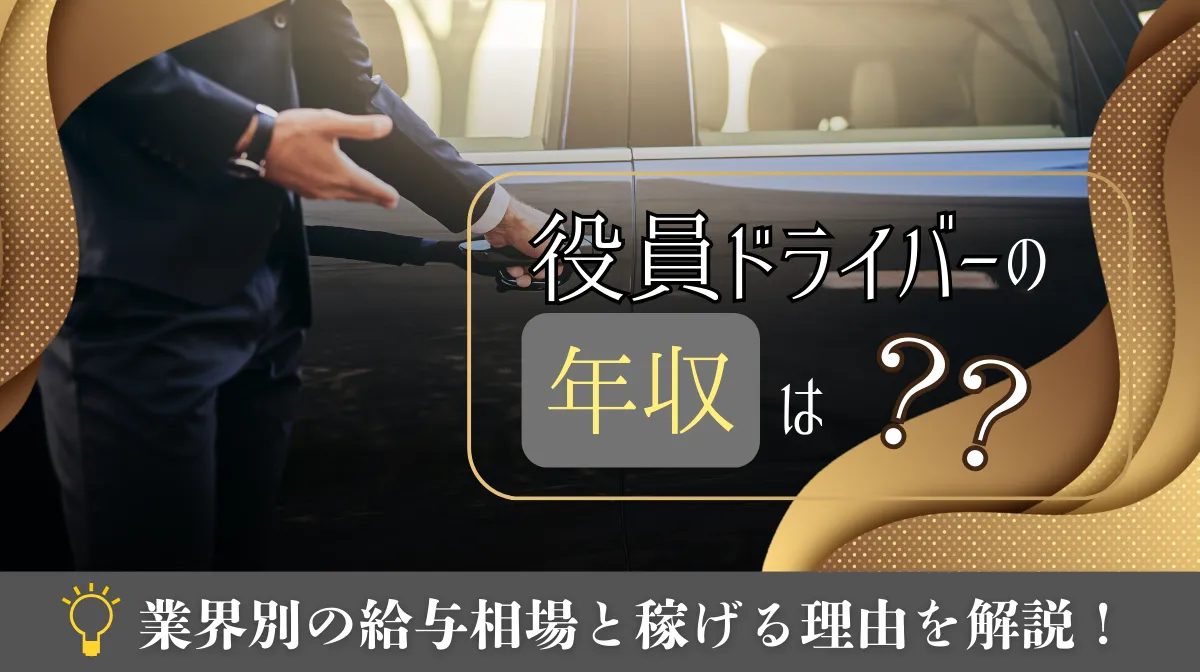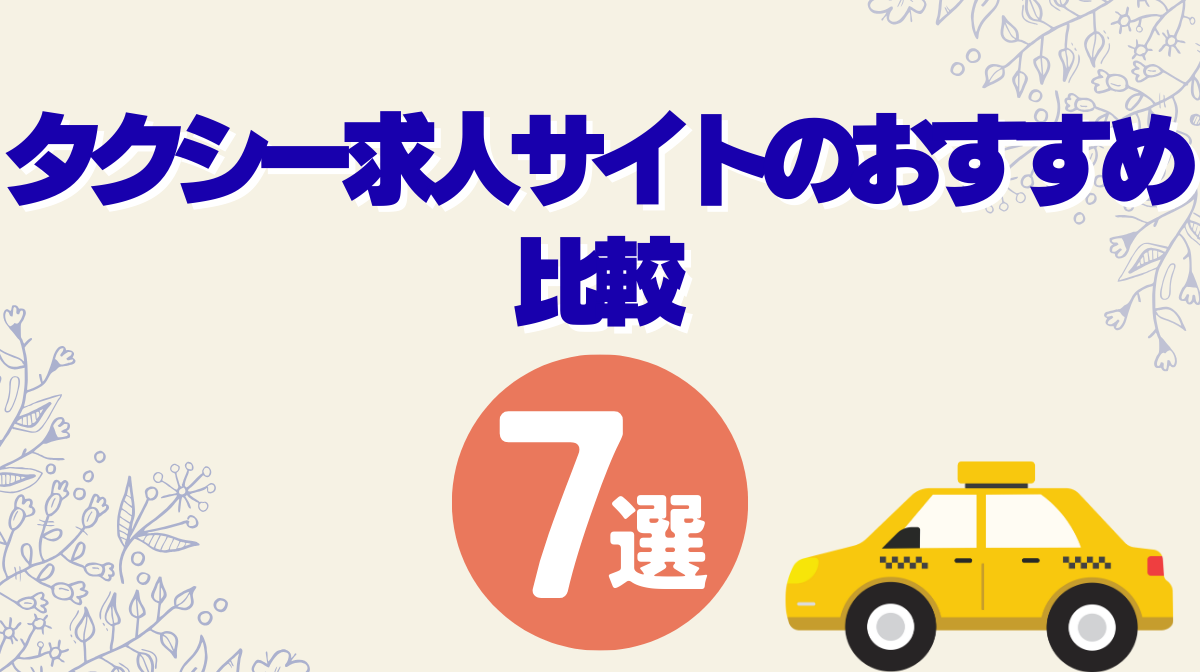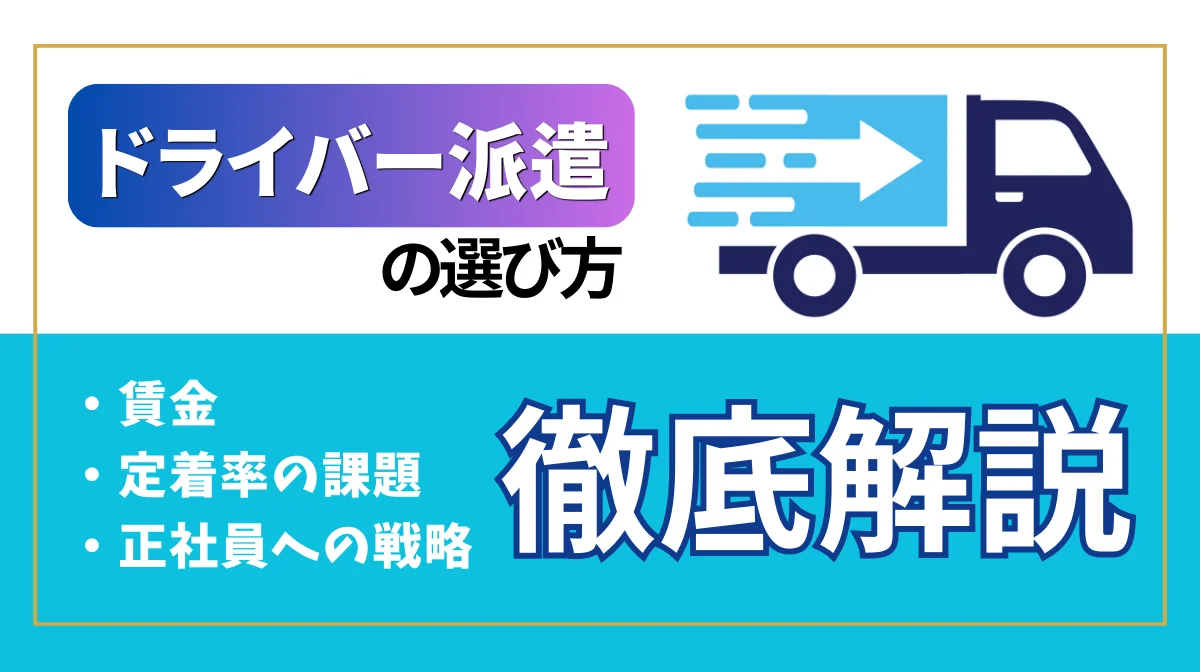自動車整備士に興味を持ったとき、適性や「きつい」という評判が気になるでしょう。車への情熱は重要ですが、お客様の命を預かる高い責任感と専門技術も必要です。
現在、業界はEVや自動運転技術により100年に一度の変革期にあり、新技術を学ぶ意欲がある人には市場価値を高める絶好の機会です。
この記事では、必要な適性、仕事のやりがいと厳しさ、将来性を解説します。
- 自動車整備士に向いている人の具体的な特徴10選
- 仕事のやりがい、厳しい現実、そして将来性
- 自動車整備士になるために必要な資格とキャリアパス
1.まずはセルフチェック!自動車整備士に向いている人の10の共通点
自動車整備士として活躍している人には、いくつかの共通点があります。ご自身に当てはまるか、セルフチェックしてみてください。
2.「車好き」だけでは通用しない?整備士に本当に必要な3つの力
「車が好き」という情熱は、この仕事を続ける上で大きなモチベーションになります。しかし、それだけで専門職として活躍し続けるのは難しいのも現実です。特に以下の3つの力は、これからの時代に不可欠です。
1. 新しい技術を学び続ける「学習意欲」
自動車業界は今、EV、ハイブリッド、自動運転、コネクテッドカーといった技術革新の真っ只中にあります。従来のガソリンエンジンの知識だけでは対応できない領域が急速に広がっています。
整備士は「資格を取ったら終わり」ではなく、むしろそこからがスタートです。
新しい技術や診断機器の使い方を生涯にわたって学び続ける「学習意欲」こそが、将来性を左右する重要な力となります。
▼あわせて読みたい
自動車整備士の具体的な仕事内容や1日の流れを知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。実際の業務イメージを持つことで、適性判断の参考になります。
2. 命を預かる「責任感」と「集中力」
整備士の仕事は、医師の仕事と似ている面があります。それは、どちらも「命」を預かるからです。
整備士の小さな見落としやミスが、大事故につながる可能性があります。
「このくらい大丈夫だろう」という慢心は許されません。お客様の安全を守るという強い「責任感」と、細部まで見逃さない「集中力」が重要です。
3. 顧客や仲間と連携する「対人スキル」
整備士は、黙々と作業だけしていれば良いわけではありません。
お客様に対しては、「なぜこの部品交換が必要なのか」「費用はいくらかかるのか」を、専門用語を使わずに分かりやすく説明する能力が求められます。
また、職場では工場長や他の整備士と情報を共有し、効率よく作業を進めるためのチームワークが不可欠です。技術力と同じくらい「対人スキル」が重視されるのです。
3.逆に注意が必要なケースは?自動車整備士に向いていないかもしれない人の特徴
一方で、以下のような特徴が強く当てはまる場合は、この仕事で苦労するかもしれません。
ただし、これらは現時点での傾向です。キャリア倫理の観点からは、仕事を通じて意識的に改善していくことも十分に可能です。
4.自動車整備士の仕事のやりがいと厳しい現実

どんな仕事にも、やりがいと厳しさの両面があります。
入社後のミスマッチを防ぐためにも、両方を理解しておくことが重要です。
やりがい:技術で問題を解決し、直接「ありがとう」と言われる
自動車整備士の最大のやりがいは、自身の専門技術で故障という「問題」を解決し、車の調子を元通りにできることです。
原因不明の不調を突き止め、修理が完了したときの達成感は格別です。
そして何より、修理を終えた車を納車した際に、お客様から「ありがとう、助かったよ」と直接感謝の言葉をもらえることが、大きなモチベーションになります。
現実:「きつい」「給料が安い」は本当?データの真実
「整備士の仕事はきつい(3K)」「給料が安い」といったイメージは、残念ながら一部事実を含んでいます。
厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)によると、自動車整備士の平均年収は全国平均で約513万円(令和6年)です。
また、日本自動車整備振興会連合会(JASPA)の調査では、整備士の平均年収は上昇傾向にあり 、特にディーラー勤務の場合は平均年収が500万円を超えているというデータもあります。
また、夏は暑く冬は寒い工場での作業や、体力的な負担、繁忙期の残業なども「きつい」と感じる要因でしょう。
ただし、給与は勤務先(ディーラー、民間の整備工場、大手チェーン店など)や、保有資格(1級・2級)、役職(検査員、工場長)によって大きく変動します。
参考|厚生労働省:自動車整備士 – 職業詳細、日本自動車整備振興会連合会:自動車整備要員給与調査
▼あわせて読みたい
自動車整備士の年収を業種別・年代別に詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。年収アップの具体的な方法も解説しています。
5.将来性はある?データが示す自動車業界の人手不足と整備士の未来

結論から言えば、専門技術を身につけた自動車整備士の将来性は明るいです。
現在、自動車整備士業界は深刻な人手不足に陥っています。若者の車離れや仕事の厳しさから、なり手が減少している一方で、ベテラン整備士の高齢化が進んでいるためです。
この「需要と供給のアンバランス」は、働く側にとっては「売り手市場」であることを意味します。
さらに、EVや自動運転技術の普及により、整備に高度な電子制御の知識や専用の診断機器が必要になっています。このため、「新しい技術に対応できる整備士」の価値はますます高騰しています。
古い知識しかない整備士は淘汰されますが、学習意欲のある整備士は、今後さらに必要とされる専門職となるでしょう。
▼あわせて読みたい
自動車整備士の人手不足がどれほど深刻化しているのか、具体的なデータと今後の見通しについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
■派遣で市場価値を高める働き方
人手不足が深刻化する今、整備士の市場価値は高まっています。派遣という働き方なら、複数のディーラーや整備工場で経験を積み、幅広いスキルを短期間で習得できます。カラフルスタッフィング メカニックでは、あなたのキャリアプランに合わせて、最適な職場をご提案します。新技術を学べる環境や、高待遇の求人も豊富に取り揃えています。
▼カラフルスタッフィング メカニックへのお問い合わせはこちら
6.未経験や女性でも自動車整備士になれる?

未経験からでも自動車整備士を目指すことは可能です。多くの整備工場では、人手不足を背景に「資格取得支援制度」を設け、働きながら学校(夜間・通信など)に通い、資格取得をサポートしています。
また、人手不足に対応するため、国土交通省は3級整備士資格の受験に必要な実務経験の要件を緩和する方針も示しています。
まずは資格が不要な整備補助(洗車、オイル交換など)からスタートし、実務経験を積みながら3級、2級とステップアップしていくのが一般的です。
また、国土交通省も女性整備士(愛称:整備“女子”)の活躍を推進しており、女性が働きやすい職場環境(更衣室やトイレの整備、育児休暇制度など)の整備が進んでいます。体力面をサポートする工具の進化もあり、女性整備士は年々増加傾向にあります。
参考|国土交通省:自動車整備業における女性が働きやすい環境づくりのためのガイドライン
▼あわせて読みたい
未経験から自動車整備士への転職を考えている方には、こちらの完全ガイドがおすすめです。具体的なステップと転職成功のポイントを解説しています。
■未経験から整備士を目指すなら派遣がおすすめ
未経験から整備士を目指す方には、派遣でのスタートがおすすめです。カラフルスタッフィング メカニックなら、資格取得支援制度のある職場や、未経験者歓迎の求人を多数ご紹介できます。専門コーディネーターが、あなたの経験やスキルレベルに合った職場を見つけ、キャリアアップをサポートします。まずは整備補助からスタートし、実務経験を積みながら資格取得を目指しましょう。
▼カラフルスタッフィング メカニックへのお問い合わせはこちら
7.自動車整備士になるには?必要な資格とキャリアパス

自動車整備士として働くためには、原則として国家資格が必要です。
国家資格「自動車整備士」の仕組み
自動車整備士の資格は、技術レベルに応じて「1級」「2級」「3級」に分かれており、さらに扱う車種によって「ガソリン」「ジーゼル」「二輪」などに細分化されています。(一般的な乗用車は2級ガソリン・ジーゼル)
多くの場合、専門学校などで2級整備士の資格を取得して就職するか、未経験で就職して実務経験を積みながら3級、2級の受験資格を得るというルートを辿ります。
主なキャリアパス(検査員、工場長、独立など)
整備士としてのキャリアは多様です。
技術を極めて「自動車検査員」(車検の最終判断ができる資格)になる道や、経験を積んで現場をまとめる「工場長」になる道が一般的です。
また、お客様対応のスキルを活かして、整備の受付や見積もりを行う「フロントアドバイザー」に転身する道もあります。さらに、十分な技術と経営ノウハウを身につけて、自身の整備工場を「独立開業」する人もいます。
▼あわせて読みたい
転職を考えている整備士の方には、転職サイトの活用が効果的です。2025年最新のおすすめ転職サイトを比較したこちらの記事をご覧ください。
■派遣でキャリアパスを広げる
整備士としてのキャリアパスは多様ですが、派遣という働き方なら、さらに選択肢が広がります。カラフルスタッフィング メカニックでは、検査員や工場長を目指せる職場から、フロントアドバイザーなど対人スキルを活かせるポジションまで、幅広い求人をご用意しています。複数の職場を経験することで、自分に最適なキャリアを見つけることができます。
▼カラフルスタッフィング メカニックへのお問い合わせはこちら
8.適性を見極め、需要の高い専門職を目指そう
自動車整備士は、「車好き」という情熱を土台に、「命を預かる責任感」と「進化する技術を学ぶ学習意欲」が求められる専門職です。
体力的な厳しさや、常に学び続けなければならないプレッシャーもありますが、それ以上に、技術で問題を解決する達成感や、社会インフラを支える誇りを感じられる仕事です。
深刻な人手不足と技術革新の波により、専門スキルのある整備士の市場価値は高まり続けています。
この記事で紹介した適性を参考に、ご自身のキャリアをデザインする上での判断材料としていただければ幸いです。