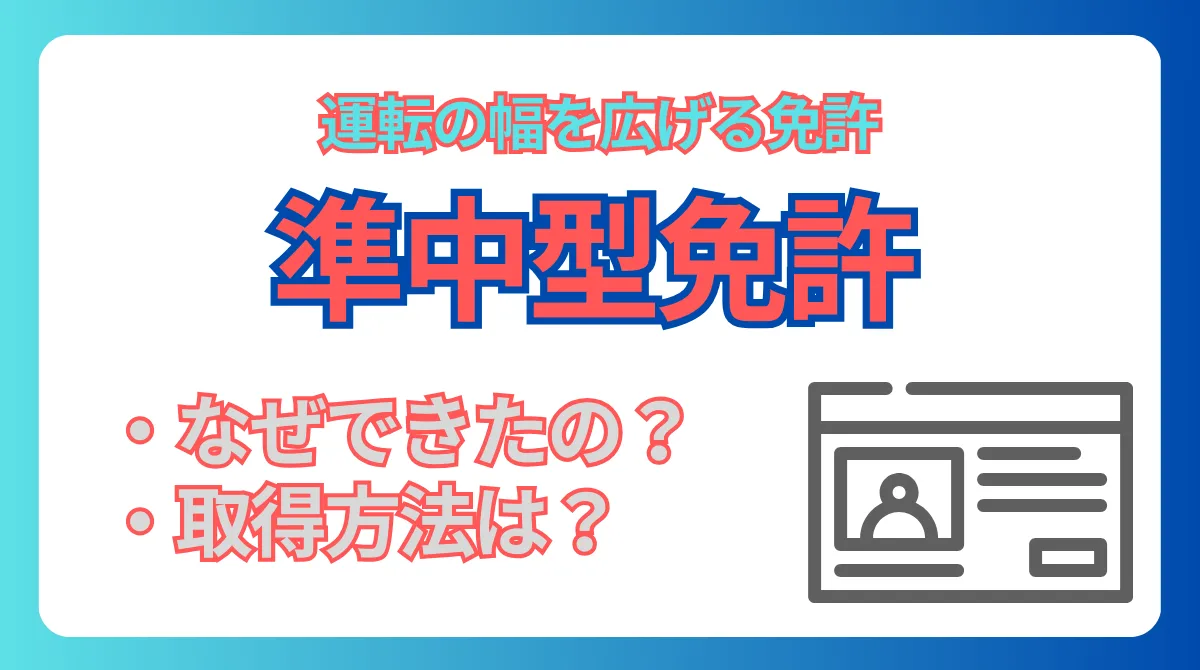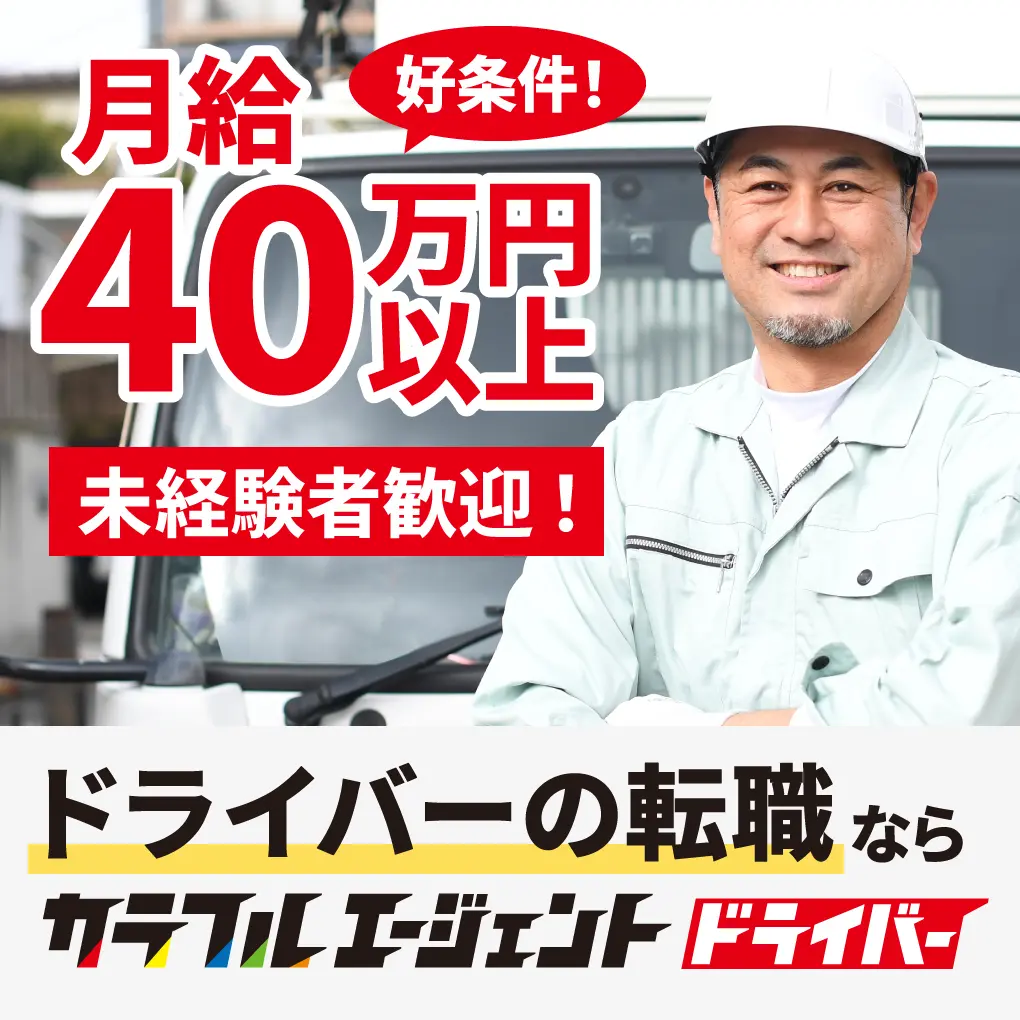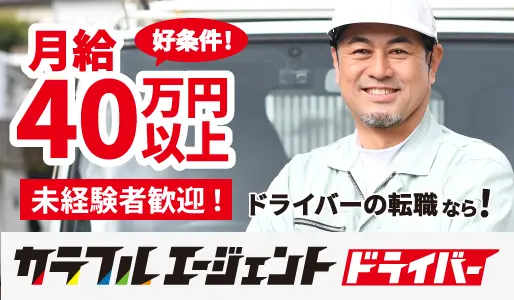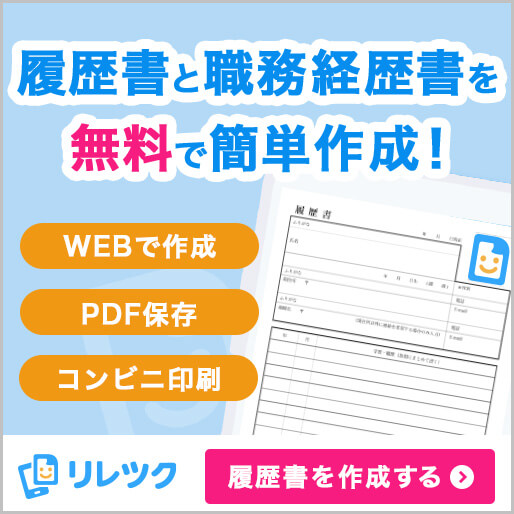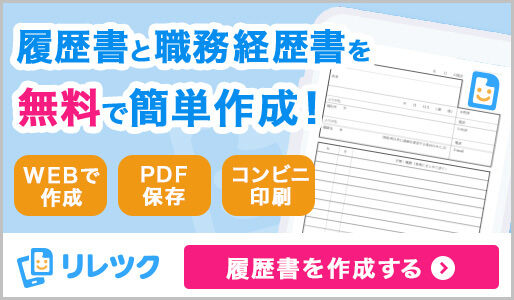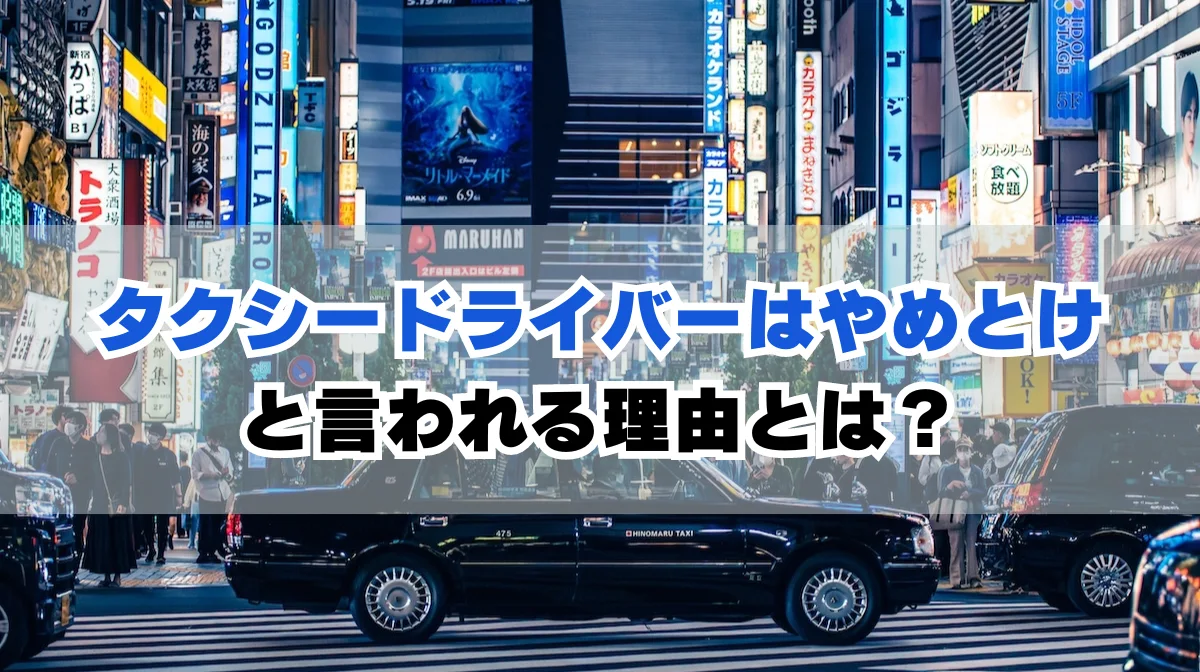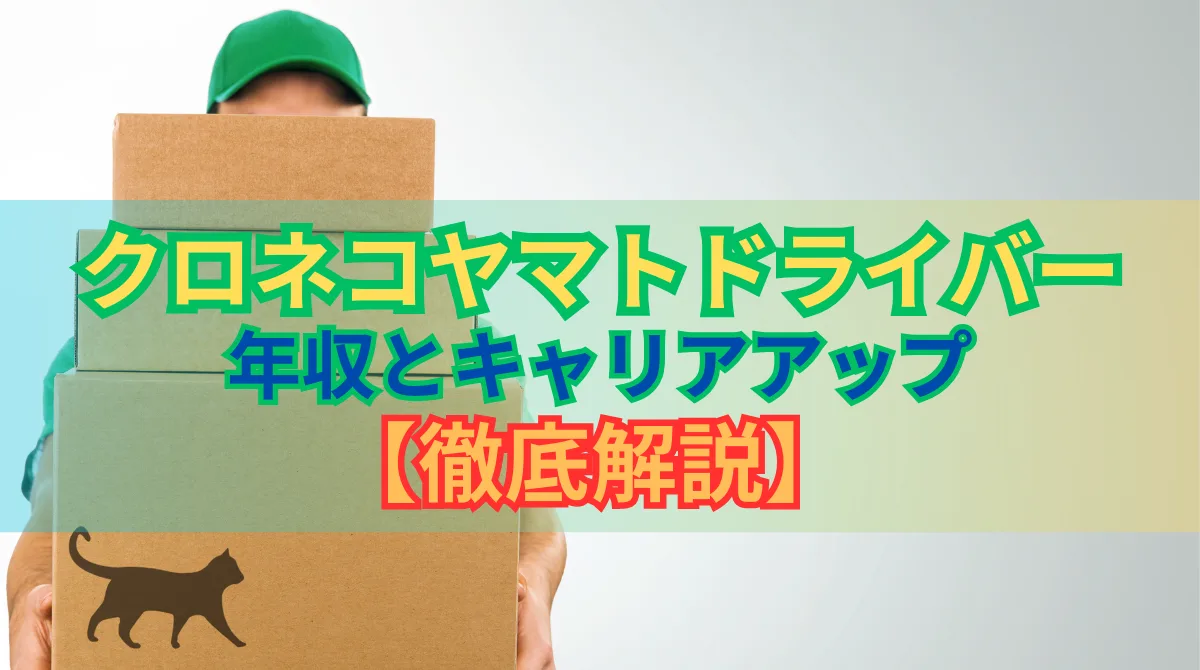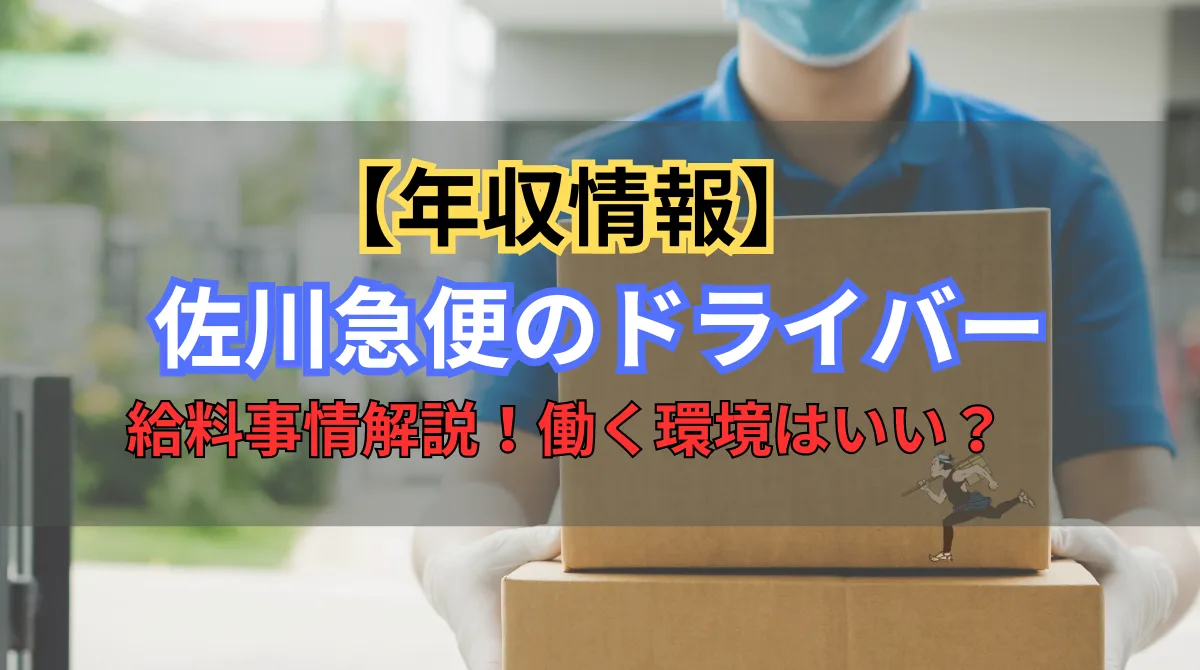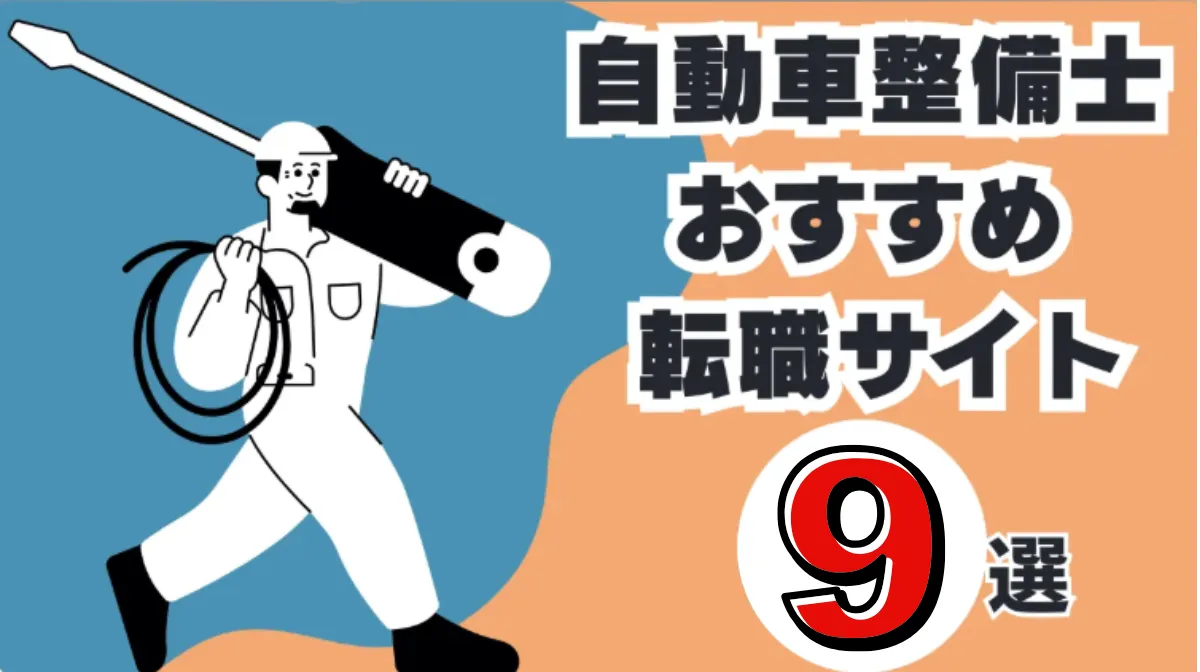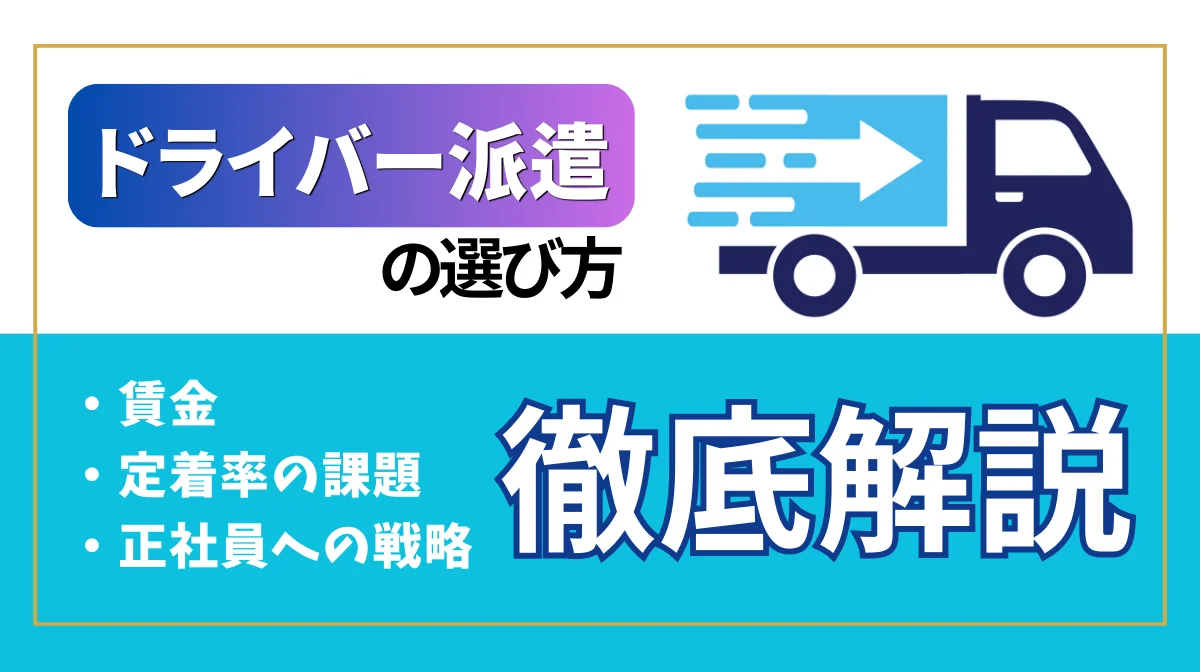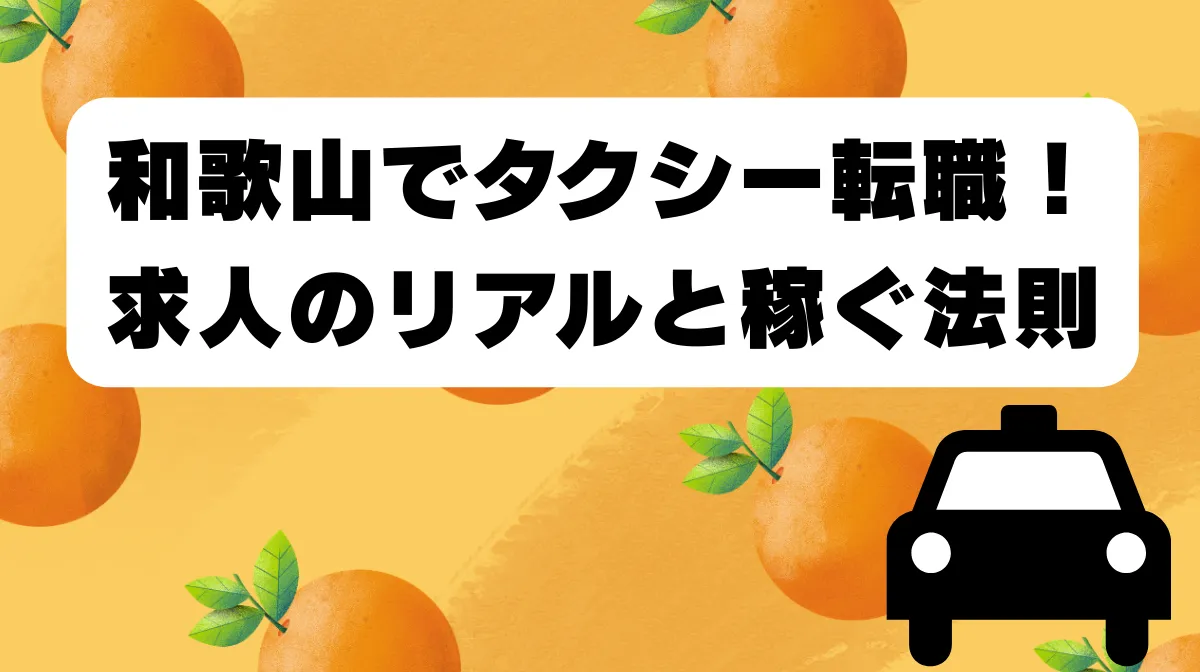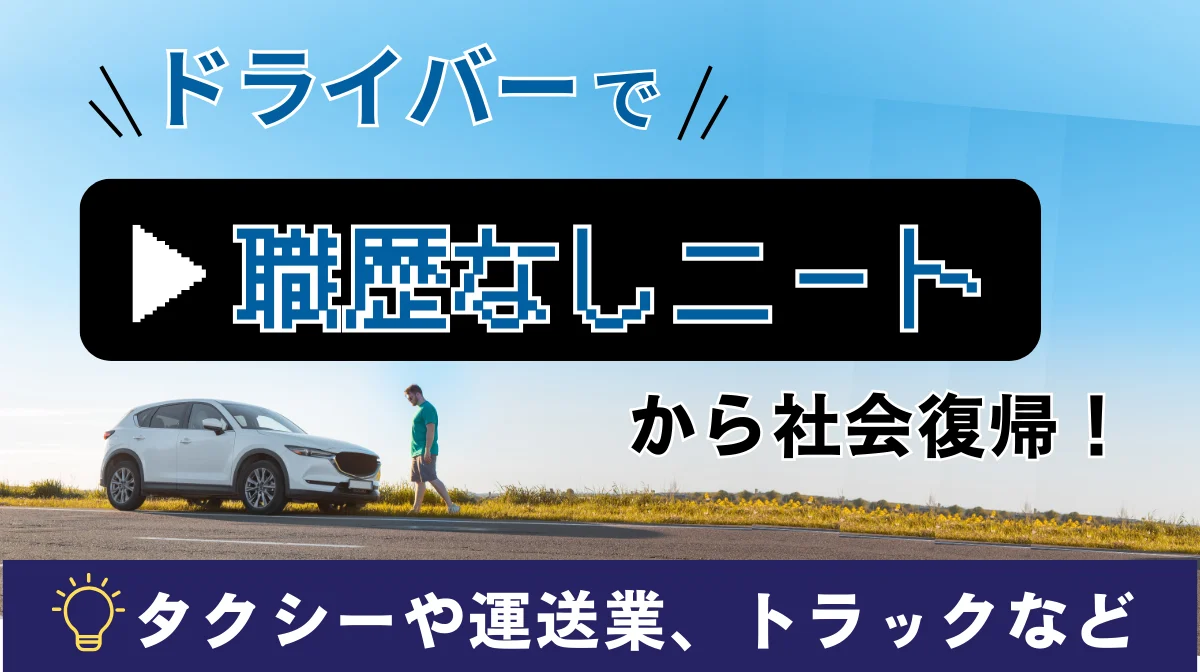18歳になったら、自動車免許の取得ができますが、運送業界での就業を考えている方は、準中型免許の取得も選択肢の一つとして知っておくとよいでしょう。
準中型免許は、2007年の道路交通法改正により新設された免許区分です。準中型免許を取得することで、運送業界をはじめとする様々な職種で活躍できるチャンスが広がります。
この記事では、準中型免許を取得するメリットと、免許を活かせる仕事の可能性について詳しく解説していきます。
- 準中型免許で就けるドライバーの仕事
- 運送業界の人手不足と若手ドライバーの需要
- 準中型免許取得によるキャリアアップのチャンス
- 免許取得が将来の選択肢を広げる理由
1.準中型免許とは?免許制度改正の背景と特徴

準中型免許新設の経緯と目的
準中型免許は、2017年3月の道路交通法改正により新しく設けられた免許区分です。
従来、普通免許で運転できる自動車の車両総重量は5トンまででしたが、準中型免許新設に伴い、普通免許で運転可能な上限が3.5トンに引き下げられました。
この制度改正の主な目的は、交通事故の削減と物流業界の人材不足解消の2点にあります。
5トン未満の中型自動車による事故が多発していたことから、免許区分を細分化することでより適切な運転技能を担保すること、そして18歳から準中型免許の取得を可能にすることで若年層のドライバー確保を狙いとしています。
普通免許との違いと運転できる車両の範囲
準中型免許で運転できるのは、車両総重量が3.5トンから7.5トン未満の自動車です。
代表的な車種としては、2トントラックやウィング車、小型ダンプなどが該当します。ただし、牽引できるトレーラーの重量は750kg未満に制限されています。
また、準中型免許には5トン限定と7.5トン限定の2種類があります。
法改正以前に普通免許を取得済みの方は「5トン限定」の準中型免許となり、新たに準中型免許を取る場合は「7.5トン限定」となるのが一般的です。
もう一つの大きな違いは、初心者マークの扱いです。普通免許では初心者マークの義務はありませんが、準中型免許は取得後1年間は初心者マークの表示が義務付けられます。
これは準中型車両の安全運転のために設けられた措置と言えるでしょう。
| 改正前区分 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 普通免許 | 中型免許 | 大型免許 |
| 自動車の種類 | 普通自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 |
| 車両総重量 | 5トン未満 | 5トン以上11トン未満 | 11トン以上 |
| 最大積載量 | 3トン未満 | 3トン以上6.5トン未満 | 6.5トン以上 |
| 乗車定員 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |
| 受験資格年齢 | 18歳以上 | 20歳以上 | 21歳以上 |
| 免許期間 | 不要 | 2年以上 | 3年以上 |
| 改正後区分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 普通免許 | 準中型免許 | 中型免許 | 大型免許 |
| 自動車の種類 | 普通自動車 | 準中型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 |
| 車両総重量 | 3.5トン未満 | 3.5トン以上7.5トン未満 | 7.5トン以上11トン未満 | 11トン以上 |
| 最大積載量 | 2トン未満 | 2トン以上4.5トン未満 | 4.5トン以上6.5トン未満 | 6.5トン以上 |
| 乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |
| 受験資格年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 | 20歳以上 | 21歳以上 |
| 免許期間 | 不要 | 不要 | 2年以上 | 3年以上 |
※普通第二種免許、中型第二種免許、大型第二種免許の受験資格については、21歳以上で3年以上の免許経験を有することが必要となります。
2.準中型免許の取得の流れ

準中型免許を取得するには、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、受験資格から免許証交付までの一連の流れを詳しく見ていきましょう。
受験資格と必要な書類
準中型免許の受験資格は以下の通りです。
- 18歳以上であること
- 適性検査に合格すること
- 視力が両眼で0.8以上、片眼でそれぞれ0.5以上であること
- 深視力が2.0未満であること
- 聴力が10m以上離れた位置から発せられる90デシベル以上の警音器の音が聞こえること
受験に必要な書類は、住民票の写しや本籍の記載された住民票(コピー不可)、身分証明書などです。
また、過去に免許取消処分や停止処分を受けている場合は、行政処分証明書の提出も必要となります。
準中型免許取得に必要な費用
準中型免許の取得費用は、教習所の料金プランによって異なります。標準的な料金は以下の通りです。
- 教習料金:20~30万円程度
- 仮免許申請料:1,100円
- 免許証交付手数料:2,050円
他にも教材費、写真代、適性検査料などの諸経費がかかります。
所持している免許によって変動しますが、総額で25~40万円ほどの費用を見込んでおくとよいでしょう。
参考:準中型免許
教習所のコースと所要時間
準中型免許の教習は、技能教習と学科教習に分かれています。技能教習は41時限(1時限=50分)、学科教習は27時限が所定時限数として定められており、これを修了する必要があります。
時限数は以下の通りです。
- 技能教習:41時限
- 基本練習:15時限
- 応用練習:18時限
- 路上教習:8時限
- 学科教習:27時限
- 自動車の構造・原理:4時限
- 法規:17時限
- 運転の心構えなど:6時限
所要期間は教習所によって異なりますが、最短で17日程度、一般的には1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります。時間的な余裕をもって教習予定を組むことが大切です。
仮免許と本免許の違いと注意点
無事に技能教習と学科教習を修了し、卒業検定にも合格すると、いよいよ仮免許の交付を受けることができます。
仮免許とは文字通り「仮の免許証」であり、交付日から6ヶ月間有効です。
仮免許取得後は、教習所で路上教習を行いながら本免許の学科試験に向けた準備を進めます。本免許の学科試験は90問が出題され、65問以上の正答で合格となります。
学科試験に合格すれば晴れて準中型免許の取得です。免許証の交付を受けたら大切に保管しましょう。
3.準中型免許への限定解除方法と費用
準中型免許の限定解除には、教習所で解除教習を受ける方法と、運転免許試験場で技能試験を受ける方法の2つがあります。
教習所に通う
教習所での限定解除には、技能教習13時限と学科教習1時限が必要です。
教習修了後、卒業検定と修了検定に合格すれば限定解除申請ができます。
手数料は限定解除審査2,850円、限定解除後の免許証交付2,050円で、教習料と合わせると総額10万円程度が目安です。
直接試験を受ける
運転免許試験場で直接技能試験を受験する場合は、学科試験が免除されます。
技能試験に合格し限定解除の申請をすれば、即日解除も可能です。試験受験料に加えて限定解除関連の手数料で5千円程度かかります。
どちらの方法を選ぶにせよ、7.5トン未満の中型貨物自動車の運転に必要な知識とスキルを身につけ、より幅広い車両を運転できるようになることは、キャリアアップの大きなステップと言えるでしょう。
4.準中型免許で18歳でも目指せるドライバーの仕事

準中型免許を取得すると、18歳から運送業界で働けます。
トラックドライバー、ダンプドライバー、引越しドライバー、宅配便ドライバーなど、様々な職種に就けるでしょう。
特にトラックドライバーは人手不足が深刻で、若手ドライバーの需要が高まっています。
初任給は月20万円前後ですが、経験を積むと月30万円以上の収入も可能です。アルバイトから社員登用を目指せるなど、キャリアアップのチャンスも豊富です。
5.準中型免許取得後のキャリアアップ戦略
準中型免許の取得は、ドライバーとしてのキャリアの第一歩に過ぎません。
その先には、より大型の車両を運転できる中型・大型免許の取得や、運送業務の管理を担う運行管理者など、様々なキャリアアップの道が待っています。
ここでは、準中型免許を起点としたキャリア形成の戦略をご紹介しましょう。
大型免許への限定解除で活躍の幅を広げる
準中型免許から5トン限定解除を経て、中型免許(7.5トン以上11トン未満)の取得を目指すのが王道のキャリアステップです。
中型免許があれば、より大きなトラックやバスの運転が可能になり、活躍の幅が一気に広がります。
運送業界では、中型免許保持者の需要が根強いため、キャリアアップや昇給・昇格のチャンスにも恵まれているでしょう。
将来的には大型免許(11トン以上)の取得を視野に入れ、中型免許取得から3年後の受験を目標に据えるのもよいでしょう。
大型トレーラーなどの特殊車両を運転できる大型免許は、ドライバーの登竜門とも言える存在です。年収600万円以上の高収入も夢ではありません。
物流のプロとして管理職を目指すためのステップ
ドライバー経験を積んだら、今度は運行管理者などのキャリアを目指すのも一つの選択肢です。
運送業務の管理全般を担う運行管理者は、安全運行の要として重要な役割を果たします。
運行管理者の資格を得るには、一定の実務経験と国家試験の合格が必要ですが、資格を取得すれば、管理職や専門職としてのキャリアが大きく花開くはずです。
さらに、運送ルートの効率化や倉庫内の荷役作業の改善など、物流のスペシャリストとしてのスキルを磨くことも重要です。
ITツールを活用した業務改善にも積極的に取り組み、常に学び続ける姿勢を忘れずにいきたいものです。
6.準中型免許を取得すること
準中型免許の取得は、18歳からトラックドライバーなどの運送業界で働くチャンスを広げます。
深刻な人手不足の中、若手ドライバーの需要は高く、アルバイトから社員登用を目指せるキャリアアップの可能性もあります。
運転が好きな人や物流業界に興味がある人は、準中型免許の取得で将来の選択肢を広げてみてはいかがでしょうか。