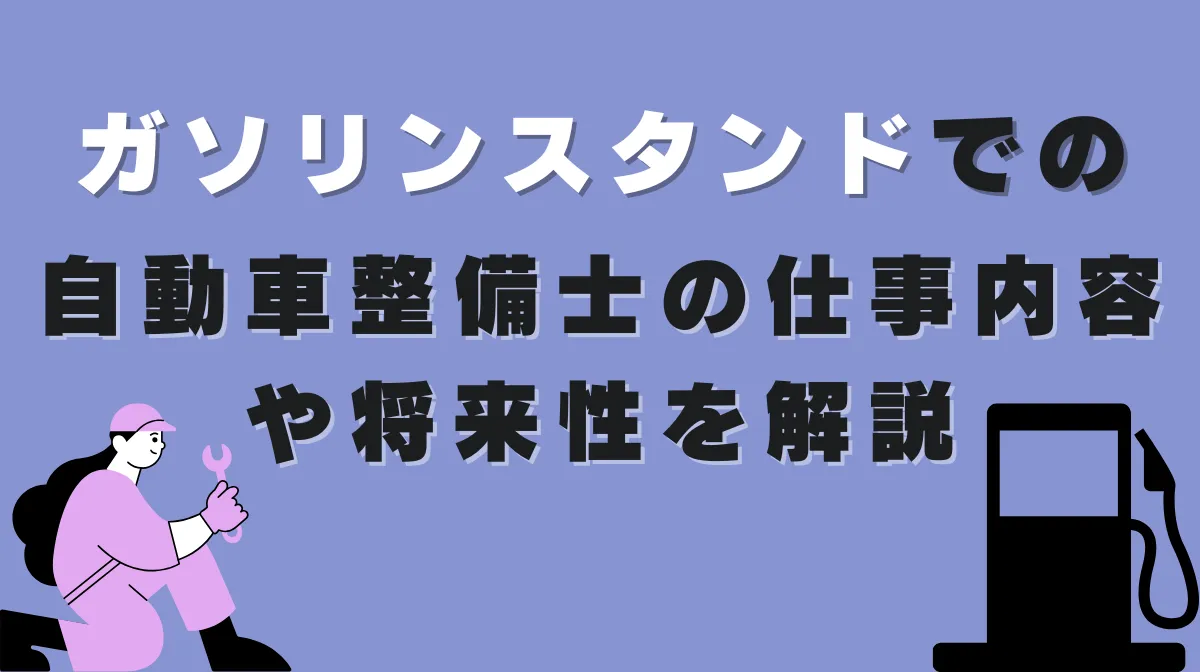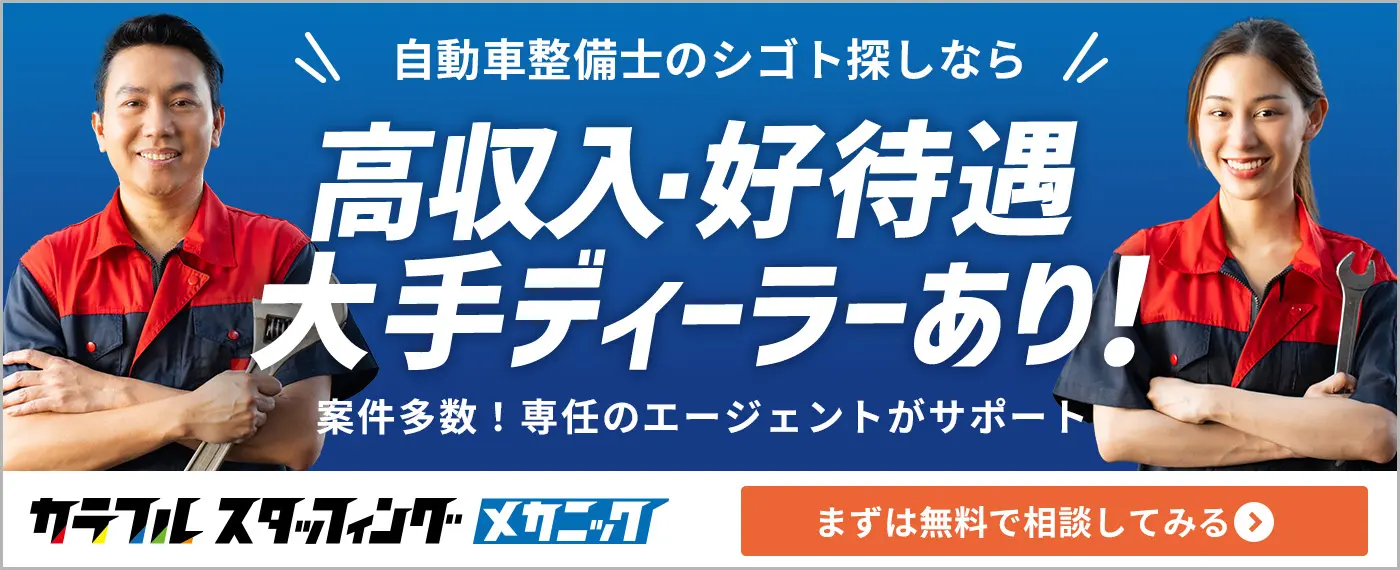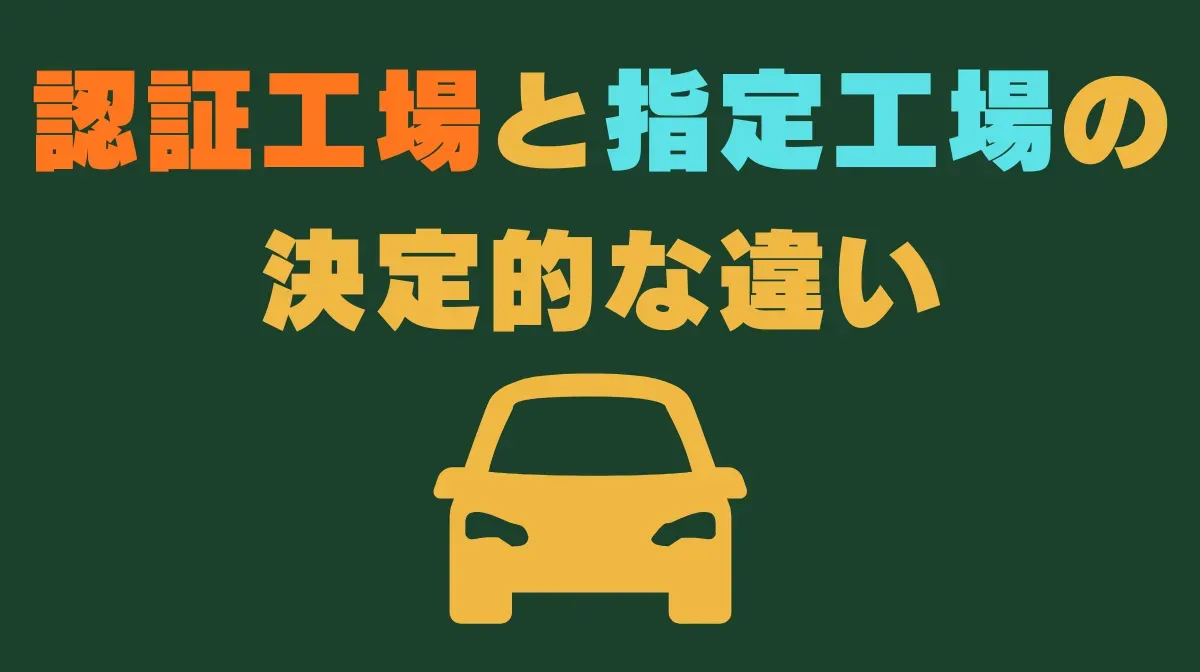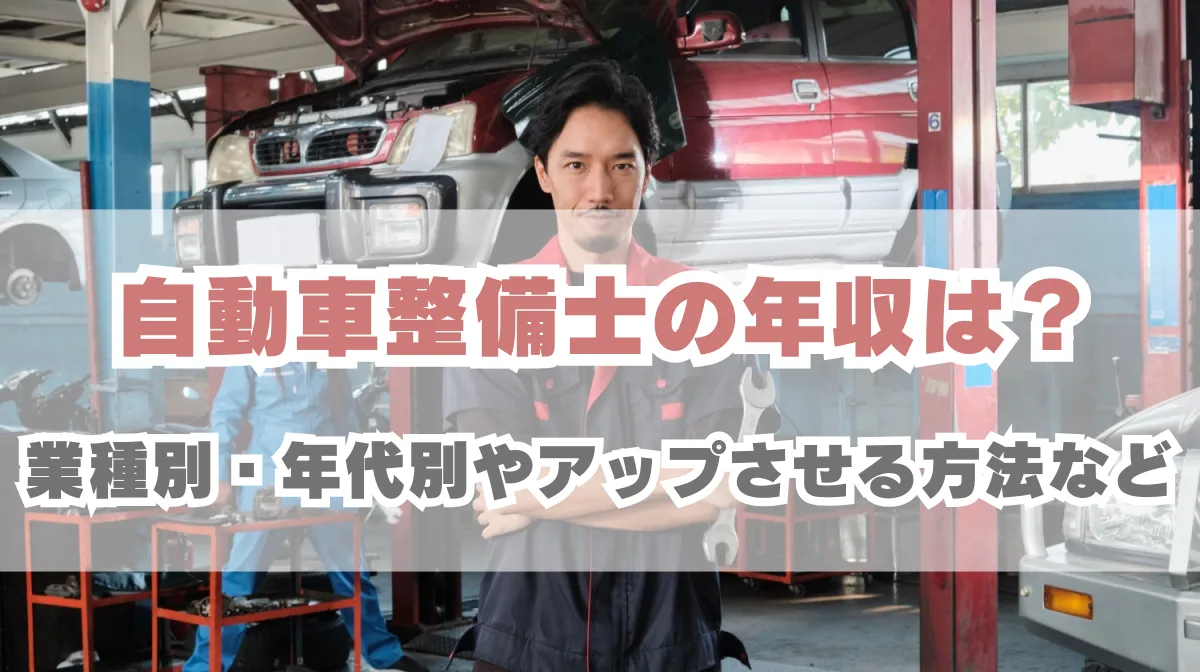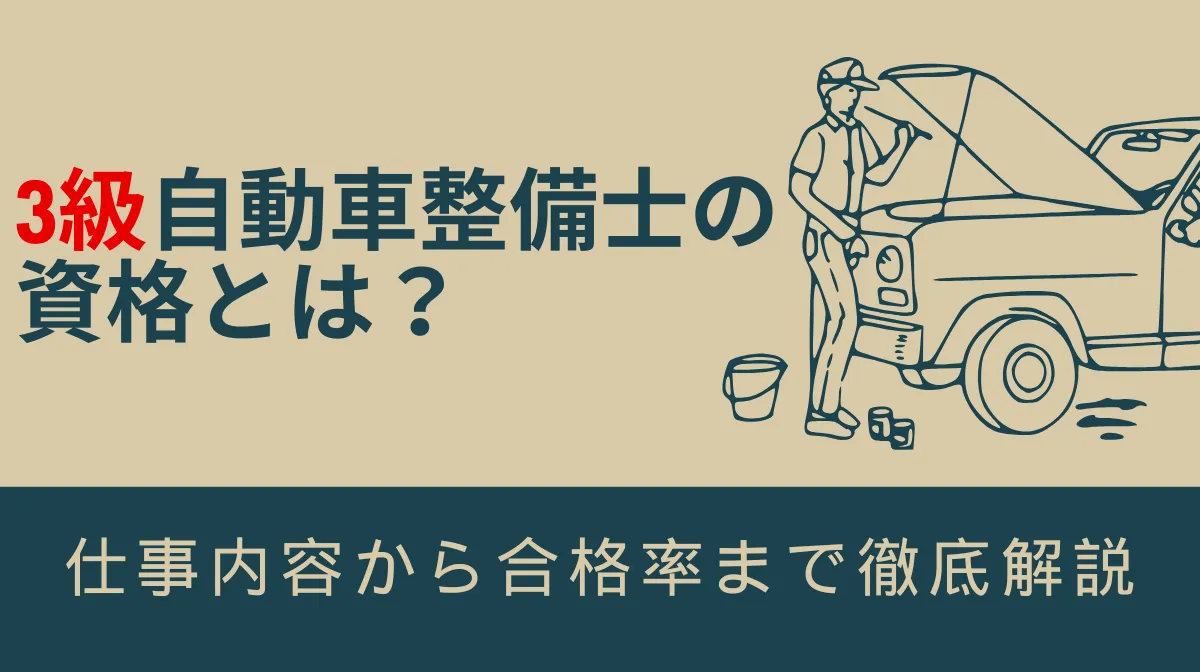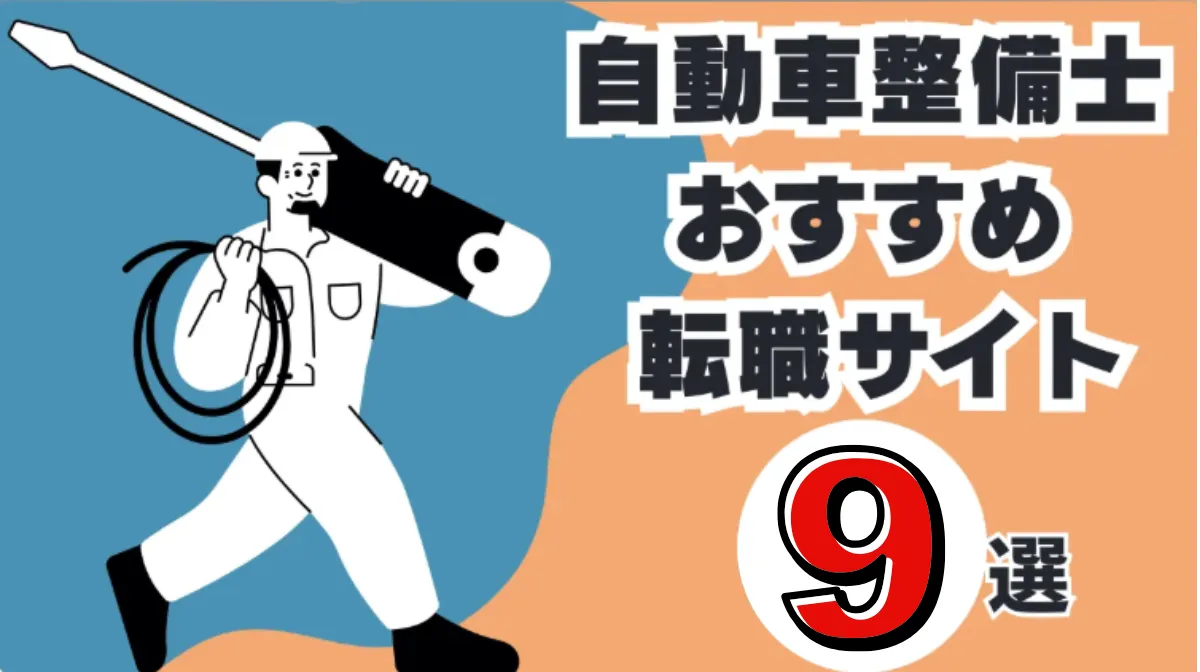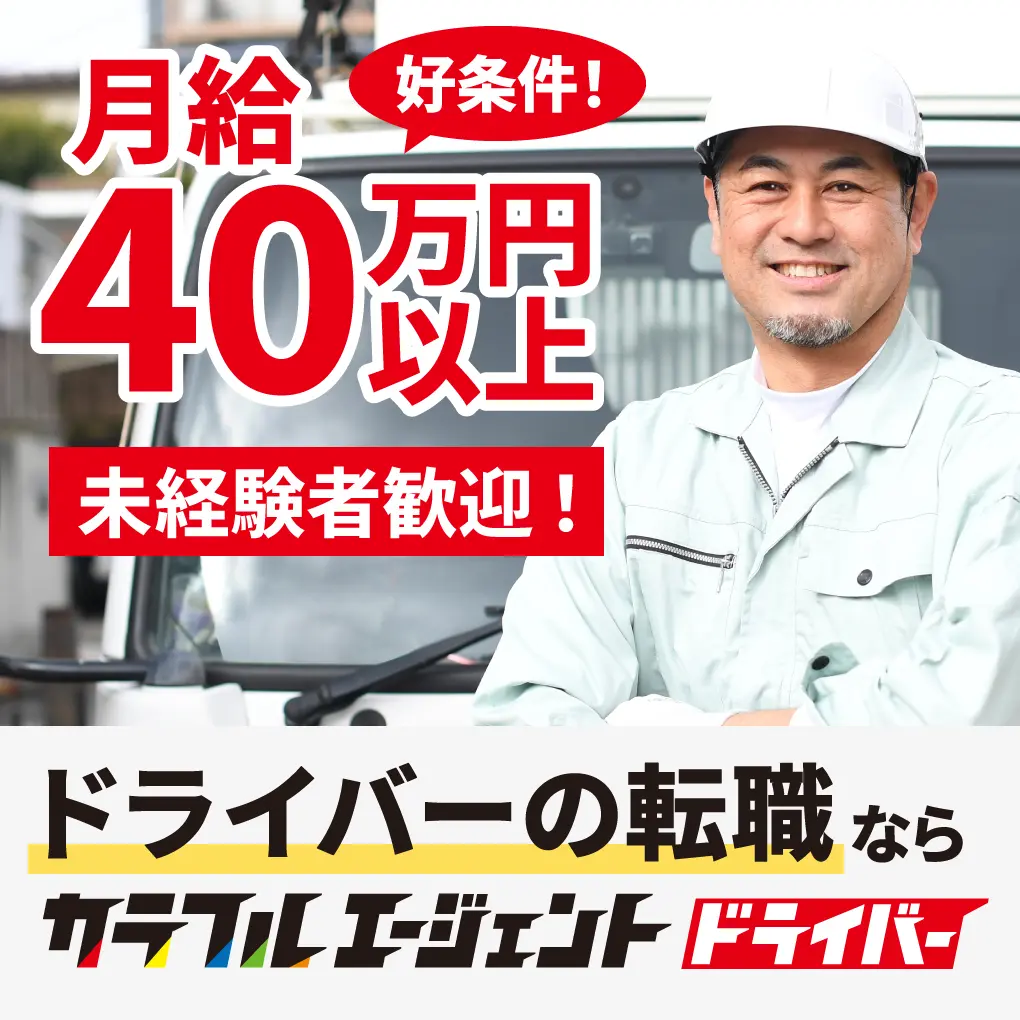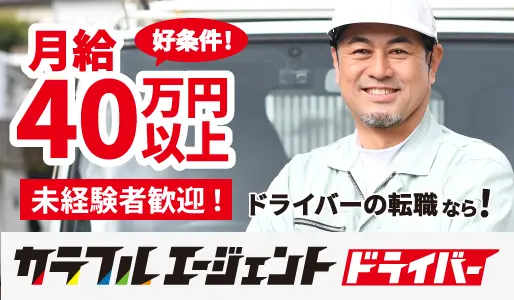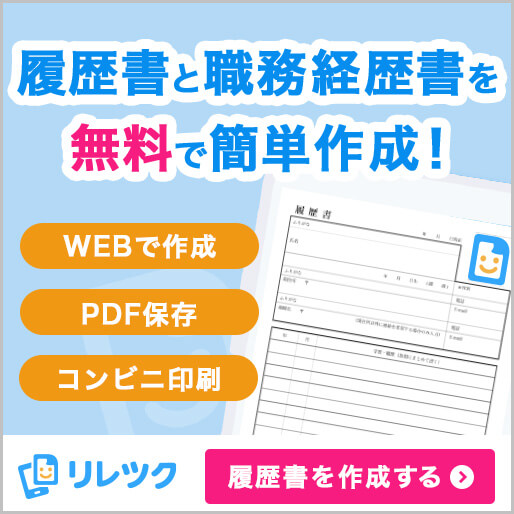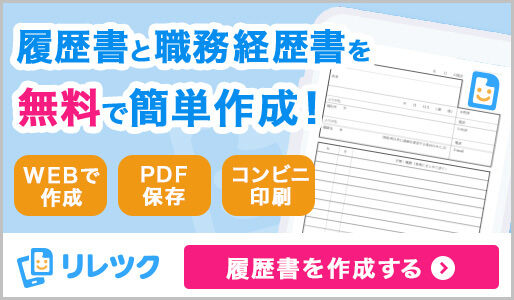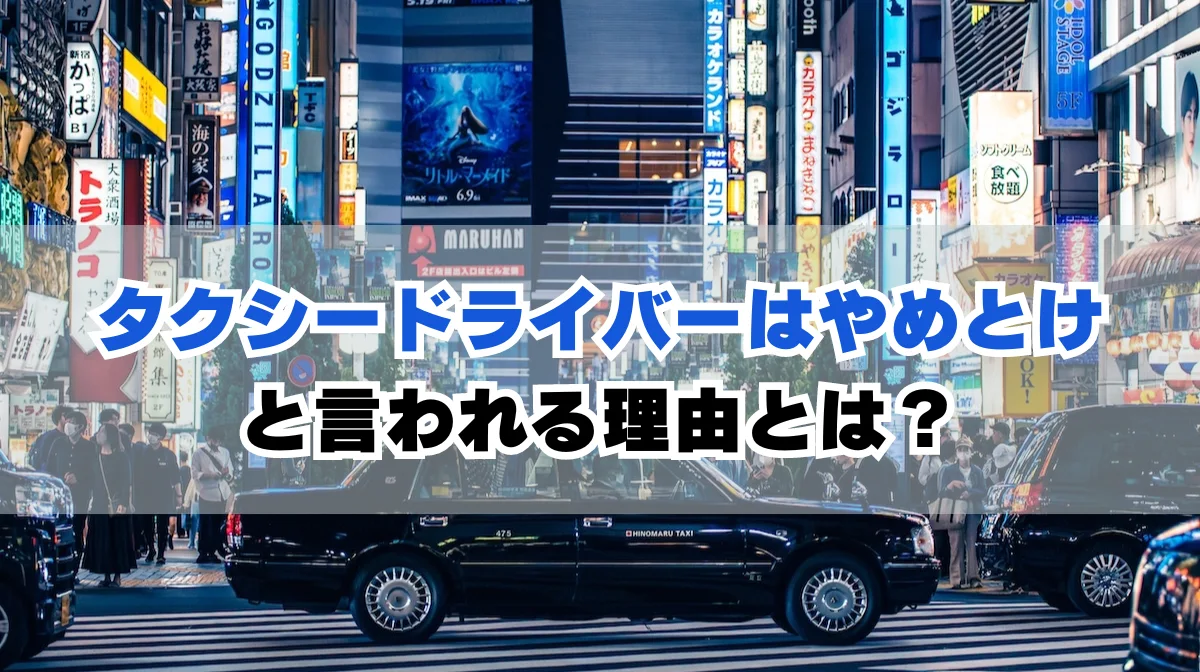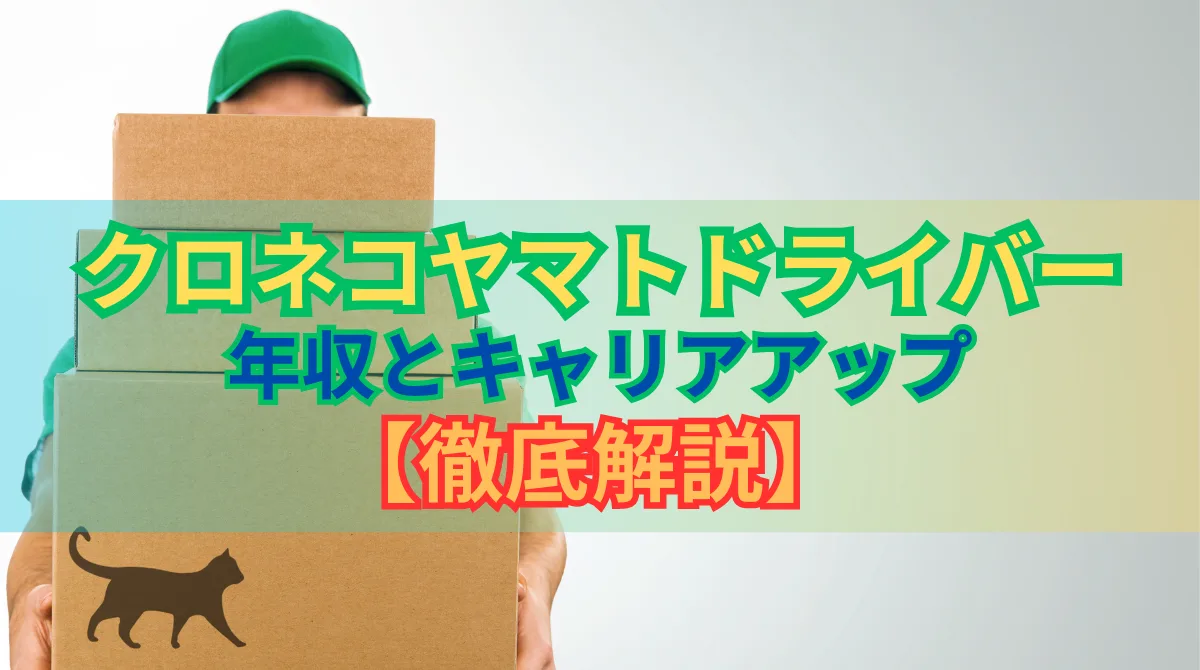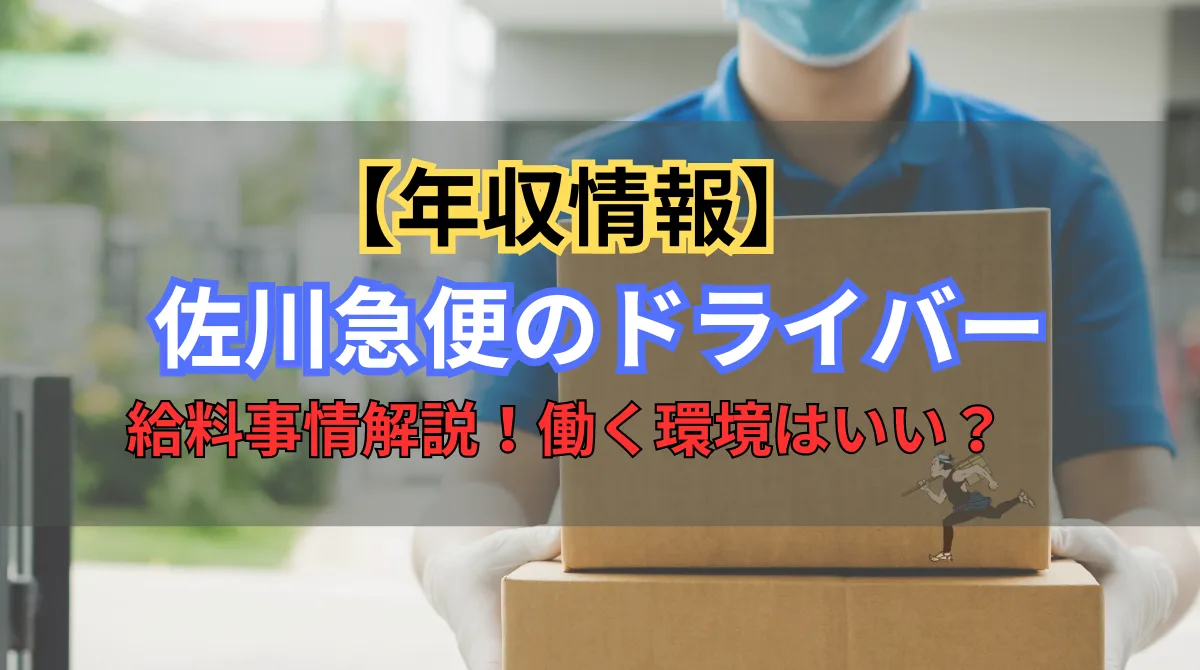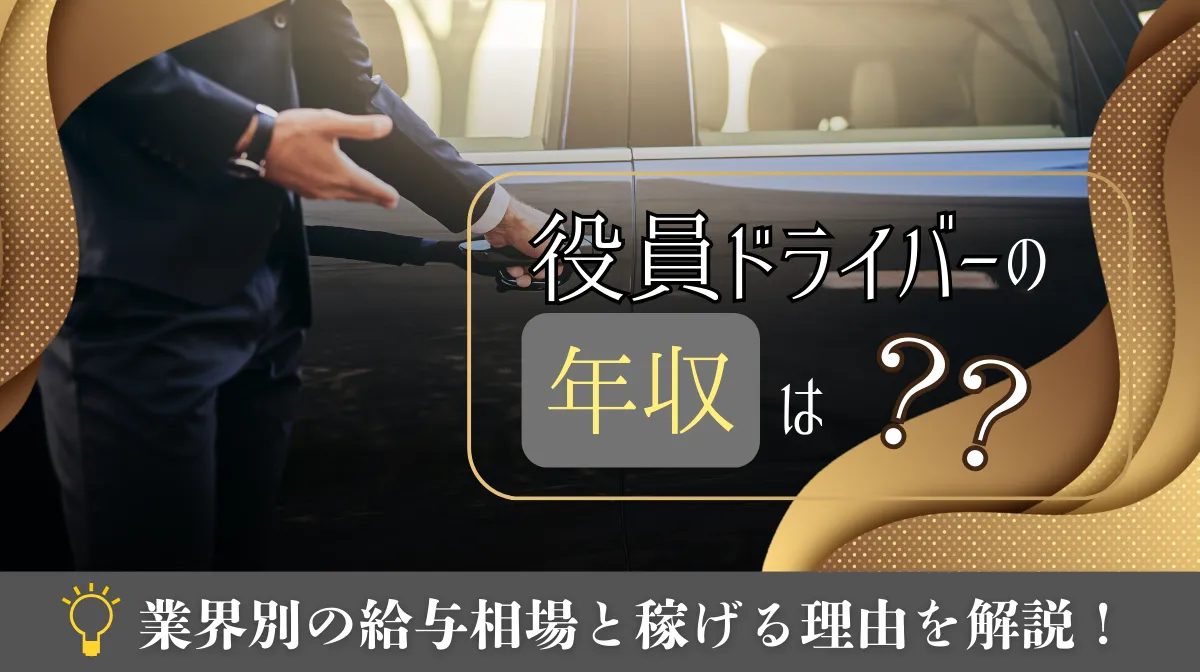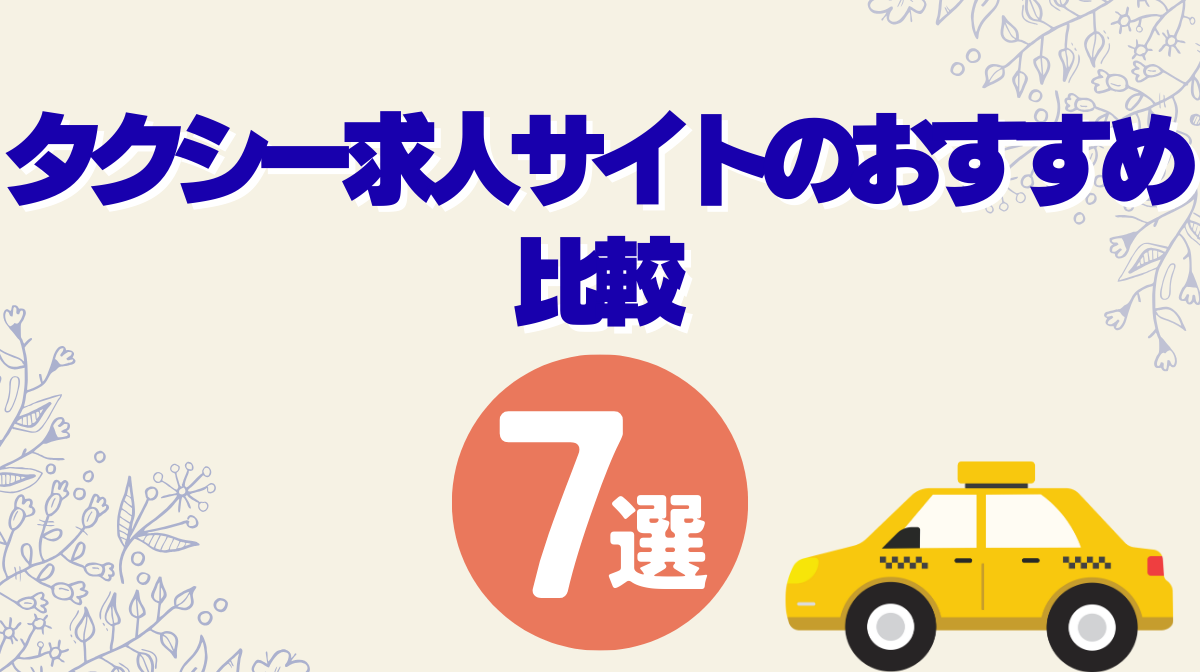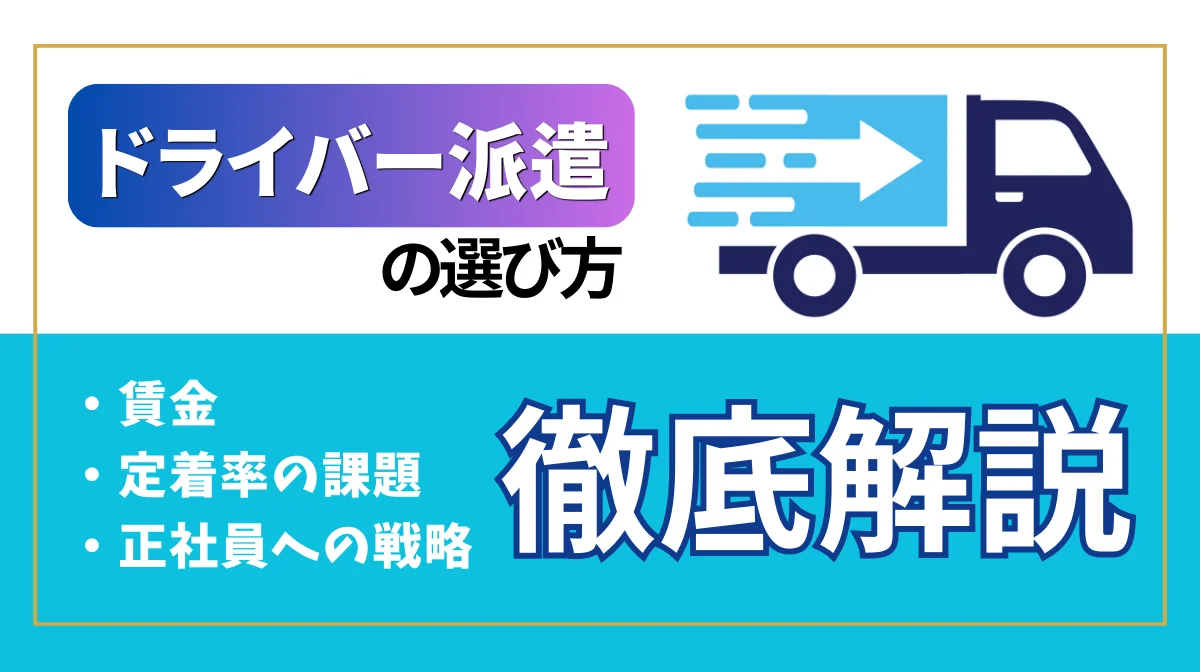かつて「ガソリンを入れる場所」だったガソリンスタンド(SS)は今、電気自動車(EV)普及などの変革期を迎え、カーメンテナンスや車両販売の総合拠点へと進化しています。
この変化の中心にいるのが「自動車整備士」です。
この記事では、ガソリンスタンドで働く整備士の仕事内容、年収、将来性、未経験からの資格取得方法やキャリアパス、向いている人の特徴まで、専門的な視点から詳しく解説します。
・ガソリンスタンドにおける整備士の具体的な仕事内容と、一般スタッフとの違い
・「きつい」と言われる理由、平均年収、そして業界の将来性
・未経験から整備士になるためのステップと、その後のキャリアパス
1.ガソリンスタンドで働く自動車整備士の具体的な仕事内容

ガソリンスタンドにおける整備士の役割は、単なる給油や窓拭きといった一般スタッフの業務とは一線を画します。
専門的な知識と技術を活かし、来店客の車の安全を守る「カーライフのドクター」のような存在です。
一般スタッフ(給油・洗車)との業務範囲の違い
一般スタッフの主な業務は、給油、洗車、タイヤの空気圧チェック、窓拭き、そしてオイルやウォッシャー液などの消耗品販売です。
これらは「接客」が中心となります。
一方、自動車整備士は、これらの業務に加えて、法律で定められた「整備」行為を行います。
具体的には、車の「分解」を伴う作業や、安全に直結する重要な部品の点検・交換を担当します。
主な整備業務(オイル交換、タイヤ、点検)
整備士が行う主な業務には、以下のようなものがあります。
- オイル交換
エンジンオイルやミッションオイルなど、各種オイルの交換。 - タイヤ関連
タイヤの交換(履き替え)、パンク修理、ホイールバランスの調整。 - バッテリー交換
専用の機器を使ったバッテリーの点検・交換。 - 定期点検
法定点検(12ヶ月点検、24ヶ月点検)の実施。 - その他
ブレーキパッド、エアフィルター、ワイパーブレードなどの消耗品交換。
【最重要】働ける職場の違い:「認証工場」「指定工場」とは?
自動車整備士としてガソリンスタンドで働く上で、最も重要な知識が「認証工場」と「指定工場」の違いです。
この違いが、自身の「実務経験」や「キャリア」に直結します。
- 認証工場(分解整備ができる)
地方運輸局長の「認証」を受けた工場です。ブレーキやエンジンといった「分解整備」を行うことができます。ただし、車検ライン(検査機器)は持っていないため、点検・整備が完了した車は、国の車検場(運輸支局)に持ち込んで検査を受ける必要があります。 - 指定工場(車検ができる)
認証工場のうち、さらに厳しい基準(設備、技術、人員)をクリアし、「指定」を受けた工場です。一般に「民間車検場」と呼ばれます。自社内に車検ラインを持っており、整備から検査(車検)までを一貫して行うことができます。

もし整備士として「実務経験」を積み、将来的に「自動車検査員」などのキャリアアップを目指すのであれば、応募先のガソリンスタンドが「認証工場」または「指定工場」の資格を持っているか(併設しているか)を確認してください。
▼あわせて読みたい
認証工場と指定工場の違いについて、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事で整備士にとっての重要性を解説しています。
2.自動車整備士の「きつい」「やめとけ」は本当?

インターネットで検索すると、「ガソリンスタンドの整備士はきつい」「やめとけ」といった言葉を見かけることがあります。
どのような仕事にも大変な側面はありますが、具体的にどのような点が「きつい」と感じられるのでしょうか。
ガソリンスタンド勤務で「きつい」と感じる点
- 体力的な負担
整備作業は、重いタイヤや部品を持ったり、中腰や不自然な姿勢での作業が続いたりすることがあります。また、多くの場合、ピット(作業場)は半屋外であり、夏は暑く、冬は寒い環境での作業となります。 - 接客と営業(ノルマ)のプレッシャー
ガソリンスタンドは「サービス業」の側面が強いため、整備士であっても直接お客様と会話し、車の状態を説明する機会が多くあります。その際、タイヤやバッテリー、車検などの「営業目標(ノルマ)」が設定されている場合があり、整備技術だけでなく営業成績も求められることにプレッシャーを感じる人もいます。 - 業務範囲の広さ
整備の予約が入っていない時間は、給油や洗車、清掃といった一般スタッフの業務を手伝うことがほとんどです。「整備だけを集中してやりたい」と考えていると、ギャップを感じるかもしれません。
それでも「やりがい」を感じる瞬間
もちろん、大変なことばかりではありません。多くの現役整備士が語る「やりがい」もあります。
- お客様からの「ありがとう」
車の不調を的確に診断し、修理・整備した結果、お客様から「調子が良くなったよ、ありがとう」と直接感謝の言葉をもらえることは、何より大きなのやりがいです。 - 技術の向上を実感できる
昨日までできなかった作業が一人でできるようになったり、故障の原因を素早く特定できたりと、自身の「技術=スキル」が日々向上していくことを実感できます。 - 国家資格という専門性
自動車整備士は国家資格です。専門的な知識と技術を身につけ、社会インフラである「自動車」の安全を守るという社会的意義の大きな仕事です。
▼あわせて読みたい
「自動車整備士はやめとけ」という評判の真相や、成功するための戦略について、こちらの記事で詳しく解説しています。
3.ガソリンスタンド整備士の年収と将来性

キャリアを選択する上で、収入と将来性は非常に重要な要素です。ガソリンスタンドで働く整備士の現状を見ていきましょう。
平均年収はいくら? カーディーラー勤務との比較
自動車整備士全体の平均年収は、統計データによると約400万円〜500万円程度で推移しています。
一般的に、ガソリンスタンド勤務の整備士は、カーディーラー勤務の整備士と比較すると、平均年収はやや低くなる傾向があります。
これは、ディーラーが特定メーカーの高度な専門知識を要する整備やリコール対応を行うのに対し、ガソリンスタンドは幅広いメーカーの基本的な点検・整備が中心となるためです。
ただし、ガソリンスタンドでも「指定工場」の運営母体が大手企業であったり、「自動車検査員」の資格手当が付いたりすることで、ディーラー勤務と遜色ない給与水準となるケースも増えています。
▼あわせて読みたい
自動車整備士の年収について、業種別・年代別の詳細データや年収アップの方法を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
自動車整備士の需要(有効求人倍率)
自動車整備士の需要は、極めて高い水準にあります。
国土交通省の調査などによると、自動車整備士の有効求人倍率は「5倍」を超えることも珍しくありません。これは、求職者1人に対して5件以上の求人があるという「圧倒的な売り手市場」を意味します。
技術の進歩(ハイブリッド車、EV、自動運転支援)により、整備士に求められる知識は高度化しており、専門知識を持った人材は常に不足しているのです。
【業界分析】SS減少でも整備士の重要性が増す理由
前述の通り、SS(サービスステーション)の「数」は減少しています。しかし、これは業界の衰退を意味しません。
従来の「給油」ビジネスから、EV充電、カーシェアリング、そして「整備・メンテナンス」といった、車の安全を守るビジネスへと事業の中核が移行しているのです。
車がどれだけ進化しても、タイヤの摩耗、ブレーキの点検、車体の安全確認は必要不可欠です。
SSが「総合モビリティ・サービスハブ」へと進化する中で、専門知識を持った整備士の存在価値は、むしろ高まっていると言えます。
■ガソリンスタンド整備士も派遣で働ける
ガソリンスタンドでの整備士経験を活かして、さらに高収入を目指すなら派遣という選択肢もあります。カラフルスタッフィング メカニックでは、ガソリンスタンドでの整備経験者を歓迎しています。専門のコーディネーターが、あなたの経験やスキルに合った、より条件の良い職場をご提案します。派遣なら、大手ディーラーや指定工場での勤務も可能で、年収アップとキャリアアップを同時に実現できます。
▼カラフルスタッフィング メカニックへのお問い合わせはこちら
4.未経験・無資格から整備士になるためのステップ

自動車整備士は専門職ですが、多くのガソリンスタンドでは未経験・無資格からスタートできる求人を用意しています。
ガソリンスタンドで「実務経験」は積める?
実務経験は積むことはできます。ただし、前述の「認証工場」または「指定工場」であることが条件です。
自動車整備士の国家試験(2級・3級)を受験するには、原則として「実務経験」が必要です。
無資格で入社した場合、まずは整備補助として働きながら、この実務経験の年数をクリアすることが最初の目標となります。
活用したい「資格取得支援制度」
多くの企業(ガソリンスタンド運営会社)では、人材確保のために「資格取得支援制度」を設けています。
これは、整備士資格を取得するための専門学校の学費(夜間や通信教育など)や、受験費用を会社が負担してくれる制度です。
未経験から整備士を目指す場合、この制度が充実している会社を選ぶことは、金銭的な負担を減らし、キャリアアップを加速させるための有効な選択肢の一つです。
必要な資格の種類(3級・2級)
自動車整備士の資格は、主に3級、2級、1級、特殊に分かれています。
- 3級自動車整備士
基本的な整備(オイル交換、タイヤ交換など)ができる資格です。まずはここを目指します。 - 2級自動車整備士
整備士として働く上で、事実上の「標準資格」です。3級よりも高度な整備(分解整備など)ができ、ほとんどの整備工場で求められます。ガソリンスタンドで実務経験を積みながら、この2級取得を目指すのが王道のキャリアパスです。
▼あわせて読みたい
3級自動車整備士の資格について、試験内容や合格率、取得方法を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
■未経験から整備士を目指すなら派遣もおすすめ
未経験から整備士を目指す方には、派遣でスタートするという方法もあります。カラフルスタッフィング メカニックなら、資格取得支援制度のある職場や、未経験者を丁寧に育成してくれる認証工場・指定工場の求人を多数ご紹介できます。専門コーディネーターが、あなたのキャリアプランに合わせて最適な職場を見つけ、実務経験を積みながら資格取得を目指せる環境をサポートします。
▼カラフルスタッフィング メカニックへのお問い合わせはこちら
5.ガソリンスタンドからのキャリアパス

ガソリンスタンドでの経験は、その後の多様なキャリアにつながる貴重な第一歩です。
資格を取得し、管理職(自動車検査員など)へ
2級整備士資格を取得し、さらに実務経験を積むと、「自動車検査員」の資格に挑戦できます。
これは、指定工場(民間車検場)で、車検の最終的な「検査(合否判定)」を行うことができる非常に重要な国家資格です。
検査員になれば、整備士のリーダーや工場長といった管理職への道が開け、大幅な待遇改善が期待できます。
経験を活かしてディーラーや専門工場へ転職
ガソリンスタンドでは、特定のメーカーに偏らず、国内外の多種多様な車種に触れる機会があります。
ここで培った幅広い整備経験と2級整備士資格を武器に、より専門性の高いカーディーラーや、特定の車種・分野(例:輸入車専門、チューニングショップなど)に特化した整備工場へ転職し、キャリアアップを図ることも可能です。
独立・開業の道
整備士としての技術と経験、そして自動車検査員などの資格を活かし、最終的に自分自身の整備工場(認証工場や指定工場)を持って独立・開業するという道もあります。
▼あわせて読みたい
ガソリンスタンドでの経験を活かして転職を考えている方には、自動車整備士におすすめの転職サイトをこちらで紹介しています。
■派遣でキャリアの選択肢を広げる
ガソリンスタンドで培った経験を活かして、次のステップへ進みたいとお考えなら、派遣という働き方が最適です。カラフルスタッフィング メカニックでは、ディーラー、専門工場、大手チェーン店など、様々な職場の求人をご用意しています。派遣なら、複数の職場を経験することで、自分に最適なキャリアパスを見つけることができます。検査員や工場長を目指す方にも、最適な環境をご紹介します。
▼カラフルスタッフィング メカニックへのお問い合わせはこちら
6.ガソリンスタンドの整備士に向いている人の特徴
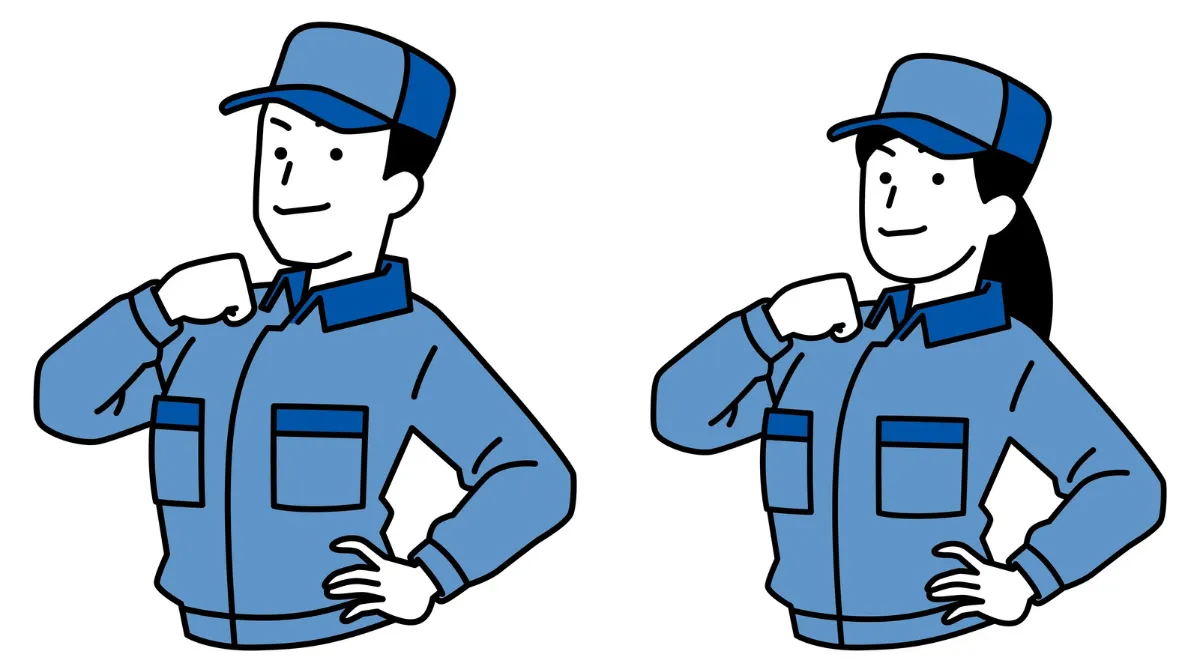
最後に、どのような人がガソリンスタンドの整備士に向いているか、その特徴をまとめます。
- 車が好きで、機械いじりが好きな人
大前提として、車の構造や仕組みに興味を持てることは非常に重要です。 - 人とコミュニケーションを取ることが苦ではない人
ディーラーや専業工場と比べ、お客様と直接話す機会が多いため、整備内容を分かりやすく説明したり、お客様の不安を取り除いたりする対話力が求められます。 - コツコツとした地道な努力ができる人
整備は安全に直結するため、小さなミスも見逃せない地道な確認作業の連続です。また、資格取得のためには、仕事後に勉強する努力も必要です。 - 新しい技術の学習に意欲的な人
EVやハイブリッド技術など、自動車の技術は日進月歩です。常に新しい知識を学ぶことに前向きな姿勢が求められます。
7.ガソリンスタンドは整備士キャリアの最適な「入り口」
ガソリンスタンドは、単なる給油所から、地域の「総合モビリティ・サービスハブ」へと進化を遂げています。
そこで働く整備士の仕事は、体力的な厳しさや営業の側面もありますが、それを上回る「専門性」「高い需要(将来性)」「お客様からの感謝」という大きなやりがいがあります。
特に、未経験・無資格から自動車整備士という国家資格キャリアを目指す人にとって、「資格取得支援制度」を活用しながら「実務経験」を積めるガソリンスタンドは、有効な選択肢の一つです。
この記事が、自動車整備士としてのキャリアを考える上で、一つの選択肢に上がると嬉しいです。