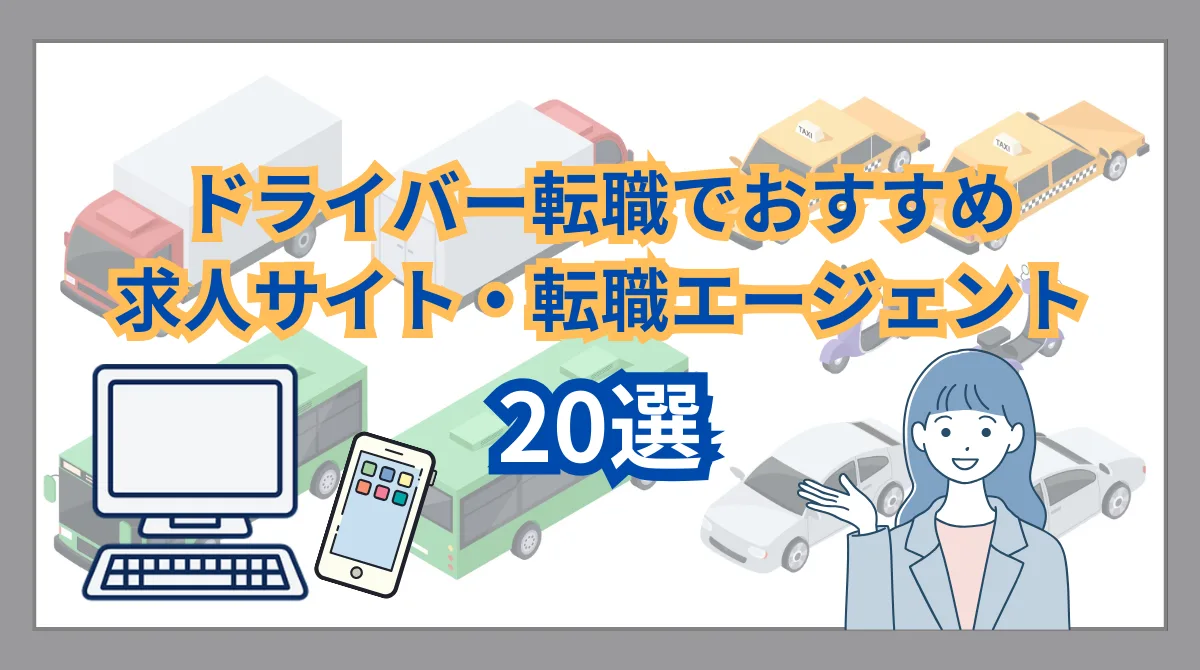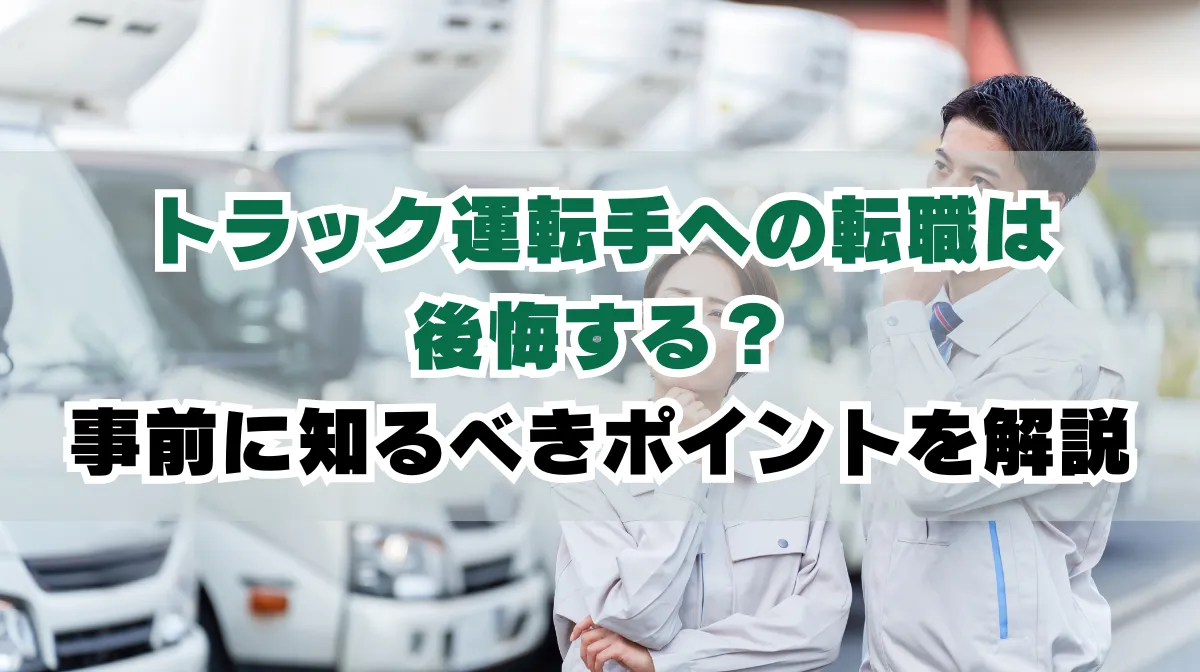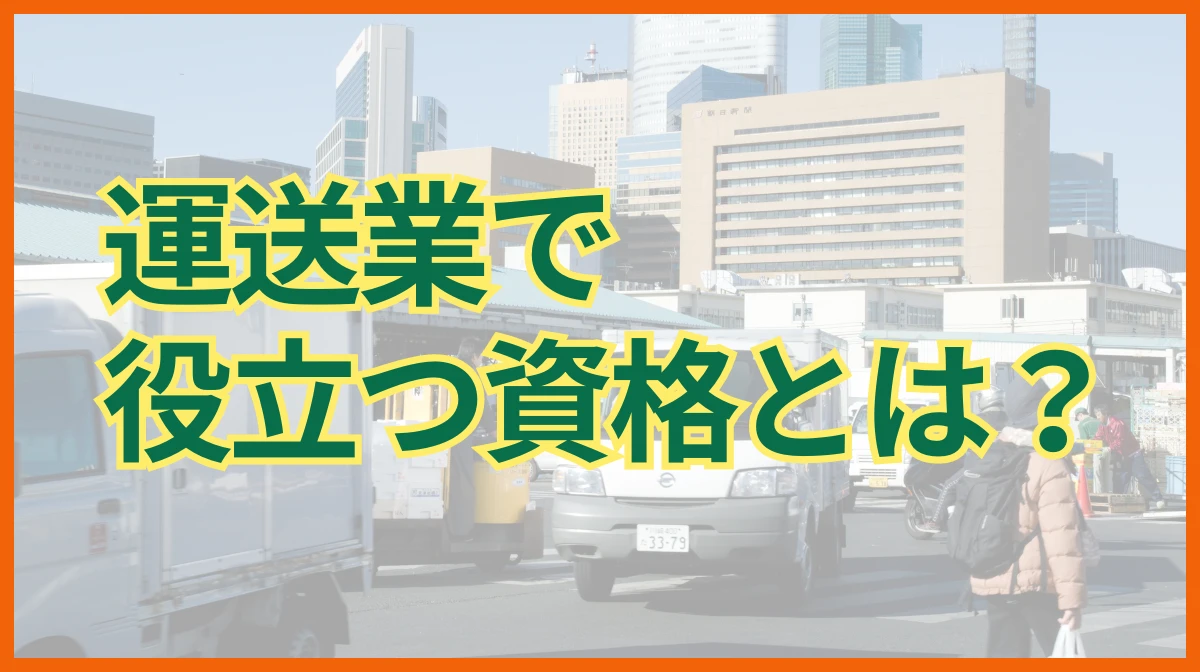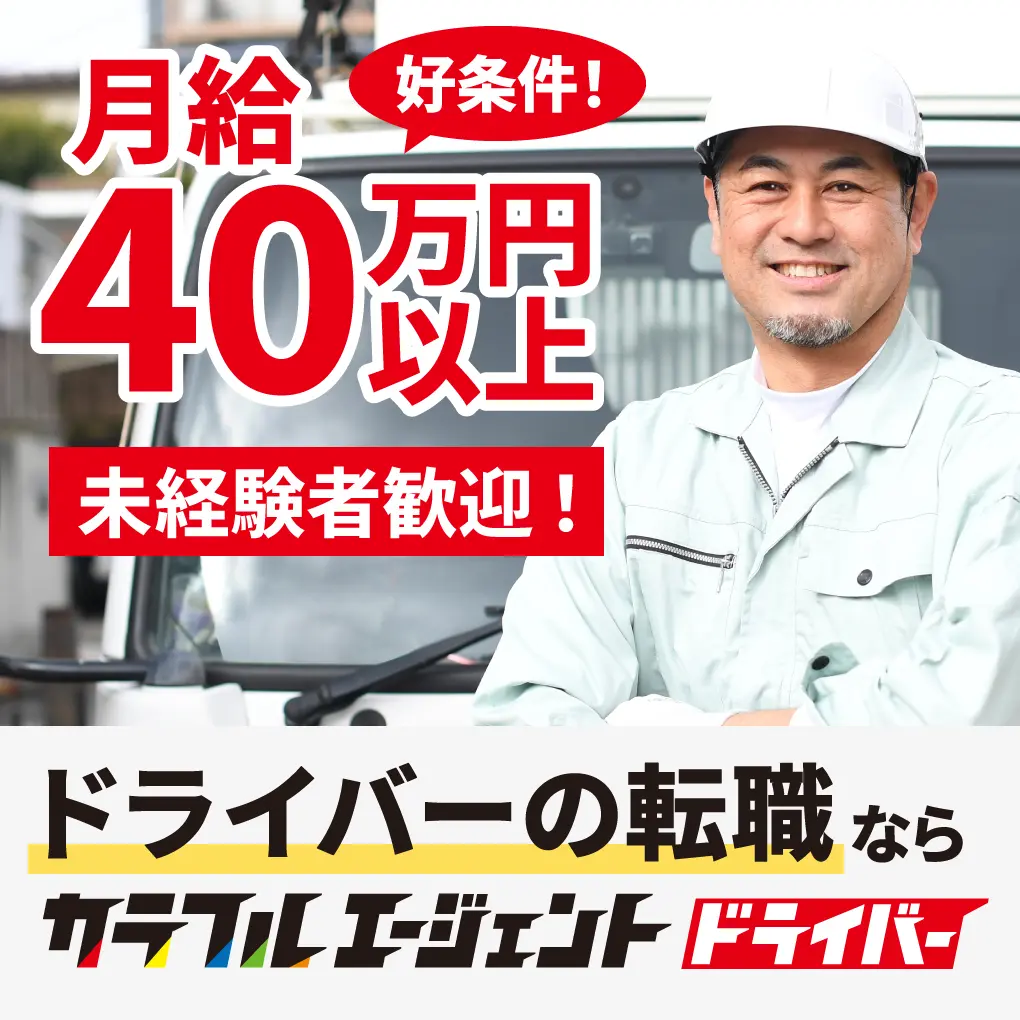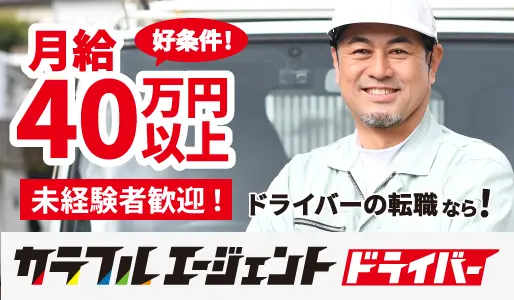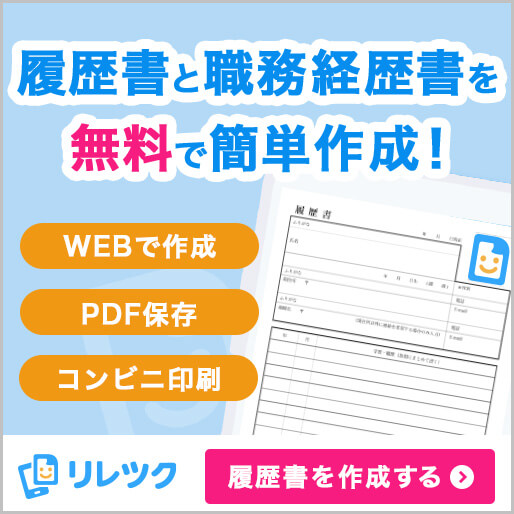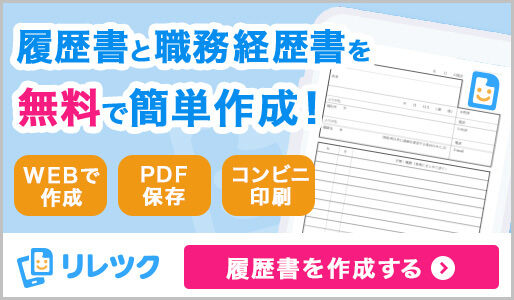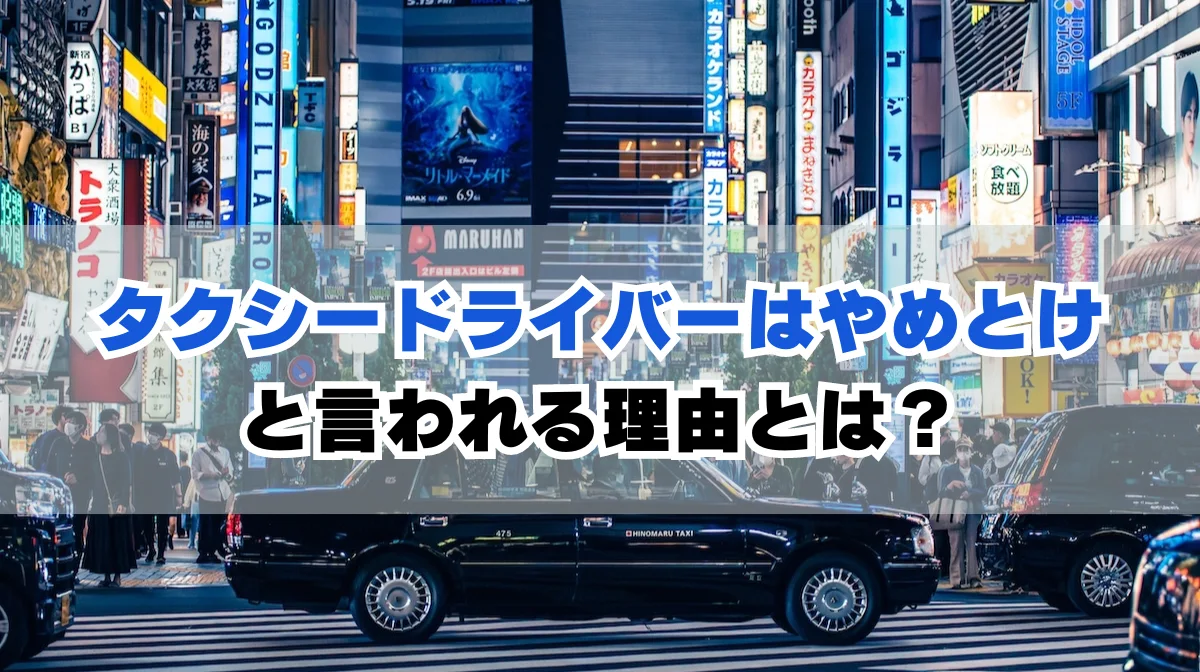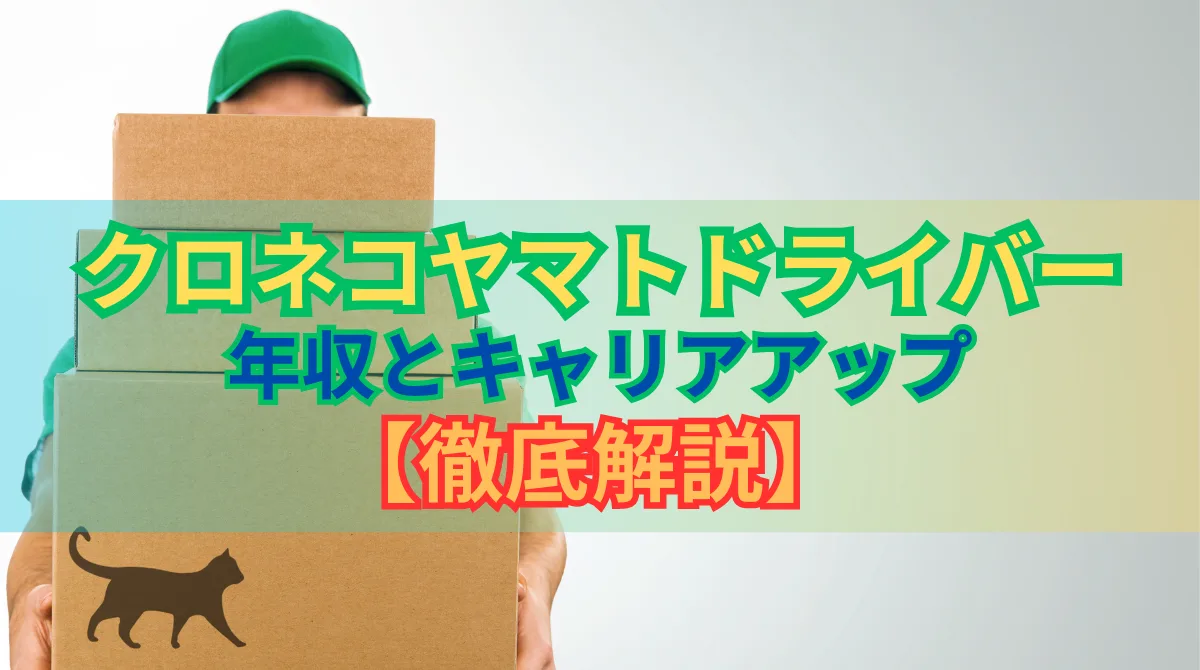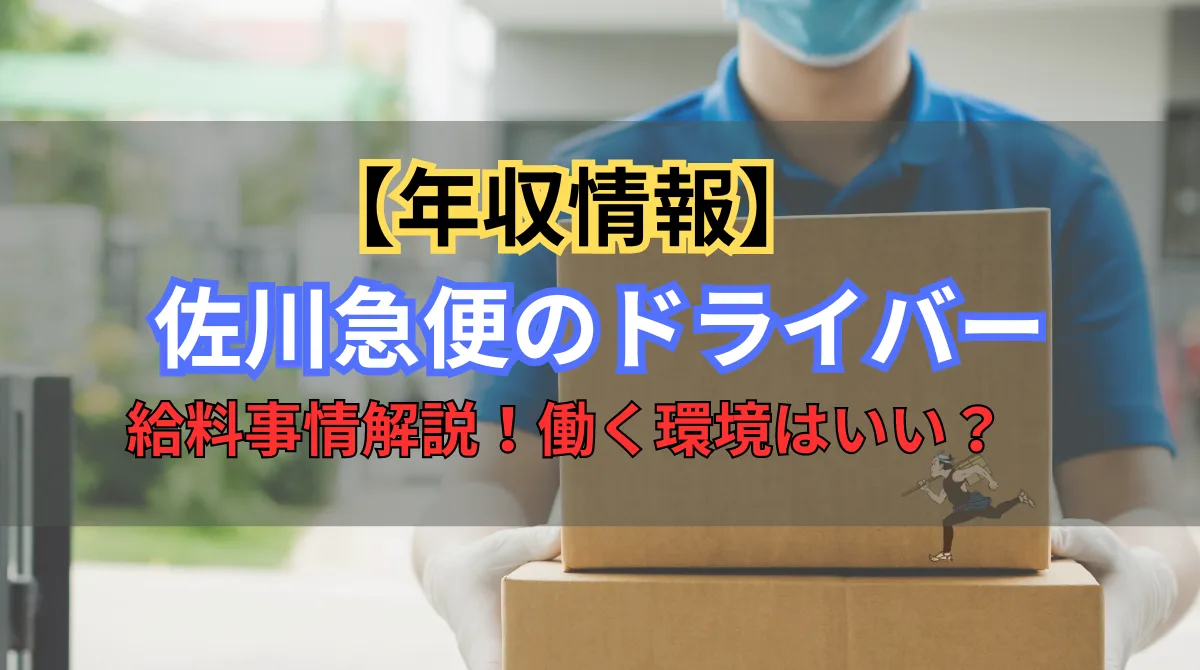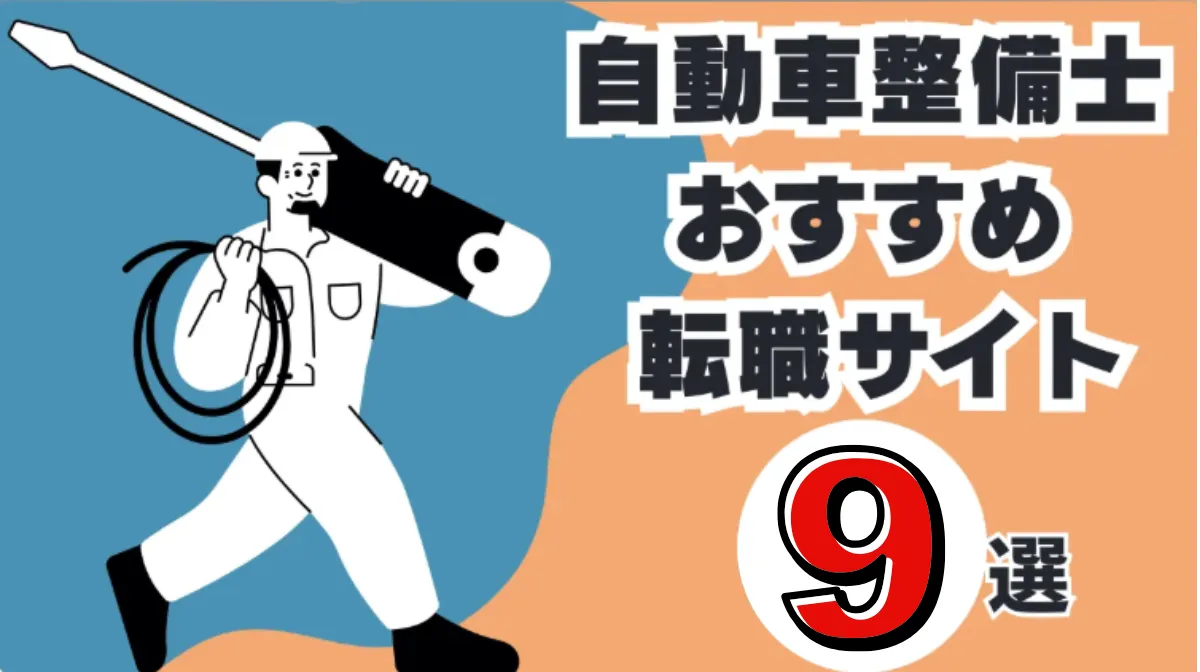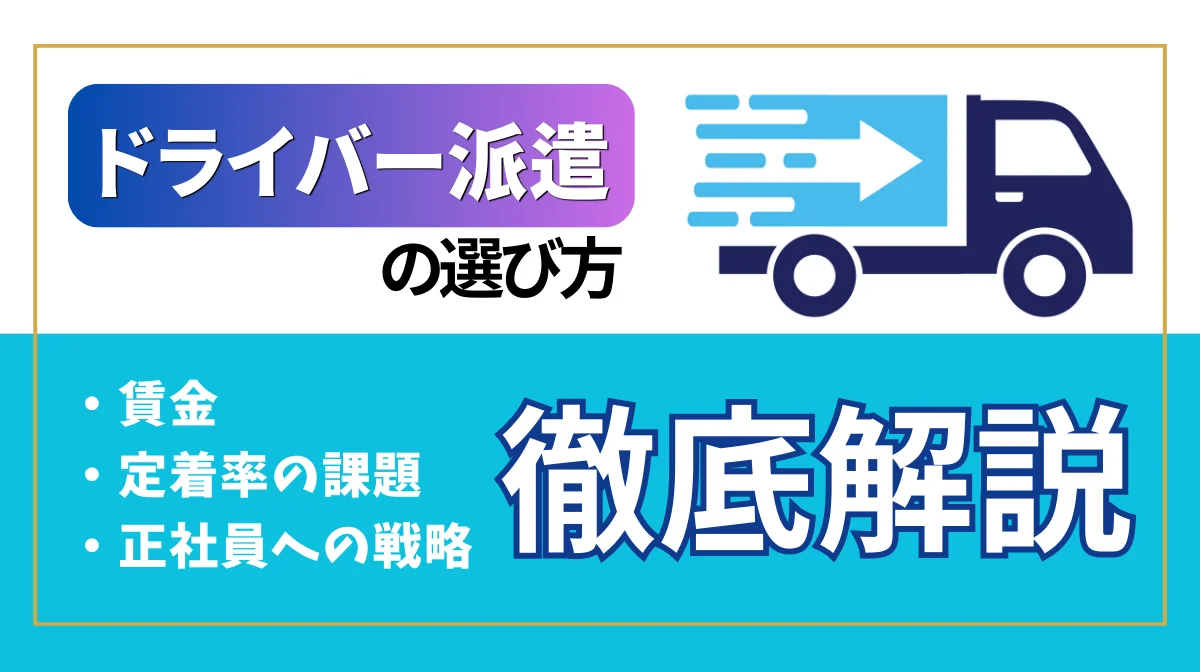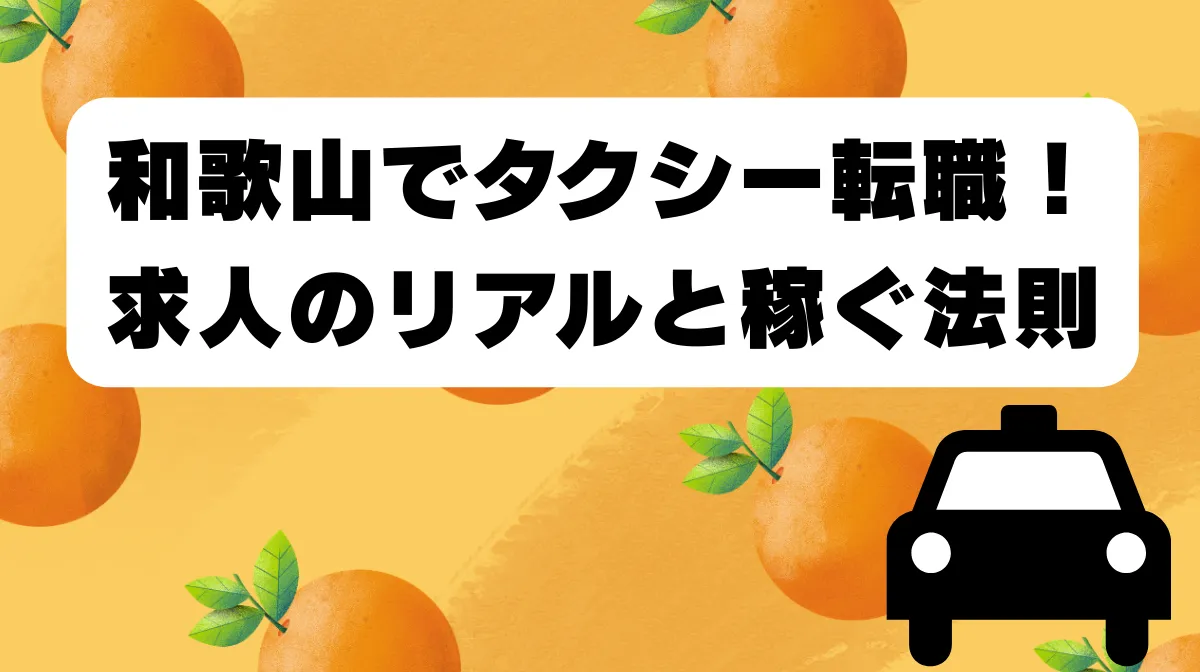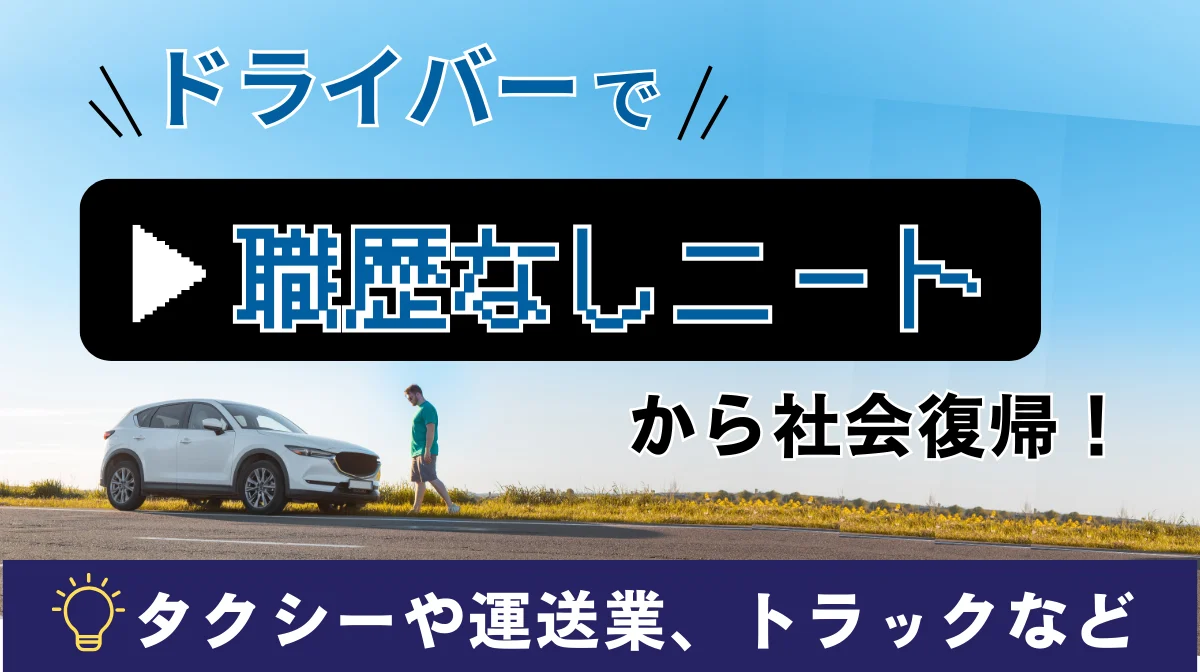トラック運送業で働いてみたいと考えているものの、「運送会社がどんな仕事をしている会社なのか、実はよく知らない」「運送会社と物流会社の違いがわからない」といった方は少なくないはずです。
本記事では、運送会社と物流会社の概要、両者の役割の違い、さらには「配送」「運輸」「輸送」の違いについてわかりやすく解説します。
物流・運送業界が直面している「2024年問題」によって、業界の転職市場がどのような動きを見せているのかもご紹介します。
- 運送会社と物流会社の概要や役割と違いについて
- 「配送」「運輸」「輸送」の概要や役割と、運送との違いについて
- 運送業界が直面している課題や将来性について
1.運送会社とは?

少し難しくいえば、運送会社とは、貨物自動車運送事業法で定められた「一般貨物自動車運送事業」を営む企業のことです。
運輸支局へ申請書を提出すると、国土交通省または地方運輸局で審査がおこなわれ、許可が下りると、晴れて事業=運送会社を開始できるようになります。
噛み砕いてお伝えすると、運送会社の「運送」とは、トラックなどの車両を使用して商品などのモノを運ぶことです。
依頼元(荷送人)が依頼した荷物を運んで、送り先まで無事に届ける業務をおこなっている企業が運送会社です。
主にトラックなどの大型車両を使って送り先に荷物を運ぶ会社であり、航空機や船で荷物を運ぶ企業を運送会社とはいいません。
同様に、車両を使ったとしても、人を運ぶ業務をおこなっている企業を運送会社と呼ぶことはありません。運ぶ手段=車両、運ぶ対象=モノの組み合わせで業務をおこなっている企業が運送会社です。
運送会社は、特定送料や手数料などを対価として受け取る代わりに、工場や物流センターなどから依頼された商品や材料などを企業や店舗、個人宅などへ届けたり、個人や企業から荷物を預かって送り先まで届けたりするサービスを提供しています。
運送会社の提供するサービスとしては、宅配便がおそらく身近で最もよく見かけるものですが、運送会社の運ぶモノはさまざまで、あるモノに特化して運ぶ運送会社もあります。
例えば、大型の建築資材や精密機械、生鮮食品などを専門にしている運送会社があります。雑貨や食品などの小口荷物を運んでいるのが、上述した宅配便です。
このように、運送会社にはさまざまな種類・専門分野があります。
運送する対象が異なれば、運ぶ手段である車両の種類も異なってきます。大型の車両、荷台の振動を抑える専用車両、冷蔵機能がついた車両など、運送対象に適した車両が使用されます。
例えばトラックひとつとっても、車両のサイズ、総重量、最大積載量によって大型・中型・小型の3種類に分類され、ドライバーが保有している免許によって運転できるトラックの最大積載量も規定されています。
最も多くの人がもっている普通自動車免許でも、総重量3.5トン未満、定員10人以下、最大積載量2トン未満のトラックであれば、運転できます。
使用する車種やエリア、事業所の所在地などは運送会社ごとに異なり、ドライバーの業務も異なってきます。フードデリバリーも軽自動車などでおこなう場合には運送業の許可が必要であり、運送業に含まれます。
2.物流会社とは?

「物流」という言葉に馴染んでいますが、実は物的流通を略したワードになります。
英語ではPhysical distributionといい、企業が商品を製造してから消費者に届けるまでの搬入、在庫管理、加工、梱包、出荷作業、情報管理などの一連の工程を指します。
物流会社では、工場やメーカーなどの製造元から倉庫などに商品を搬入して、倉庫の在庫を管理し、消費者に出荷する際には梱包や出荷、配送など、さまざまな業務をおこなっています。大きく分けると物流は、
- 輸送・配送
- 保管
- 包装
- 荷役
- 流通加工
の五大機能から成り立っていますが、最近はこれに加えて、
- 情報管理
もおこなっている物流会社が数多くあります。
以下に、それぞれの機能の詳細について紹介してきます。
輸送・配送
輸送・配送(輸配送)の輸送は、航空機や船、トラックなどで長距離を運ぶことを意味します。
工場から物流センターや倉庫などに向けて商品を長い距離、運び届けるケースは輸送に該当します。
一方、中距離の(複数の)場所に商品を届けるのが配送です。配送には、物流センターや倉庫から店舗や個人の自宅などに届けることもあります。
保管
製造された商品を一定期間、保管する機能です。
保管時には、品質の低下を防ぐため、製造年月日、適切な温度、湿度などに配慮しなければなりません。商品の品質を維持するだけでなく、発送のタイミングを考慮した在庫数調整などもおこないます。
包装
商品の発送の際に、商品を汚れや衝撃から守り、安全に消費者に届けるため、もしくは商品を装飾して価値を高めるためにおこないます。
荷役
商品の入庫から出庫まで、商品の移動に関する作業全般が荷役機能です。
荷役には、トラックなどへの商品の積み込み、荷下ろしのほか、倉庫内での商品の運搬、入出庫、仕分け、棚入れ、ピッキングや荷揃えなど、幅広い作業が含まれます。
流通加工
出荷時に、商品の価値を高めるためにおこなう加工作業のことです。
ラッピングやタグ・ラベル貼り、洗浄、詰め合わせなど、商品ごとにそれぞれ異なる作業をおこないます。
情報管理
情報管理は、商品が消費者のもとに届くまでの情報管理についてシステムを利用しておこない、物流の効率化を図ります。
拠点ごとの在庫状況や、発注を受けた商品の現在の配送状況、商品の品質などをシステム上で一元管理し、共有します。
3.運送会社と物流会社の役割の違い
運送会社と物流会社とでは、目的が異なります。
運送会社は運び方はさまざまであるもののモノを運ぶことに特化しており、依頼された荷物を効率よく、かつ安全に荷受人のもとに運ぶことを目的としています。
一方、物流会社では、先述したように輸送・配送から情報管理まで、幅広い物流業務のすべてを担っており、効率的な物流システムを構築することによって、荷主の利益拡大に貢献することが目的です。
両者の業務領域が大きく異なっているため、求められる役割も自ずと異なってきます。
業務領域で見れば、物流会社が担っている業務の一部(モノの配送・輸送)を専門におこなっているのが運送会社とも考えられます。
4.運送と配送、運輸、輸送との違い

「運送」「配送」「運輸」「輸送」は、いずれも何かを運ぶときに使われる言葉です。まったく同じ意味の言葉でないことはわかりますが、何が違うのでしょうか。
これらは、運ぶ対象や量、発送元・発送先が異なっており、以下にて説明していきます。
運送:トラックで荷物を運ぶこと
運送とは、おもにトラックや自動車などで荷物を運ぶことです。工場や物流センター、倉庫などから荷物を出荷して、中距離から長距離の発送先まで届ける業務を運送と呼びます。
配送:近距離で荷物を運ぶこと
配送とは、荷物を長距離先まで運ぶのではなく、近距離の発送先に届けることです。
物流センターや倉庫などから、近距離のスーパーといった店舗、消費者など複数の場所に荷物を届ける業務を意味し、「二次輸送」とも呼ばれます。
宅配便で見かけるように、小型のトラックや軽自動車などが多く使用されます。近年では、バイクや自転車を使用したフードデリバリーサービスなどの配送も増加しています。
運輸:人や荷物を運ぶこと
運輸が運ぶ対象には荷物だけでなく人も含まれ、しかも配送とは異なり、一度に大量に運びます。
おもにトラックで荷物を運ぶのが運送なら、船や航空機、電車、バスなどで人や荷物を運ぶことが運輸です。運輸には、積み込みや荷下ろし、仕分け、保管、流通加工などの業務も含まれます。
輸送:海外などから長距離で大量の荷物を運ぶこと
輸送は大量の荷物を長い距離、運ぶ業務であり、配送の前段階を担います。
そのため「一次輸送」と呼ばれることもあります。例えば、海外から日本の拠点に大量の荷物を運ぶ場合や、工場から物流センターに大量の荷物を運ぶ場合などが輸送です。
輸送にはトラックを使用する陸送、航空機を使用する空送、船を使用する船送などがあります。運送は輸送に内包される概念です。
5.運送業界が抱える課題

現在、運送業界が抱えている課題としてよく知られているのが、
- ドライバーの不足
- ドライバーの高齢化
- 2024年問題(残業時間の上限規制)
- 燃料費の高騰
などです。
ドライバーの不足
ネットショッピングや通販での商品購入が普及した現在では、購入された商品の配送件数は拡大する一方です。
公益社団法人日本トラック協会が発表した「日本のトラック輸送産業 現状と課題 2022」によれば、道路貨物運送業の就業者数は2010年が181万人だったのに対して、2021年は199万人と増加傾向にはあるものの、伸び率は9.94%にすぎません。
一方、国内のBtoC EC市場の規模は2013年が5兆9,931億円だったのに対して、2021年には13兆2,865円で121.69%増。
宅配便取扱実績では、2011年が34億96万個だったのに対して、2021年には48億3,647万個と、42.20%増であり、配送個数の増加に対してドライバー数の増加が追いついていません。
IT活用等による業務効率化で補える部分はあるとはいえ、明らかにドライバー不足であることがわかります。
また、消費者への配送では、
- 荷物の再配達が多い
- トラックに荷物を積み込むまでの荷待ち時間がある
といった問題もあります。ドライバー不足により、一人のドライバーにかかる業務負担が大きくなっています。
参照:
我が国の物流を取り巻く現状と取組状況
国交省発表による2020年の宅配個数と10年間の推移 再配達が課題|ECzine(イーシージン)
ドライバーの高齢化
同じく「日本のトラック輸送産業現状と課題 2022」には「道路貨物運送業 年齢階級別就業者構成比」が掲載されており、2010年から2022年までにドライバーの高齢化が進んでいることがわかります。
2010年には就業者数のうち30代以下が約40%、40代は約28%、50代が約20%、60代が約14%でしたが、2022年には30代以下の従業員は全体の約23%に減少しています。
40代は約29%とあまり変わりませんが、50代は約28%、60代以上の従業員は約18%に増加しています。
運送業界では、人材不足による従業員の負担が問題になり、若年層の離職が続いたことなどが原因です。
運送業界は今後も市場の拡大が見込まれるため、ドライバーの労働環境改善などによって人材を確保する取り組みを進める必要があります。
2024年問題(残業時間の上限規制)
働き方改革関連法によって、2024年4月からは運送業界の時間外労働の上限が年間960時間に規制されました。
上限規制は2019年から設けられていましたが、あわせて5年間の猶予期間も設定されていました。この猶予期間が2024年3月で終了し、規制が適用されるようになりました。
その結果、ドライバーの実労働時間が減少し、長距離運送などの業務がこれまでのスケジュール通りにおこなえなくなってきている状況も出はじめています。
従来は、多くのドライバーが960時間を超えて残業していたため、残業時間の減少による給与の低下も懸念されています。
960時間を超えてドライバーに残業させた場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が事業者に科されることがあります。
荷待ち時間を削減し、効率的な運送業務を実現するシステムの導入などが求められています。
【2024年問題に関する詳細が知りたい方はこちら】
燃料費の高騰
世界的は燃料価格の上昇は運送業界にも大きな打撃を与えています。
新型コロナウイルス感染拡大などが原因で、多くのトラックが燃料としている軽油の価格は2022年にいったん下落したものの、その後は再び、高騰が進んでいます。
こうした状況を受け、燃料価格の上昇によって生じるコストを別料金で受け取る「燃料サーチャージ」の導入を進める運送事業者が増加しています。再配達時に追加料金を徴収する可能性もあります。
料金変更による利用者離れを防ぐためにも、サービスを向上させる取り組みは喫緊の課題です。
6.今後も運送業界の需要は高まっていく
運送業界は、通信販売やネットショッピングの利用者増加などにより、今後も市場の拡大が見込まれています。
労働環境の改善はまだ多くの余地があるものの、将来性のある魅力的な業界であるといえるでしょう。
工場や物流センターなどから商品を企業、個人宅などに届けるサービスを提供するのが運送会社の現在の役割ですが、現状だけでなく、将来も鑑みたうえでキャリアを検討していくとよいでしょう。