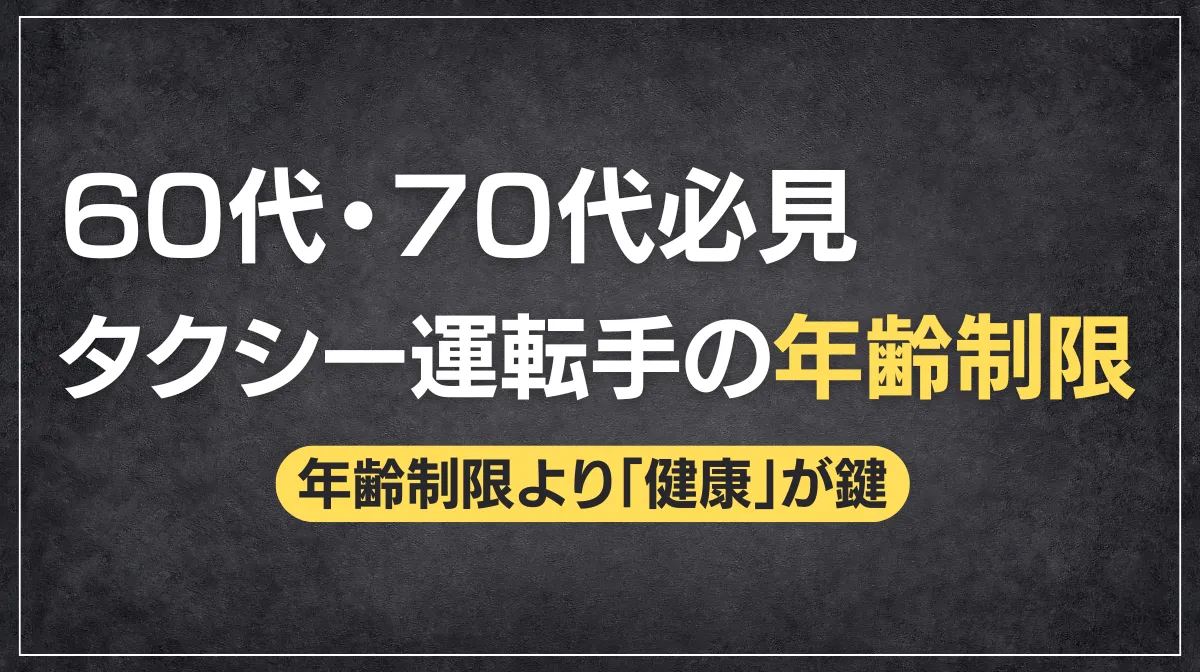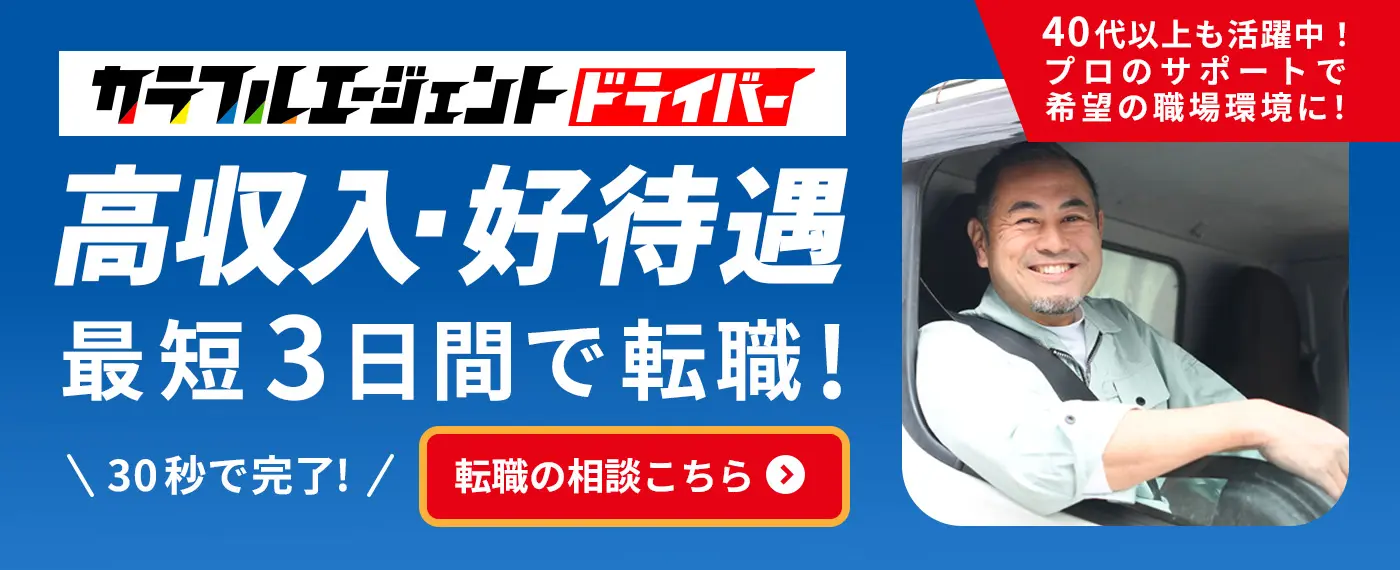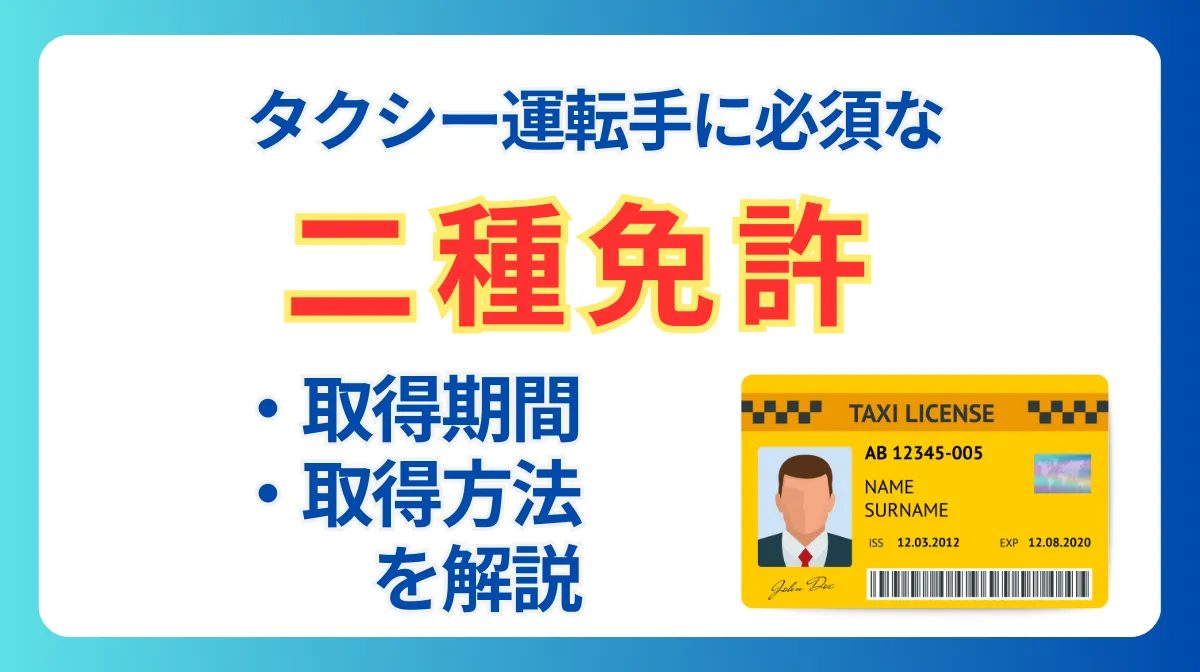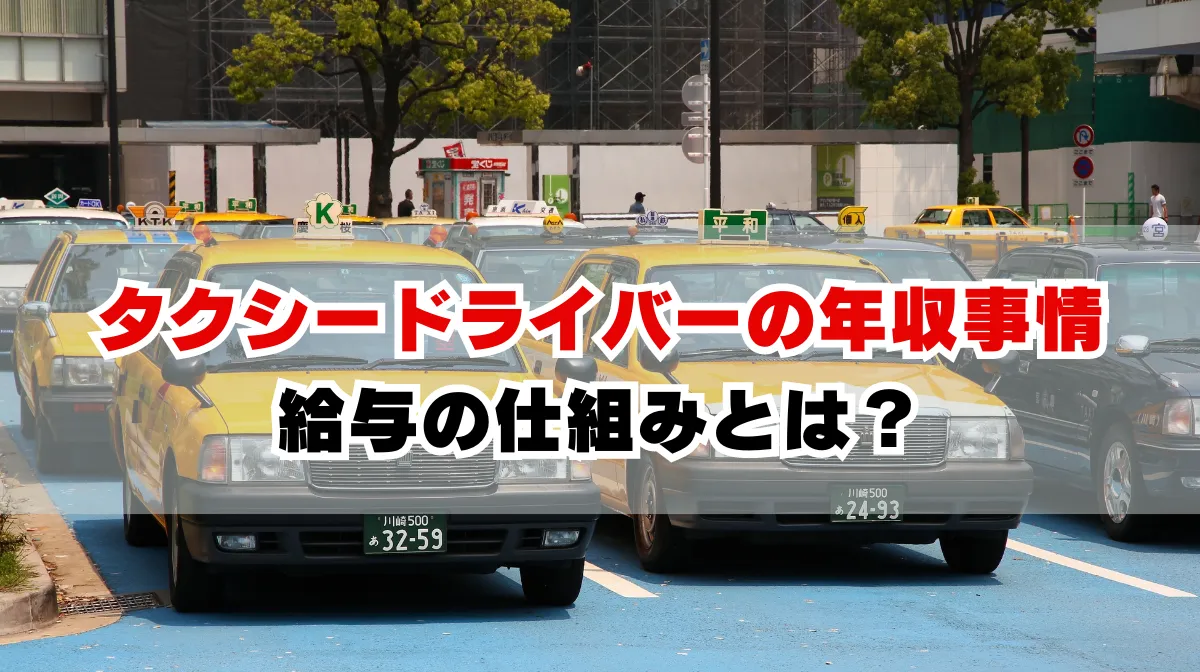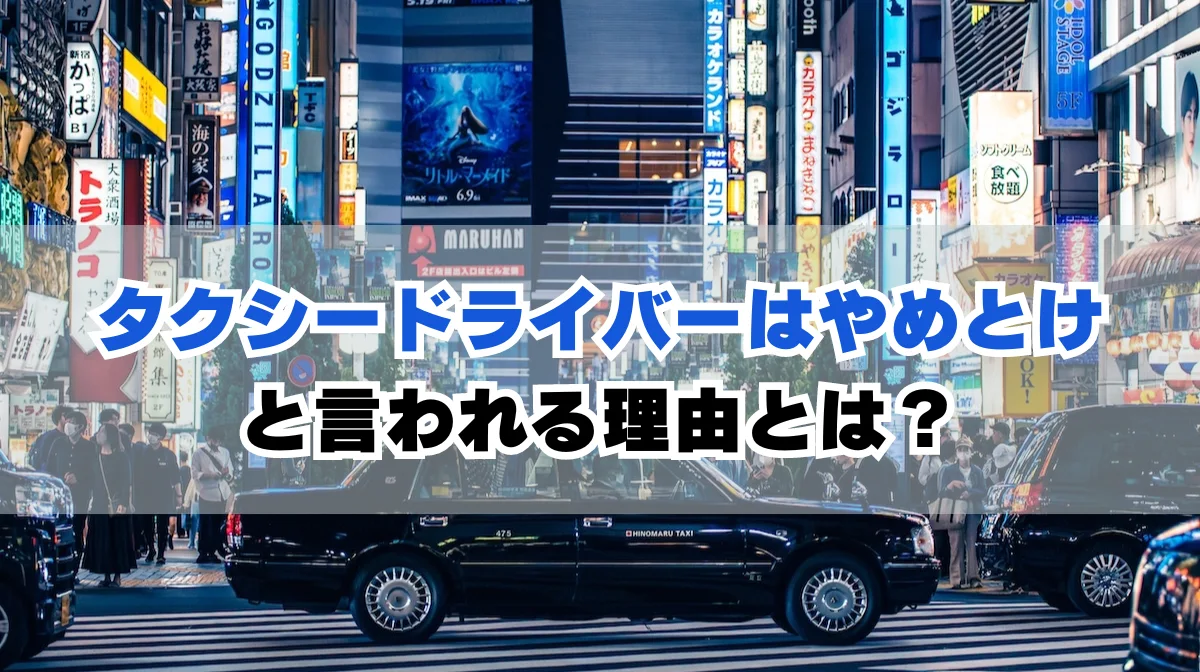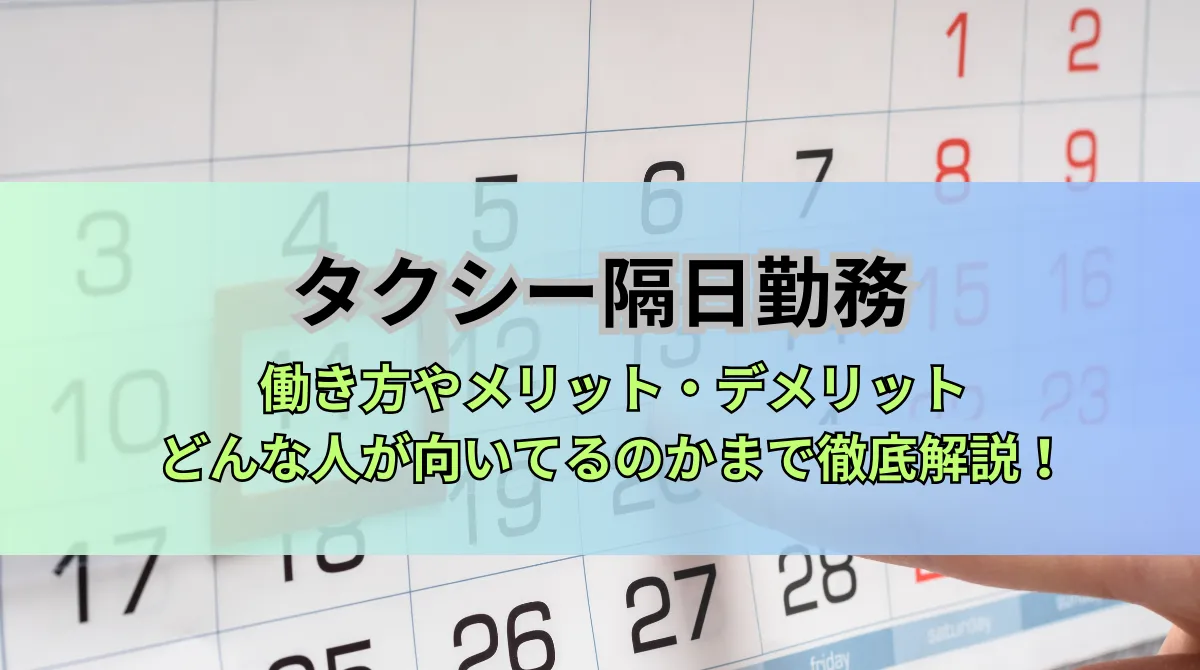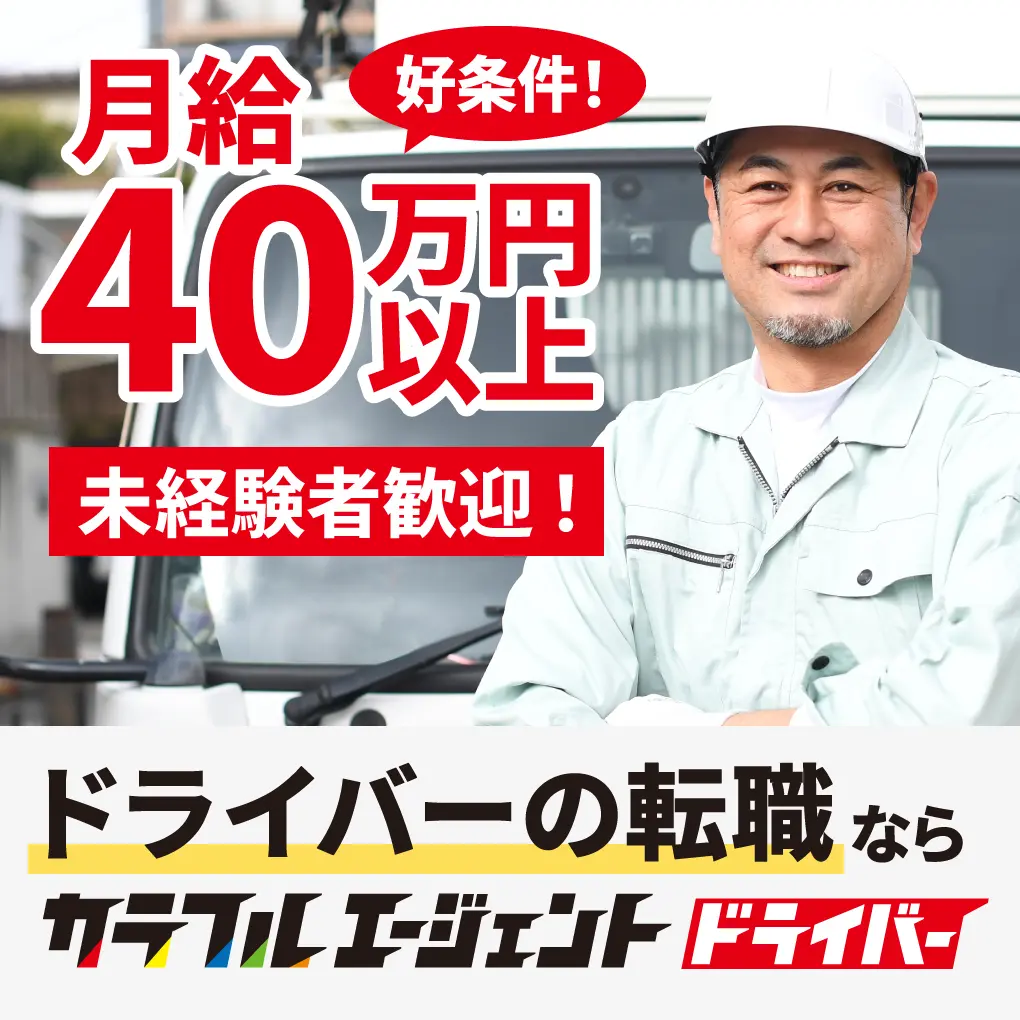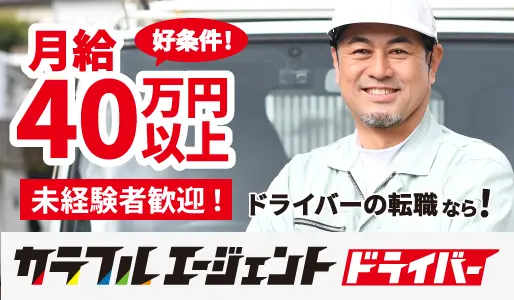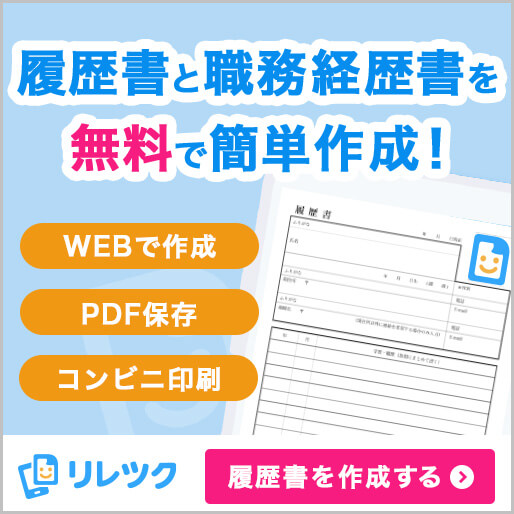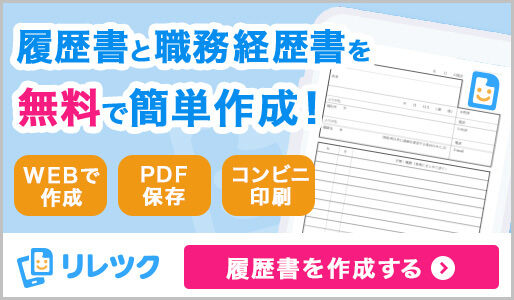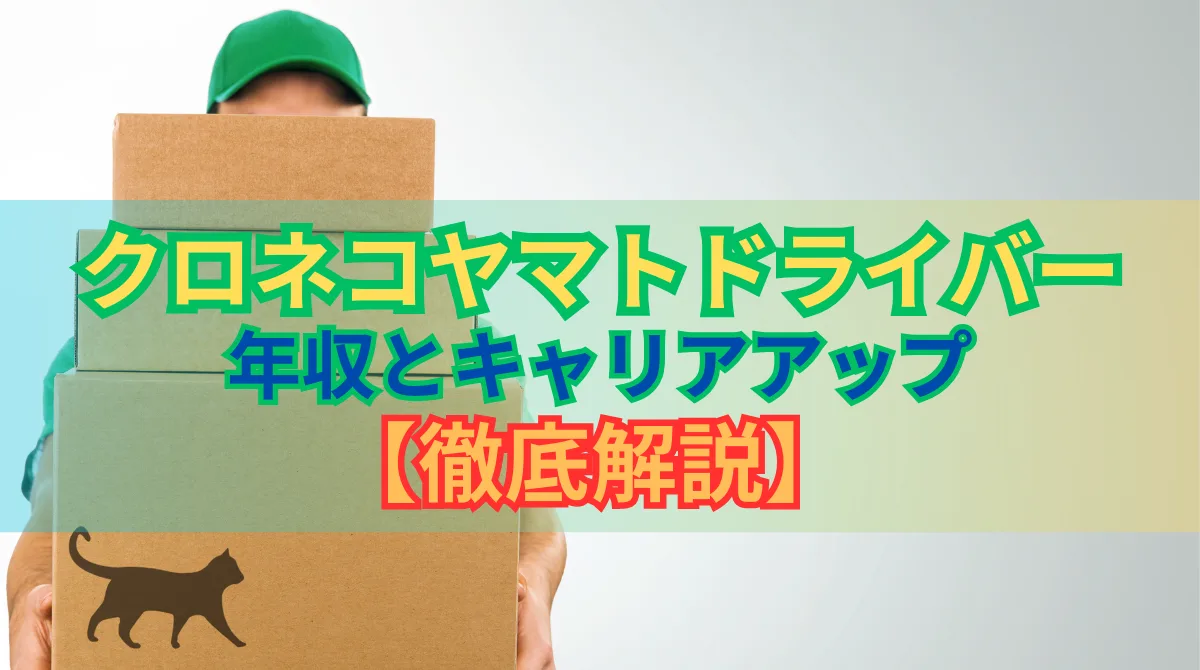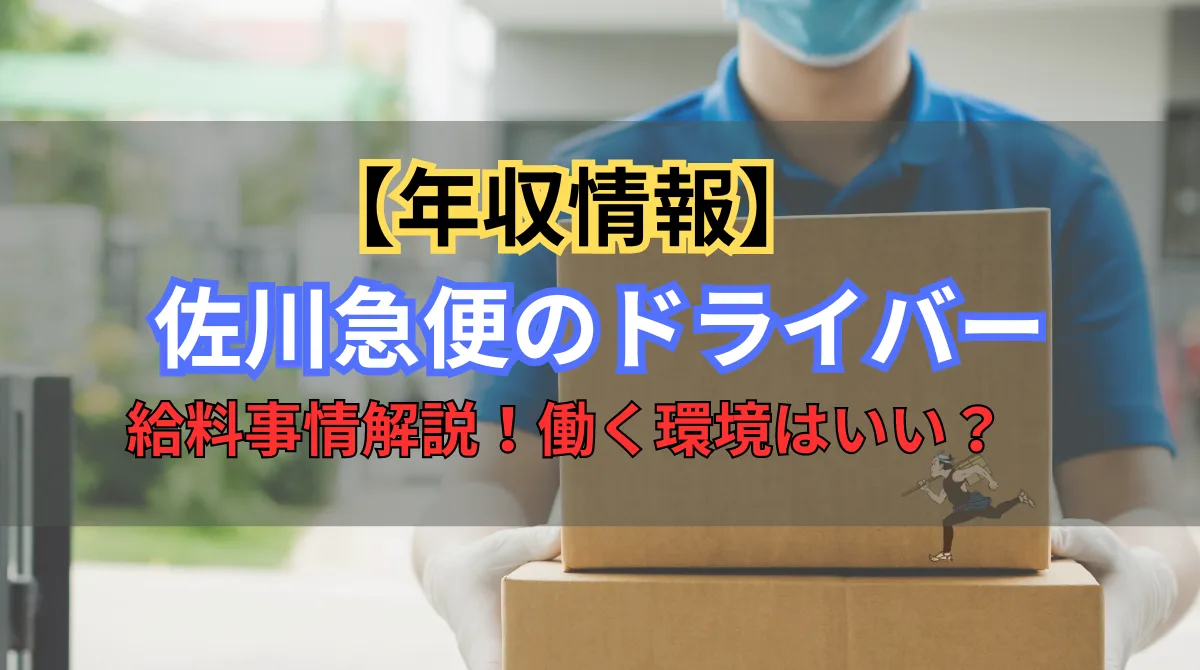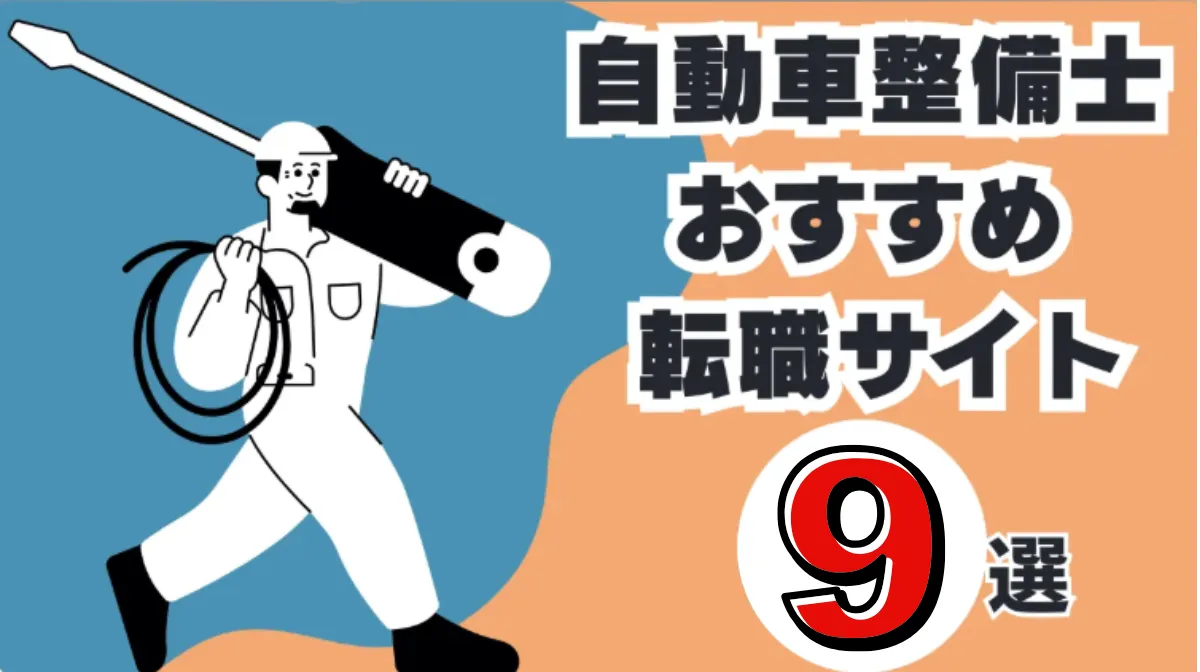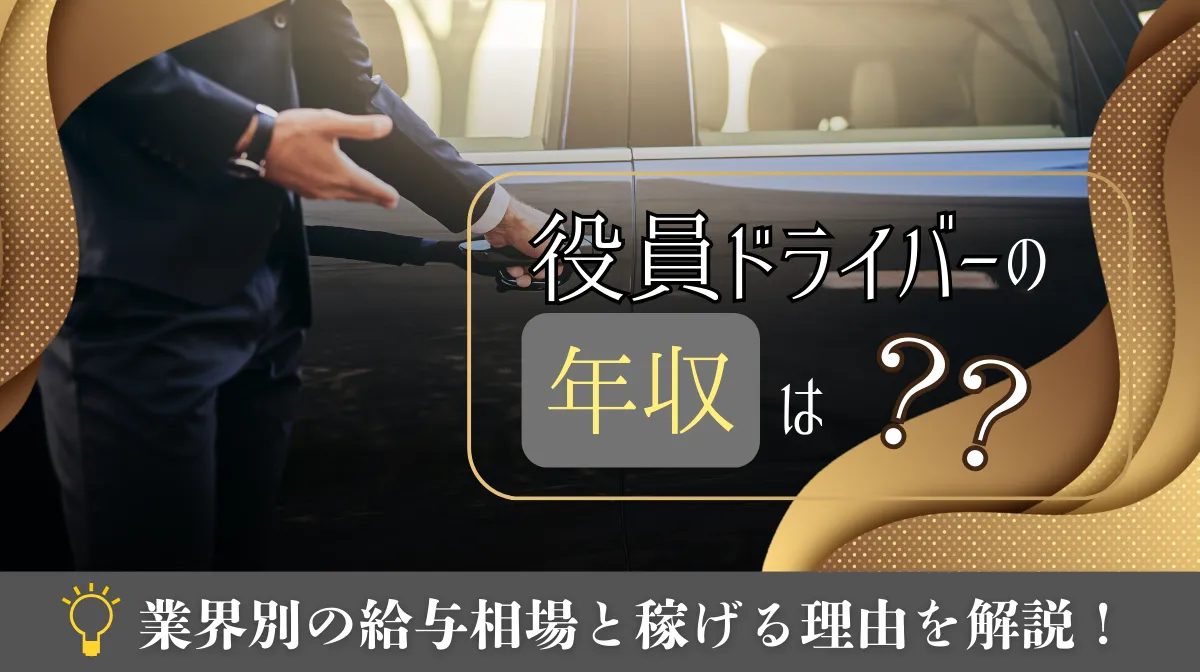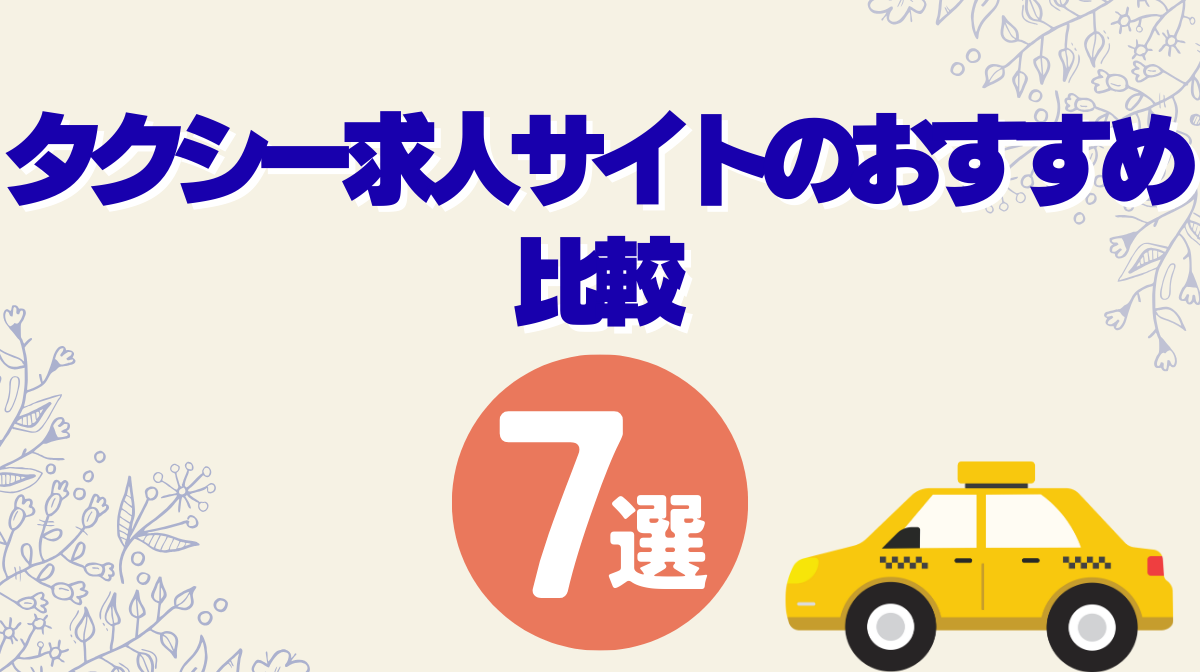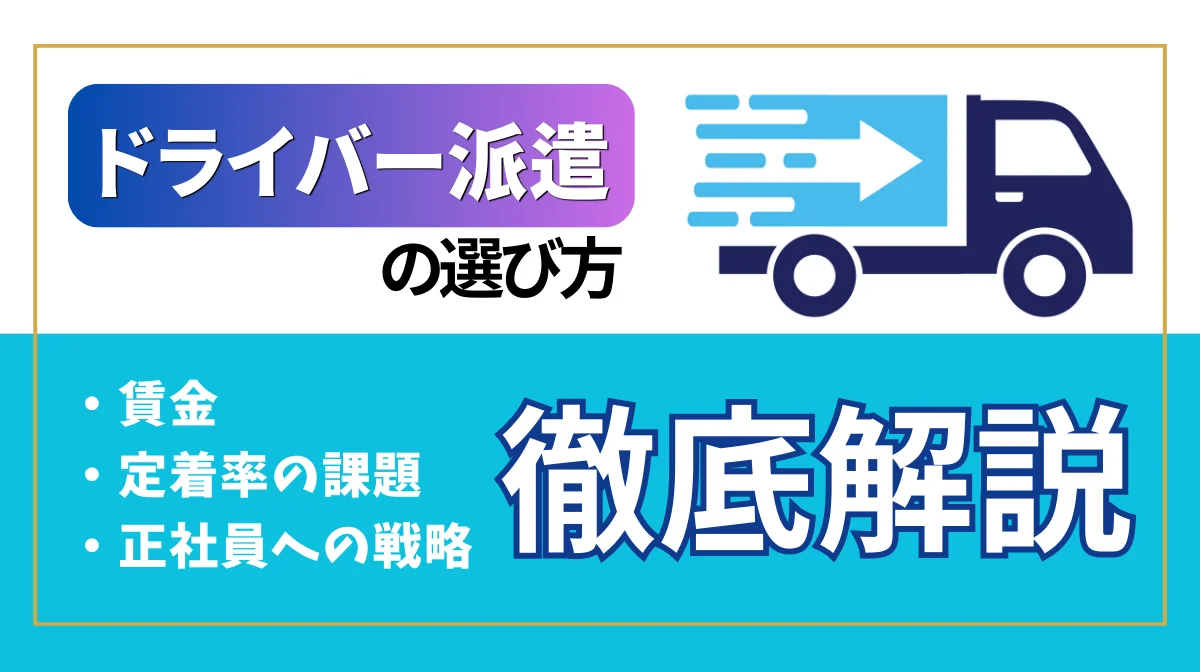タクシー運転手という仕事に関心を持ったとき、「何歳まで働けるのだろうか」「60代や70代からでも挑戦できるのだろうか」といった年齢に関する疑問は、多くの方が抱く疑問の一つかもしれません。
特に、定年後のセカンドキャリアとして検討する場合、法律上の制限や健康面のリスク、そして実際の採用状況は、大きな関心事でしょう。
この記事では、タクシー運転手の年齢制限に関する法的な根拠から、法人・個人タクシーそれぞれの実態、そしてシニア世代が安全に長く活躍するためのポイントまでを解説します。
- タクシー運転手の年齢に関する法的な根拠と実態
- 法人・個人タクシーそれぞれの定年や更新制度
- 60代・70代の採用状況と、シニアが安全に働くためのポイント
1.結論:法的な「年齢上限」はないが、実質的な「3つの壁」が存在する
壁 1:法律
年齢の「上限」を直接定める法律はありません。
壁 2:健康状態
安全に運転できる健康状態が法的に必須です。
壁 3:免許(下限)
法律が定めるのは「下限」年齢(19歳~)です。
結論から述べると、タクシー運転手として働くことについて、「何歳まで」という年齢の「上限」を直接定めた法律はありません。
しかし、実際には以下の3つの「法的な壁(あるいは基準)」が存在し、これらが実質的な制限として機能しています。
根拠(1):「何歳まで」を直接禁じる法律(道路交通法など)はない
日本の法律(道路交通法や旅客自動車運送事業に関する法令など)において、「〇歳になったら運転業務をしてはならない」といった、年齢の上限を定めた規定は存在しません。
これが、80代の現役ドライバーが実在する法的な理由です。
根拠(2):法律が求めるのは「安全に運転できる健康状態」
法律が年齢の上限を定めない代わりに厳しく求めているのが、「乗客の安全を守れる健康状態であること」です。
タクシー会社(事業者)は、法律に基づき、運転者に対して定期的な健康診断を実施する義務があります。
また、国土交通省もガイドラインを定め、健康管理の重要性を強く指導しています。
年齢に関わらず、医師の診断によって安全な運転が難しいと判断されれば、乗務することはできません。これが実質的な最大の「壁」となります。
根拠(3):法律が定めるのは「運転資格(二種免許)の年齢(下限)」
法律が明確に定めているのは「上限」ではなく「下限」です。
旅客運送に必要な「第二種運転免許(二種免許)」は、以前は21歳以上でなければ取得できませんでした 。しかし、人手不足への対策もあり、一定の条件を満たせば19歳からでも取得が可能になるよう、制度が変更されています 。
2.タクシー運転手の平均年齢と高齢化の現状
タクシー業界はドライバーの高齢化が進んでいると言われます。厚生労働省の統計によると、平均年齢は60歳にも達し、他の多くの職業と比べても高い水準です。
ここでは、データに基づき、なぜ高齢化が進むのか、その背景にある人手不足の実態を解説します。
平均年齢は60歳前後?
タクシードライバーの平均年齢
タクシー業界が高齢化しているという話は、耳にしたことがあるかもしれません。
実際、厚生労働省の調査によれば、タクシードライバーの平均年齢は60歳と報告されています。これは、他の多くの職業と比較しても高い水準です。
なぜ高齢化が進むのか(人手不足の背景)
既存ドライバーの高齢化
これまで業界を支えてきたドライバー層が定年退職の時期を迎えています。
新規参入者の減少
新たに二種免許を取得し、運転手になろうとする人が減少傾向にあります。
結果:深刻な人手不足
この状況において、元気で意欲のあるシニア層は、豊富な経験を持つ「貴重な労働力」となっています。
この背景には、業界全体が抱える構造的な人手不足があります。 具体的には、「既存ドライバーの高齢化」と「新規参入者の減少」という2つの側面が同時に進行しているためです。
高齢・障害・求職者雇用支援機構の調査によれば、これまで業界を支えてきたドライバー層が定年退職の時期を迎えている 一方で、新たに二種免許を取得してタクシー運転手になろうとする人の数が減少傾向にあると指摘されています 。
つまり、「辞める人」は増えているのに、「新しく入る人」が減っているため、深刻な人手不足が続いているのです。
この状況において、タクシー会社側も「豊富な経験」や「真面目な勤務態度」といったシニアならではの利点に着目しており 、元気で意欲のあるシニア層は貴重な労働力となっています。
参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構 (JEED)|高齢者雇用の実態調査
▼あわせて読みたい
タクシー運転手に必要な二種免許の取得条件、費用、期間について詳しく解説しています。会社の全額負担制度を活用すれば、初期投資なしでキャリアをスタートできます。
3.タクシー会社の採用年齢の実態と「年齢を重ねても活躍できる理由」
年齢を重ねても活躍できる理由
平均年齢が高い
=「高齢でも必要とされている」証拠です。
AIで代替困難
柔軟な働き方
資格取得支援
平均年齢が高いということは、裏を返せば「高齢であっても、業界から必要とされている」ということです。
実際、多くの中高年・シニア世代が新たにタクシー運転手として転職しており、60代はもちろん、70代からでも採用されるケースは珍しくありません。
理由1:AIや自動運転でも代替されにくい業務
「AIや自動運転が普及すると仕事がなくなるのでは?」という懸念もあるかもしれません。
しかし、特にタクシーのような「ドアtoドア」のサービスは、荷物の積み下ろしを手伝ったり、お客様の要望に柔軟に応えたりと、単に運転する以外の業務が多くあります。
こうした人間ならではの細やかな対応はAIやロボットでは代替しにくく、ドライバーの仕事がすぐに無くなる可能性は低いと考えられています。
理由2:柔軟な勤務形態(隔日勤務・短時間など)
タクシー業界特有の「隔日勤務(1日働いて1日休む)」や、定年後の再雇用における短時間勤務など、体力に合わせて柔軟な働き方を選びやすい点も、シニア世代が活躍できる理由です。
理由3:「二種免許」の取得支援制度が充実
二種免許を持っていない未経験者でも、入社後に会社が費用を全額負担して免許取得をサポートする制度が充実している会社が多いため、初期投資なしで新しいキャリアを始めやすい環境が整っています。
▼あわせて読みたい
タクシー運転手の年収や給与体系の仕組み、地域による収入差について詳しく解説しています。歩合制や賞与の仕組みを理解することで、収入の見通しが立てやすくなります。
■50代・60代からのタクシー転職をプロがサポート
カラフルエージェント ドライバーでは、シニア世代の採用に積極的なタクシー会社を多数ご紹介しています。
二種免許取得支援が充実した企業、再雇用制度が手厚い企業、体力に合わせた勤務形態を選べる企業など、あなたの希望に合った職場をキャリアアドバイザーが無料でご提案いたします。
▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら
4.「何歳まで働ける?」法人・個人タクシーの定年と更新制度

「何歳まで」の具体的な目安は、会社に勤務する「法人タクシー」か、自営業である「個人タクシー」かで異なります 。
(1) 法人タクシー:「65歳定年+75歳までの再雇用」が一般的
多くのタクシー会社では、一般企業と同様に60歳~65歳を「定年」として設定しています。
しかし、重要なのはその後の「再雇用(嘱託)制度」です 。
健康状態などに問題がなければ、70歳、あるいは75歳頃まで働くことができる制度を設けている会社が一般的です。これが、法人タクシーで働く場合の一つの目安となります。
(2) 個人タクシー:「75歳以上は1年更新」が実質的なライン
自営業である個人タクシーには「定年」という概念がありません。
ただし、事業を続けるためには国の「許可」を更新し続ける必要があります 。
この更新基準が年齢によって異なり、国土交通省の基準では、75歳以上になると「1年ごと」に許可の更新が必要とされています。
毎年、健康状態や違反の有無などをクリアし続ければ理論上は働き続けられますが、この「75歳」というのが一つの節目と見られています。
▼あわせて読みたい
タクシー転職で失敗・後悔しないために理解すべき働き方や収入の実態、会社選びのポイントを詳しく解説しています。転職前に必ず確認しておきたい情報が満載です。
5.なぜ「タクシー運転手はやめとけ」と言われる?リスクと対策のポイント
「タクシー運転手はやめとけ」という意見には、シニア世代が働く上での具体的なリスクが反映されている場合があります。
シニア世代がタクシー運転手になるリスク
シニア世代が直面する2つのリスク
リスク1:健康・体力への懸念
リスク2:事故率(統計データ)
リスク1:健康(視力・体力)と安全への懸念
長時間の運転は、視力や体力を消耗します。
特に夜間の運転は、加齢とともに見えづらさを感じることも増えるかもしれません。 日々の体調管理や、自身の体力の限界を把握することが非常に重要です 。
リスク2:事故率(統計データ)
残念ながら、統計データを見ると、高齢ドライバーによる事故の割合が高いことも事実として報告されています。
国土交通省が発表した最新の統計(令和5年版)によれば、タクシー運転手による事故のうち、65歳以上の運転者による事故の比率は、全国で約5割(51.4%)に達していることが示されています。
乗客の命を預かる仕事である以上、このリスクは客観的に認識し、人一倍の安全意識を持つ必要があります。
▼あわせて読みたい
「タクシー運転手はやめとけ」と言われるのは、イメージ先行で実務や給与形態などが知られていないことです。以下の記事ではやめとけと言われる理由から現在のタクシー業界のホワイトさまで解説します。
【対策】シニアのタクシードライバー転職のポイントと準備
安全に長く働くための「3つの準備」
リスクを回避し、活躍するためのポイントです。
健康状態の客観的把握
働きやすい会社選び
無理のない計画
これらのリスクを理解した上で、安全に長く働くためには、次のような「準備」と「対策」が転職のポイントとなります。
(1) 自身の健康状態を客観的に把握する(健康診断)
まずは、自身の健康状態を客観的に知ることがスタートです。
転職活動を始める前に健康診断を受け、医師から長時間の運転業務に耐えうる健康状態であるか、客観的な意見をもらうことも有効です。
二種免許取得に必要な身体要件
視力
両眼で0.8以上、かつ片眼で各0.5以上。
深視力
三桿(さんかん)法検査での平均誤差が2センチメートル以下。
視力・深視力ともに、眼鏡やコンタクトレンズによる矯正可。
聴力
10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。
補聴器の使用可。
色彩識別
赤・青・黄の3色が識別できること。
運動能力
ハンドルやブレーキなど、運転に必要な操作が確実にできること。
(2) シニアが働きやすい会社を選ぶ(再雇用・勤務形態)
会社によって、再雇用制度の手厚さや、選択できる勤務形態は異なります。
「定年後のシニア採用実績が豊富か」
「体力に合わせた短時間勤務が可能か」
「日中だけの勤務(日勤)は選べるか」
など、無理なく働ける環境が整っている会社を選ぶことが重要です。
(3) 無理のない働き方を計画する(年金との併用など)
60代以降の働き方として、年金を受給しながら、タクシーの仕事で収入を補うという働き方 も選択肢になります。
若い世代と同じように収入の最大化を目指すのではなく、「健康維持」を最優先とし、体力的な負担と収入のバランスが取れる働き方を計画することが、長く続ける秘訣です。
▼あわせて読みたい
タクシー運転手の隔日勤務について、勤務形態の特徴や適性、メリット・デメリットを詳しく解説しています。体力に合わせた柔軟な働き方を選ぶための参考にしてください。
■健康管理を重視する優良タクシー会社をご紹介
安全に長く働くためには、健康管理体制が整った会社選びが重要です。
カラフルエージェント ドライバーでは、定期健康診断の実施はもちろん、日勤専属勤務が可能な会社、短時間勤務制度がある会社など、シニア世代が無理なく働ける環境を提供する企業を厳選してご紹介しています。専門アドバイザーが丁寧にサポートいたします。
▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら
6.80代の現役ドライバーは実在する?
大阪エリアのタクシードライバー年齢分布
令和7年11月4日時点(実数データ)
前述の通り、法律上の上限がないため、80代、あるいは90代の現役ドライバーも実在します。
最新の統計データ(令和7年11月時点)によれば、大阪エリアでは75歳以上のドライバーが合計3,181人(75~79歳: 2,505人、80~84歳: 616人、85歳以上: 60人)活躍されています。
これは、全ドライバー(22,905人)の約13.9%に相当する数字です。
これは決して大多数ではありませんが、「健康であれば年齢に関わらず活躍できる」というタクシー業界の特性を、最新のデータが明確に象徴しています。
参考:公益財団法人大阪タクシーセンター|年齢別運転者数及び運転者証(事業者乗務証)交付数について
▼あわせて読みたい
タクシー運転手に向いている人の特徴や必要なスキル、仕事内容を詳しく解説しています。未経験でも充実した研修制度で安心してスタートできる理由がわかります。
7.タクシー運転手は年齢制限がなく、健康と働き方の計画が重要
タクシー運転手として働ける期間は、法律で定められた「年齢の数字」で決まるわけではありません。 最も重要なのは、乗客の安全を守れる「健康状態」を維持できるか、という点です。
業界の人手不足を背景に、60代や70代からでもセカンドキャリアとして挑戦できる門戸は開かれています。
「やめとけ」と言われるリスクを正しく理解し、健康管理を徹底すること、そして何よりも自身の体力に合った無理のない働き方を計画し、それ(年金併用や短時間勤務など) を認めてくれる会社を選ぶことです。
これら「準備」と「計画」こそが、シニア世代がタクシー運転手として長く働き続けるための鍵となります。